アライグマの好物は何?【果物や小動物が大好物】被害を予防する5つの対策と食べ物の管理法

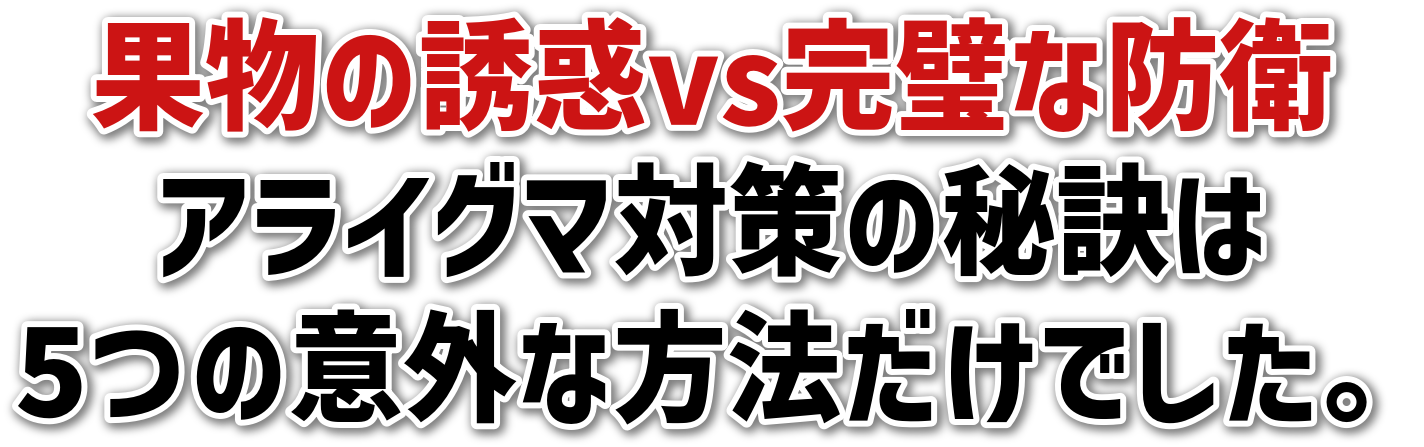
【この記事に書かれてあること】
アライグマの好物って知っていますか?- アライグマが特に好む果物や野菜のリスト
- アライグマの食性の季節変化と被害パターン
- アライグマと他の動物との食性比較
- アライグマの栄養摂取量と人間との差
- 食べ物を狙わせない5つの対策方法
実は、この可愛らしい見た目の動物、食べ物の好みがはっきりしているんです。
果物や小動物が大好物なんですよ。
でも、これが問題を引き起こすことも。
庭の果物や野菜が次々と食べられてしまうなんて経験、ありませんか?
そんなアライグマの食性を知ることで、効果的な対策が立てられます。
この記事では、アライグマの好物リストから季節による食性の変化、そして対策方法まで詳しく解説します。
アライグマとの知恵比べ、一緒に始めてみませんか?
【もくじ】
アライグマの好物とは?被害対策の第一歩

アライグマが大好物な「果物」トップ5!
アライグマが最も好む果物は、甘くて柔らかいものです。特に人気なのは柿、ぶどう、いちご、すいか、梨の5つです。
これらの果物は、アライグマにとってたまらない誘惑なんです。
「甘くておいしそう!」とアライグマの目が輝きます。
柿は特に人気で、熟れた柿を見つけると夢中になって食べてしまいます。
アライグマがこれらの果物を好む理由は、次の3つです。
- 高い栄養価:果物は糖分とビタミンが豊富
- 水分補給:果物は水分を多く含む
- 簡単に食べられる:柔らかくて手で簡単にちぎれる
「おいしくて、栄養もあって、食べやすい。最高の食べ物じゃない!」とアライグマは考えています。
果物の木がある庭は、アライグマにとって天国のような場所。
「ここなら毎日おいしい果物が食べられる!」と、アライグマは何度も通ってくるでしょう。
対策としては、果物が熟す前に収穫するか、ネットで覆うのが効果的です。
アライグマに「残念、今日は食べられないや」と思わせることが大切なのです。
野菜被害の主犯!アライグマが狙う「柔らかい食材」
アライグマが野菜の中で特に好むのは、柔らかくて水分の多いものです。トウモロコシ、トマト、なす、かぼちゃなどが主な標的となります。
これらの野菜は、アライグマにとって絶好の食べ物なんです。
「柔らかくておいしい!しかも水分たっぷり!」とアライグマは喜びます。
特にトウモロコシは大好物で、畑に入り込んでは実を食べ荒らしてしまいます。
アライグマがこれらの野菜を好む理由は、次の3つです。
- 食べやすさ:柔らかい texture が口に合う
- 水分補給:野菜から水分も摂取できる
- 栄養価:ビタミンやミネラルが豊富
「おいしくて、栄養もあって、のどの渇きも潤せる。最高の食べ物じゃない!」とアライグマは考えています。
家庭菜園や畑がある場合、アライグマにとってはごちそうの宝庫。
「ここなら毎日新鮮な野菜が食べられる!」と、アライグマは何度も通ってくるでしょう。
対策としては、野菜の周りに忌避剤を撒いたり、電気柵を設置したりするのが効果的です。
アライグマに「ここの野菜は食べられないや」と思わせることが大切なのです。
野菜を守るためには、アライグマの好みを知り、それに応じた対策を取ることが重要です。
意外と知らない!アライグマが好む「小動物」リスト
アライグマは果物や野菜だけでなく、小動物も好んで食べます。特に人気なのは、カエル、小魚、昆虫、小鳥の卵などです。
これらはタンパク源として重要なんです。
「動くものは全部おいしそう!」とアライグマは考えています。
特にカエルは大好物で、池や湿地を見つけると夢中になって探し回ります。
アライグマがこれらの小動物を好む理由は、次の3つです。
- 高タンパク:成長に必要な栄養素が豊富
- 捕まえやすさ:小さくて動きが遅い
- 美味しさ:肉の旨味が強い
「動くものを追いかけるのは楽しい!しかも栄養満点!」とアライグマは興奮します。
庭に池や小川がある場合、アライグマにとっては格好の狩り場になってしまいます。
「ここなら毎日新鮮な肉が食べられる!」と、アライグマは何度も通ってくるでしょう。
対策としては、池や湿地にネットを張ったり、庭に小動物を寄せ付けない環境作りをしたりするのが効果的です。
アライグマに「ここでは狩りができないや」と思わせることが大切なのです。
小動物も大切な生態系の一部。
アライグマから守ることで、庭の生態系のバランスを保つことができます。
アライグマの食性を理解し、適切な対策を取ることが、人間と野生動物の共生につながるのです。
アライグマの食欲が「最も旺盛」になる季節は?
アライグマの食欲が最も旺盛になるのは、秋です。これは冬に向けて体に脂肪を蓄える必要があるためです。
「冬を乗り越えるためには、今のうちにたくさん食べなきゃ!」とアライグマは必死になります。
秋になると、アライグマの食欲は通常の1.5倍から2倍に増加します。
この時期のアライグマの食欲の特徴は、次の3つです。
- 量の増加:1日の摂取カロリーが大幅に増える
- 高カロリー志向:脂肪分の多い食べ物を好む
- 貯蔵本能:食べ物を隠す行動が増える
「食べられるものは全部食べつくさなきゃ!」とアライグマは考えています。
果樹園や家庭菜園にとって、秋は最大の危機。
「ここなら冬の準備ができる!」と、アライグマは執拗に通ってくるでしょう。
対策としては、収穫時期を早めたり、強力な防護柵を設置したりするのが効果的です。
アライグマに「ここの食べ物は手に入らないや」と思わせることが大切なのです。
秋は実りの季節。
人間にとっても大切な時期です。
アライグマの食欲が最も高まる時期を知り、それに応じた対策を取ることで、収穫物を守ることができます。
アライグマの生態を理解し、適切な対策を講じることが、人間と野生動物の共存への第一歩となるのです。
アライグマの食べ物vsタヌキの食べ物「違いを比較」
アライグマとタヌキ、どちらも雑食性ですが、その食性には明確な違いがあります。アライグマの方がより人間の食べ物に興味を示し、果物や野菜への執着が強いのです。
「人間の食べ物ってすごくおいしそう!」とアライグマは考えます。
一方、タヌキは「自然の中にある食べ物で十分」と思っているようです。
両者の食性の違いは、次の3点に現れます。
- 果物への執着:アライグマ>タヌキ
- 昆虫食:タヌキ>アライグマ
- 人間の残飯:アライグマ>タヌキ
「人間の庭や畑は最高の食事処!」とアライグマは考えています。
庭や畑にとって、アライグマはタヌキよりも深刻な脅威となります。
「ここなら毎日おいしいものが食べられる!」と、アライグマは何度も通ってくるでしょう。
対策としては、アライグマに特化した防護策を講じる必要があります。
例えば、果樹には反射板を設置し、ゴミ箱には強固な蓋をするなどです。
アライグマに「ここの食べ物は手に入らないや」と思わせることが大切なのです。
アライグマとタヌキ、どちらも日本の生態系の一部です。
しかし、アライグマの方が人間の生活圏に入り込みやすい性質を持っています。
両者の食性の違いを理解し、適切な対策を講じることで、人間と野生動物の共存が可能になるのです。
自然との調和を保ちつつ、私たちの生活を守る。
そんなバランスの取れた対策が求められているのです。
アライグマの食性を知って被害を防ぐ!

アライグマの食欲vs人間の対策「勝負の行方」に注目!
アライグマの旺盛な食欲に対し、人間の対策は後手に回りがちです。でも、知恵を絞れば勝機はあるんです!
アライグマの食欲は本当にすごいんです。
「お腹すいた!何でも食べちゃうぞ!」という感じで、庭や畑を荒らしてしまいます。
でも、人間にも対抗する方法はあるんです。
アライグマの食欲の特徴は、次の3つです。
- 旺盛な食欲:体重の5〜10%を毎日摂取
- 多様な食性:果物、野菜、小動物まで何でも食べる
- 高い学習能力:新しい食べ物にもすぐ適応
例えば、果樹園なら高めのフェンスを設置。
「えっ、入れないの?」とアライグマを驚かせましょう。
においや音、光を使った対策も有効です。
「うわっ、このにおい苦手!」「きゃっ、急に光った!」とアライグマを怖がらせるんです。
ただし、アライグマは賢いので、同じ対策を続けていると慣れてしまいます。
「あれ?この光、もう怖くないや」なんて思われちゃいます。
だから、対策は定期的に変えることが大切です。
人間とアライグマの知恵比べ。
頭をフル回転させて、アイデアを絞り出しましょう。
きっと、あなたの庭や畑を守れるはずです。
がんばれ、人間チーム!
春と秋の食性の違い「季節で変わる被害パターン」
アライグマの食性は季節によって大きく変化します。春と秋では、まるで別の動物のような食べ方をするんです。
春のアライグマは、新芽や若葉、小動物の卵を主に食べます。
「やった!新鮮な芽が出てきた!」と、庭の植物を荒らしてしまうんです。
一方、秋のアライグマは果物や野菜を中心に食べます。
「うわ?、おいしそうな果物がたくさん!」と、果樹園や畑を襲撃しちゃうんです。
季節による食性の変化は、次のようになります。
- 春:新芽、若葉、小動物の卵
- 夏:果物、野菜、昆虫
- 秋:熟した果実、穀物、木の実
- 冬:残り物、小動物、木の皮
春なら新芽を守るネットを、秋なら果樹園のフェンスを強化するといった具合です。
例えば、春に庭に植えたばかりの花が次々と食べられてしまったら、きっとアライグマの仕業。
「あれ?せっかく植えた花がなくなってる!」なんて悲しい思いをしないために、春先は特に注意が必要です。
秋になったら、今度は果物に要注意。
「あ?、育てたリンゴが全部なくなっちゃった!」なんて悲劇にならないよう、収穫前の果物をしっかり守りましょう。
季節の変化を意識して対策を立てれば、アライグマの被害をグっと減らせます。
自然のリズムに合わせた対策で、庭や畑を守りましょう。
アライグマの栄養摂取量vs人間「食欲の差」に驚愕!
アライグマの食欲は、人間の想像をはるかに超えています。その驚くべき栄養摂取量を知れば、対策の重要性がよくわかるはずです。
アライグマは、なんと体重の5〜10%ものカロリーを毎日摂取します。
人間に例えると、60kgの人が3〜6kgもの食べ物を毎日平らげるようなものです。
「えっ、そんなに食べるの!?」と驚いてしまいますよね。
アライグマと人間の食欲の差は、次の点に現れます。
- 摂取カロリー:アライグマは体重比で人間の2〜3倍
- 食事の頻度:アライグマは一日中食べ歩く
- 食べ物の種類:アライグマは何でも食べる
例えば、たった1匹のアライグマが、一晩で小さな家庭菜園を丸坊主にしてしまうことだってあります。
「昨日まであんなに元気だった野菜が…」なんて悲しい経験をした人も多いはず。
アライグマの食欲は、まるで掃除機のよう。
庭に置いてあるものを次々と吸い込んでいくんです。
「ごくごく、もぐもぐ、まだまだ食べられる!」というアライグマの声が聞こえてきそうです。
この驚異的な食欲に対抗するには、徹底的な対策が必要です。
食べ物を完全に隠す、強力な忌避剤を使うなど、アライグマの食欲を上回る策を考えましょう。
アライグマの食欲の強さを知れば、被害の深刻さがよくわかります。
でも、知識は力。
この情報を活かして、しっかりと対策を立てていきましょう。
アライグマの嗅覚vs人間の防御「知恵比べ」の結果は?
アライグマの嗅覚は驚くほど鋭敏で、人間の防御策をいとも簡単に突破してしまうことがあります。でも、人間の知恵を総動員すれば、この嗅覚王者に勝つチャンスはあるんです。
アライグマの嗅覚は、人間の約100倍も鋭いと言われています。
「おっ、おいしそうな匂いがする!」と、遠くからでも食べ物の位置を嗅ぎ分けてしまうんです。
この嗅覚の鋭さは、次のような特徴があります。
- 遠距離探知:数百メートル先の食べ物も感知
- 地中探知:土の下の根菜類も匂いで発見
- 微量探知:ほんの少量の残り香でも追跡可能
実は、この鋭い嗅覚を逆手にとった対策が効果的なんです。
例えば、アライグマの嫌いな匂いを利用する方法があります。
「うっ、この匂い苦手!」とアライグマが思うような強い香りのハーブや、唐辛子スプレーを庭に撒くんです。
アライグマの鼻をくすぐる作戦、というわけです。
また、食べ物の匂いを完全に遮断する方法も有効です。
密閉容器を使ったり、二重三重の包装をしたりして、「あれ?匂いがしないぞ?」とアライグマを困らせるんです。
人間の知恵と工夫次第で、アライグマの鋭い嗅覚も攻略できます。
匂いを利用したり、匂いを消したり。
アライグマの得意技を逆手にとる戦略で、庭や畑を守りましょう。
頭をフル回転させて、アライグマに勝つアイデアを絞り出してください。
きっと、あなたならできるはずです!
アライグマ対策!食べ物を狙わせない5つの方法

果物の木に「反射板」設置!意外な効果に注目
果物の木に反射板を設置すると、アライグマを効果的に撃退できます。その仕組みとは?
アライグマは夜行性で目がキラキラ光ることで有名ですよね。
実は、その目の特徴を逆手にとった対策が「反射板」なんです。
「キラッ!」という突然の光に、アライグマはビックリしちゃうんです。
反射板の効果は、次の3つのポイントにあります。
- 突然の光:予期せぬ瞬間に目に入る光が苦手
- 動く反射:風で揺れる反射板が不規則な光を作り出す
- 持続的な効果:電気を使わないので長期間使える
古いコンパクトディスクや、アルミホイルを貼った厚紙を紐で木に吊るすだけ。
「よいしょ」と木に登ろうとしたアライグマも、「うわっ、まぶしい!」と驚いて逃げ出しちゃいます。
ただし、注意点もあります。
反射板は風で動くことが大切なので、あまりきつく固定しないようにしましょう。
「ふわふわ」揺れる感じが、アライグマには不気味に感じるんです。
また、定期的に位置を変えるのもおすすめです。
同じ場所だとアライグマが慣れてしまうので、「あれ?今日は違う場所で光ってる!」と思わせることが大切です。
この方法なら、お金をかけずに効果的な対策ができますよ。
果物の木を守りながら、アライグマとの知恵比べを楽しんでみてはいかがでしょうか。
庭に「唐辛子スプレー」散布!強烈な香りで撃退
唐辛子スプレーを庭に散布すると、アライグマを効果的に寄せ付けません。その秘密は強烈な刺激臭にあるんです。
アライグマは鼻がとても敏感。
そのため、強い刺激臭には弱いんです。
「うっ、この臭い!」とアライグマが思わず後ずさりしてしまうほどの効果があります。
唐辛子スプレーの効果は、次の3つのポイントにあります。
- 強烈な刺激:鼻や目に染みる成分がアライグマを寄せ付けない
- 持続性:雨に濡れても効果が続く
- 自然由来:化学物質ではないので環境にやさしい
唐辛子パウダーを水で薄めて、スプレーボトルに入れるだけ。
「シュッシュッ」と庭の周りに吹きかけると、アライグマの侵入を防げます。
ただし、使用する際は注意が必要です。
風上から散布し、自分の目や鼻に入らないように気をつけましょう。
「あちち!」なんて自分が困っちゃうと元も子もありません。
また、ペットがいる家庭では使用を控えた方が良いでしょう。
「わんわん!」と吠えながら庭を走り回る愛犬が、唐辛子スプレーで困っちゃうかもしれません。
効果を持続させるには、定期的な散布が大切です。
雨が降ったり、時間が経ったりすると効果が薄れるので、週に1〜2回のペースで散布しましょう。
「よし、今日も庭を守るぞ!」という気持ちで続けることが大切です。
この方法で、アライグマを寄せ付けない庭づくりができますよ。
自然の力を借りて、アライグマ対策を進めてみましょう。
「ソーラーライト」で夜間照明!突然の光に弱点あり
ソーラーライトを使った夜間照明は、アライグマ対策に効果的です。突然の光に弱いアライグマの特性を利用した、賢い方法なんです。
アライグマは夜行性で、暗闇に適応した目を持っています。
そのため、急に明るくなると「うわっ!」と驚いてしまうんです。
この反応を利用するのが、ソーラーライトによる対策です。
ソーラーライトの効果は、次の3つのポイントにあります。
- 突然の点灯:動きを感知して光るタイプが特に効果的
- 省エネ:太陽光で充電するので電気代がかからない
- 設置の簡単さ:配線不要で、どこにでも置ける
庭の入り口や、果樹の周りなど。
「よいしょ」と乗り越えようとした瞬間に「パッ!」と光れば、アライグマも「びっくり!」して逃げ出すでしょう。
ただし、注意点もあります。
人の目にも眩しいので、寝室の窓の近くには置かないようにしましょう。
「まぶしくて眠れない!」なんてことになったら、本末転倒ですからね。
また、アライグマは賢い動物なので、同じ場所に長く置いていると慣れてしまう可能性があります。
「またあの光か…」と思われないよう、定期的に位置を変えるのがコツです。
ソーラーライトは、環境にもお財布にも優しい対策方法。
「エコでお得、しかも効果的!」という、一石三鳥の方法と言えますね。
夜の庭を明るく照らして、アライグマを寄せ付けない環境を作りましょう。
「アンモニア水」で臭い攻撃!鼻の敏感さを逆手に
アンモニア水を使った臭い攻撃は、アライグマの鋭い嗅覚を逆手に取った効果的な対策です。強烈な臭いで、アライグマを寄せ付けません。
アライグマの鼻は非常に敏感。
人間の100倍以上の嗅覚を持っているんです。
そのため、強い臭いには特に弱いんです。
「うっ、この臭い!」とアライグマが思わずのけぞるほどの効果があります。
アンモニア水の効果は、次の3つのポイントにあります。
- 強烈な刺激臭:アライグマの鼻を強く刺激する
- 広範囲への効果:気化して広い範囲をカバーする
- 持続性:効果が長く続く
アンモニア水を染み込ませた布を、庭の数カ所に置くだけ。
「プンプン」と臭いが広がって、アライグマを遠ざけます。
特に、アライグマが侵入しそうな場所に置くと効果的です。
ただし、使用する際は十分な注意が必要です。
アンモニアは強い刺激臭を持つため、人間にも不快感を与えます。
「げほげほ」とむせてしまうほど強いので、取り扱いには気をつけましょう。
また、植物にも影響を与える可能性があるので、直接植物にかからないよう注意が必要です。
「せっかく育てた花が枯れちゃった…」なんてことにならないよう、適切な場所選びが大切です。
効果を持続させるには、定期的な交換が必要です。
1週間に1回程度、新しいアンモニア水に交換しましょう。
「よし、今週も庭を守るぞ!」という気持ちで続けることが大切です。
この方法で、アライグマを寄せ付けない環境づくりができますよ。
ただし、強力な臭いなので、近所迷惑にならないよう配慮することも忘れずに。
アライグマと上手に付き合いながら、庭を守りましょう。
「動く風車」で視覚的威嚇!不気味な動きに要注意
動く風車を庭に設置すると、アライグマに対して視覚的な威嚇効果があります。不規則に動く物体が、アライグマを怖がらせるんです。
アライグマは新しい環境や予測できない動きに対して警戒心が強いんです。
そのため、くるくる回る風車や、ひらひらと動くピンホイールは「うわっ、なんだあれ!?」とアライグマを驚かせます。
動く風車の効果は、次の3つのポイントにあります。
- 不規則な動き:風の強さで回転速度が変わり、予測不能
- 視覚的効果:キラキラ光る素材を使うとさらに効果的
- 音の効果:カラカラという音も威嚇に一役買う
市販の風車やピンホイールを庭の数カ所に立てるだけ。
手作りするなら、ペットボトルを加工して羽根を付ければOK。
「よいしょ」と庭に入ろうとしたアライグマも、クルクル回る風車を見て「ひえー!」と逃げ出すかもしれません。
ただし、注意点もあります。
風車は風がないと動かないので、風通しの良い場所に設置しましょう。
「せっかく置いたのに動かない…」では効果がありません。
また、人間の目にも気になる場合があるので、寝室の窓の近くは避けた方が良いでしょう。
「夜中にカラカラ音がして眠れない!」なんてことになったら困りますからね。
効果を持続させるには、定期的に位置を変えるのがコツです。
同じ場所だとアライグマが慣れてしまうので、「あれ?今日は違う場所にある!」と思わせることが大切です。
この方法なら、お金をかけずに楽しみながら対策ができますよ。
庭を守りつつ、風車のある素敵な庭づくりを楽しんでみてはいかがでしょうか。
アライグマ対策が、新しい庭の魅力づくりにつながるかもしれませんよ。