アライグマが庭に来る理由とは【果物や野菜が豊富だから】庭の魅力を減らし、追い払う7つの効果的な方法

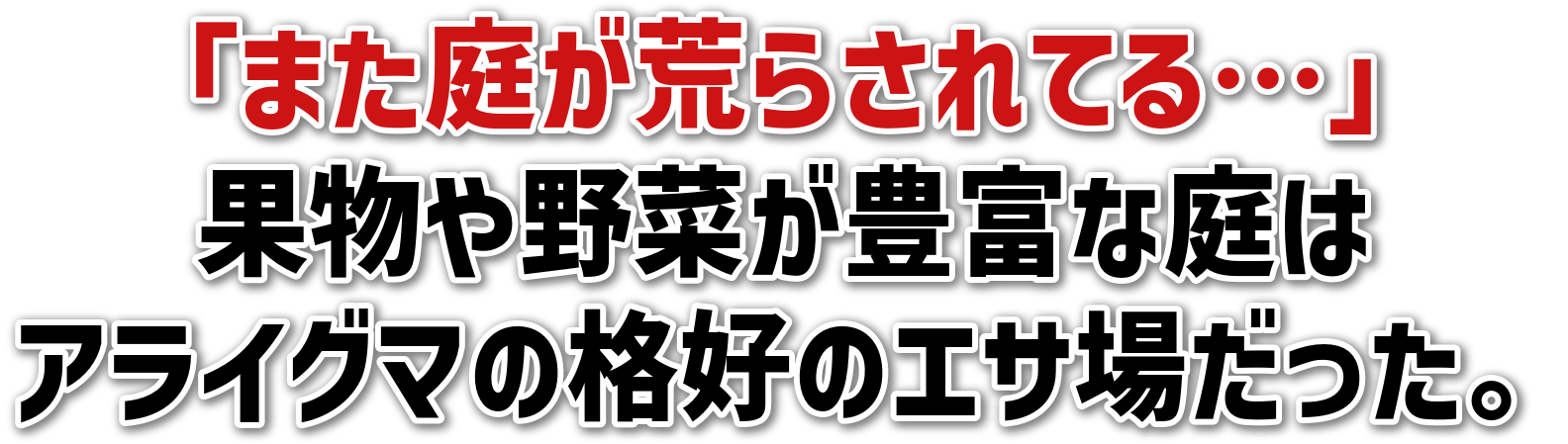
【この記事に書かれてあること】
庭に突然アライグマが現れて困っていませんか?- 庭は果物や野菜が豊富でアライグマの格好のエサ場に
- 水場や茂みが隠れ家として魅力的
- 夜行性のため深夜から早朝が活動のピーク
- 放置すると植物の食害や土壌の掘り返し被害が深刻化
- 5つの裏技を活用してアライグマを効果的に追い払う
実は、あなたの庭はアライグマにとって魅力的な食事処になっているかもしれません。
果物や野菜が豊富な庭は、アライグマの格好のエサ場。
しかも、水場や茂みは絶好の隠れ家に。
でも、大丈夫。
この記事では、アライグマが庭に来る理由を詳しく解説し、さらに驚くほど簡単な5つの裏技で撃退する方法をお教えします。
「もう庭を荒らされたくない!」そんなあなたの願いを叶える秘策がここにあります。
【もくじ】
アライグマが庭に来る理由と被害の実態

果物や野菜が「豊富な食料源」になっている!
庭に果物や野菜があると、アライグマにとって魅力的な食事処になってしまいます。アライグマは雑食性で、特に甘くて栄養価の高い果物や野菜が大好物なんです。
「うわっ!せっかく育てた野菜がみんな食べられちゃった…」
こんな悲しい経験をした人も多いのではないでしょうか。
アライグマは知能が高く、一度おいしい食べ物があると覚えると、繰り返し訪れるようになります。
彼らにとって、あなたの庭は24時間営業の無料レストランのようなものなのです。
アライグマが特に好む果物や野菜には以下のようなものがあります:
- イチゴ
- ブドウ
- スイカ
- トマト
- トウモロコシ
- カボチャ
「でも、せっかく育てた野菜や果物を諦めるわけにはいかない!」そう思いますよね。
大切なのは、アライグマを寄せ付けない工夫をすることです。
例えば、収穫時期が近づいたら防鳥ネットで覆ったり、収穫をこまめに行ったりするのが効果的です。
アライグマの被害を防ぐには、彼らの食べ物探しの習性を理解し、対策を立てることが重要なんです。
水場や茂みが「隠れ家」として魅力的
アライグマが庭に来る理由は、食べ物だけではありません。水場や茂みは、彼らにとって理想的な隠れ家になるのです。
「えっ、うちの庭にそんな場所があるの?」と思われるかもしれません。
しかし、アライグマの目線で見ると、意外なところが絶好の隠れ家に見えるんです。
アライグマが好む隠れ家の特徴は以下のとおりです:
- 日中の日差しを避けられる場所
- 人目につきにくい暗がり
- 天敵から身を守れる密集した植物
- 水分補給ができる水場の近く
また、小さな池や水飲み場があると、さらに魅力的な環境になってしまいます。
「でも、庭を殺風景にするわけにはいかないし…」
そう悩む方も多いでしょう。
大切なのは、アライグマに利用されやすい場所を把握し、適切な対策を取ることです。
例えば、茂みを定期的に刈り込んだり、水場の周りに動きセンサー付きのライトを設置したりするのが効果的です。
アライグマにとって居心地の悪い環境を作ることで、彼らの侵入を防ぐことができるんです。
ガサガサ、ザワザワと、落ち着かない雰囲気を演出するのがポイントです。
夜行性のため「深夜から早朝」が活動のピーク
アライグマが庭に現れやすいのは、深夜から早朝にかけてです。
彼らは夜行性の動物なので、暗くなってから活発に動き回るんです。
「え?じゃあ寝ている間にやってくるの?」
そうなんです。
人間が活動を終えて静かになる時間帯こそ、アライグマにとってはゴールデンタイムなんです。
彼らの行動パターンを知ることで、効果的な対策を立てることができます。
アライグマの夜間の活動時間帯は、おおよそ以下のようになっています:
- 日没後30分〜1時間:活動開始
- 深夜0時〜午前3時:活動のピーク
- 午前4時〜日の出:活動終了、帰巣
この時間帯、アライグマたちは食べ物を探して庭中を探索します。
「ガサガサ」「ゴソゴソ」という音が聞こえたら、それはアライグマかもしれません。
夜行性であることを利用した対策も効果的です。
例えば、動きセンサー付きのライトを設置すると、突然の明かりでアライグマを驚かせることができます。
また、ラジオを低音量で夜中につけておくのも一案です。
人の気配を感じさせることで、アライグマを寄せ付けない効果があるんです。
「でも、毎晩起きていられないよ…」
そう思う方も多いでしょう。
大切なのは、アライグマの行動パターンを理解し、彼らが活動しやすい環境を作らないことなんです。
夜間に食べ物を外に放置しないことや、ゴミ箱の蓋をしっかり閉めることなど、簡単にできる対策から始めてみましょう。
庭のゴミ箱あさりは「絶好のエサ場」に
庭に置かれたゴミ箱は、アライグマにとって宝の山なんです。
彼らは鋭い嗅覚を持っており、ゴミの中の食べ残しや生ゴミの匂いを遠くからかぎつけることができます。
「えっ、うちのゴミ箱もねらわれるの?」
そうなんです。
特に、食べ物の残りや果物の皮が入ったゴミ箱は、アライグマにとって絶好のエサ場になってしまいます。
彼らは器用な手と強い顎を持っているので、簡単な蓋なら開けてしまうんです。
アライグマに狙われやすいゴミの種類は以下のとおりです:
- 食べ残しの入った容器
- 果物や野菜の皮
- 魚や肉の包み
- ペットフードの空き袋
- 甘い飲み物の空き容器
これらのゴミが庭に放置されていると、アライグマにとっては「いらっしゃいませ」と言っているようなものなんです。
「でも、ゴミ収集日まで庭に置くしかないんだけど…」
そう悩む方も多いでしょう。
大切なのは、アライグマが簡単にゴミにアクセスできないようにすることです。
例えば、次のような対策が効果的です:
- 頑丈な蓋付きのゴミ箱を使用する
- ゴミ箱にゴム紐やバンジーコードを取り付ける
- ゴミ箱を屋内や施錠できる場所に保管する
- 生ゴミは冷凍庫で保管し、収集日の朝に出す
これらの対策を組み合わせることで、アライグマのゴミあさりを効果的に防ぐことができます。
「ガシャン、ゴロゴロ」というゴミ箱の音が聞こえなくなれば、成功の証です。
アライグマに負けない、賢いゴミ管理を心がけることが大切なんです。
庭に来るアライグマを放置するのは「逆効果」!
「アライグマが来ても、そのうち勝手に去っていくだろう」
こんな考えは大きな間違いです。
アライグマを放置すると、状況はどんどん悪化していきます。
彼らは学習能力が高く、一度食べ物や隠れ家を見つけると、繰り返し訪れるようになるんです。
アライグマを放置した場合、次のような事態が起こる可能性があります:
- 被害が拡大し、庭全体が荒らされる
- 他のアライグマも集まってくる
- 繁殖を始め、個体数が増加する
- 家屋への侵入リスクが高まる
- 感染症のリスクが増大する
「えっ、そんなに深刻になるの?」
そうなんです。
アライグマは頭がよく、環境に適応する能力が高いので、放っておくと本当に厄介な問題になってしまいます。
例えば、庭に来るアライグマを1匹見かけただけでも、すぐに対策を始めることが大切です。
早めの対応が、将来的な大問題を防ぐ鍵となるんです。
効果的な初期対応として、次のような方法があります:
- 庭の整理整頓を行い、隠れ場所を減らす
- 食べ物の誘引源を取り除く
- 動きセンサー付きライトを設置する
- 忌避剤を使用する
- フェンスの補強を行う
これらの対策を組み合わせることで、アライグマに「ここは居心地が悪い」というメッセージを送ることができます。
「でも、かわいそうじゃない?」
そう思う方もいるかもしれません。
しかし、アライグマを放置することは、結果的に彼らにとっても良くないのです。
自然の生態系から離れ、人間の環境に依存するようになると、野生動物としての本来の姿を失ってしまうからです。
アライグマと人間が共存するためには、お互いの領域を尊重することが大切なんです。
早めの対策で、アライグマに「ここは君たちの場所じゃないよ」とやさしく、でもしっかりと伝えることが重要なんです。
- 日没後30分〜1時間:活動開始
- 深夜0時〜午前3時:活動のピーク
- 午前4時〜日の出:活動終了、帰巣
- 食べ残しの入った容器
- 果物や野菜の皮
- 魚や肉の包み
- ペットフードの空き袋
- 甘い飲み物の空き容器
- 頑丈な蓋付きのゴミ箱を使用する
- ゴミ箱にゴム紐やバンジーコードを取り付ける
- ゴミ箱を屋内や施錠できる場所に保管する
- 生ゴミは冷凍庫で保管し、収集日の朝に出す
- 被害が拡大し、庭全体が荒らされる
- 他のアライグマも集まってくる
- 繁殖を始め、個体数が増加する
- 家屋への侵入リスクが高まる
- 感染症のリスクが増大する
- 庭の整理整頓を行い、隠れ場所を減らす
- 食べ物の誘引源を取り除く
- 動きセンサー付きライトを設置する
- 忌避剤を使用する
- フェンスの補強を行う
庭での行動パターンと植物被害の深刻度
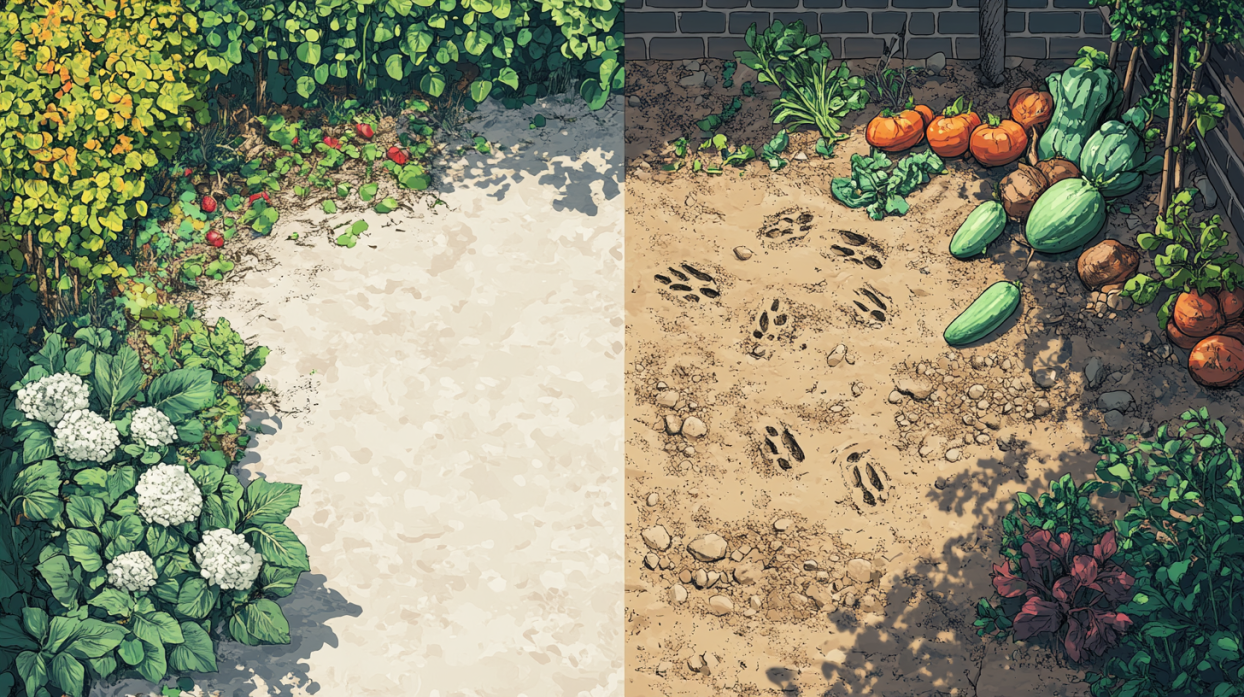
果樹園vs家庭菜園「どちらが狙われやすい?」
果樹園と家庭菜園、どちらもアライグマにとっては魅力的な食事処ですが、実は家庭菜園の方が狙われやすいんです。「えっ、なんで?」と思われるかもしれません。
その理由は、家庭菜園の方が多様な食べ物があり、人の目が届きにくいからなんです。
果樹園は確かに実がたくさんなりますが、種類が限られています。
一方、家庭菜園では様々な野菜や果物が育っていることが多いですよね。
アライグマにとっては、まるでビュッフェレストランのようなものなんです。
さらに、家庭菜園は夜間に人の目が届きにくいという特徴があります。
果樹園では夜間パトロールなどの対策がとられていることもありますが、家庭菜園ではそこまでの対策はしていないことが多いんです。
アライグマの被害に遭いやすい作物を順番に並べると、こんな感じになります:
- トウモロコシ
- トマト
- イチゴ
- メロン
- ブドウ
- カボチャ
そう思った方も多いのではないでしょうか。
これらの作物は栄養価が高く、アライグマにとっては格好のごちそうなんです。
家庭菜園を守るには、ネットや柵で囲むのが効果的です。
でも、アライグマは賢くて器用なので、簡単な対策では突破されてしまうかもしれません。
「よし、これで完璧!」と思っても油断は禁物。
定期的に対策を見直し、強化していく必要があるんです。
植物の食害と「土壌の掘り返し被害」に注意
アライグマによる庭の被害は、植物を食べられてしまう「食害」だけではありません。実は、土壌の掘り返し被害も深刻な問題なんです。
「えっ、土まで荒らされちゃうの?」
そうなんです。
アライグマは好奇心旺盛で、いたずら好きな性格。
庭の土をガリガリ掘り返して、虫や根っこを探すんです。
その結果、せっかく育てた植物の根が傷ついたり、露出したりしてしまいます。
アライグマによる土壌被害の特徴は以下の通りです:
- 浅い穴がたくさんできる
- 芝生がめくれ上がる
- 植物の根元が掘り起こされる
- 土の表面が荒れて固くなる
そう表現する人もいるくらい、アライグマの掘り返し被害は深刻なんです。
特に、新しく植えた苗や球根は要注意。
柔らかい土に興味を示すアライグマは、これらを掘り起こしてしまうことがあります。
対策としては、以下のようなものがあります:
- 土の表面に小石や粗い砂利を敷く
- 植物の周りにトゲのある枝を置く
- 地面に金網を敷いて植物を植える
- 忌避剤を土にまく
でも、完全に防ぐのは難しいんです。
「もう、諦めちゃおうかな…」なんて思わないでください。
根気強く対策を続けることが大切です。
アライグマとの知恵比べ、負けてられませんよ。
庭を守るためには、私たちの方が一枚上手でなければいけないんです。
フンの放置による「衛生被害」も深刻に
アライグマの被害と聞くと、まず植物の食害を思い浮かべる方が多いでしょう。でも、実はフンの放置による衛生被害も見逃せない問題なんです。
「えっ、フン?それって大したことないんじゃ…」
いえいえ、そんなことありません。
アライグマのフンは、見た目以上に厄介な問題を引き起こすんです。
アライグマのフンが引き起こす問題には、以下のようなものがあります:
- 寄生虫の卵が含まれている可能性がある
- 細菌やウイルスが繁殖しやすい
- 悪臭の原因になる
- 庭の美観を損ねる
- 土壌を汚染する
この寄生虫の卵は、人間が誤って摂取してしまうと深刻な健康被害を引き起こす可能性があるんです。
「うわっ、怖い!どうすればいいの?」
まずは、アライグマのフンを見つけたらすぐに適切に処理することが大切です。
以下のような手順で対応しましょう:
- 使い捨ての手袋を着用する
- ビニール袋でフンを包み込む
- 二重にビニール袋に入れて密閉する
- できるだけ早くゴミとして処分する
- フンがあった場所を消毒する
そうですね。
毎日の点検は確かに面倒かもしれません。
でも、家族の健康を守るためには必要な作業なんです。
朝のコーヒーを飲みながら庭を見回る習慣をつけるのも良いかもしれません。
また、フンの放置を防ぐためには、そもそもアライグマを寄せ付けないことが重要です。
餌となる食べ物を放置しない、隠れ場所を作らないなど、総合的な対策が必要になってきます。
アライグマのフン問題、見過ごしてはいけません。
「臭いものに蓋」どころか、しっかり対処することが大切なんです。
季節による「被害の変化」を把握しよう
アライグマの被害、実は季節によって大きく変わるんです。この変化を知っておくと、効果的な対策が立てられますよ。
「えっ、季節で変わるの?」
そうなんです。
アライグマの行動パターンは、季節や気候に大きく影響されるんです。
まずは、季節ごとの特徴を見てみましょう:
- 春:活動が活発化し、繁殖期に入る
- 夏:食料が豊富で、被害が最も多くなる
- 秋:冬に備えて食べ物を貪欲に求める
- 冬:活動が鈍るが、完全に冬眠はしない
この時期は庭の植物が成長し、実をつける時期と重なるため、アライグマの被害が急増します。
「じゃあ、冬は安心できるの?」
いえいえ、油断は禁物です。
確かに冬は活動が鈍りますが、完全に冬眠するわけではありません。
暖かい日には活動することもあるんです。
季節ごとの対策のポイントをまとめると、こんな感じになります:
- 春:巣作りの場所を作らないよう、庭の整理整頓を
- 夏:果物や野菜の収穫を遅らせない
- 秋:落ち葉や枯れ枝を放置しない
- 冬:暖かい隠れ場所を作らないよう注意
そうです。
季節の変化を意識して対策を立てることで、より効果的にアライグマの被害を防ぐことができるんです。
例えば、夏に向けて果樹にネットを張ったり、秋には落ち葉をこまめに片付けたりするのがおすすめです。
冬は、物置や軒下などアライグマが暖を取りそうな場所をしっかりチェックしましょう。
季節の変化を味方につけて、アライグマ対策を効果的に行いましょう。
「備えあれば憂いなし」とはよく言ったものです。
季節を先読みした対策で、被害を最小限に抑えられますよ。
放置された庭vs手入れされた庭「被害の差」
庭の手入れ、実はアライグマ対策の重要なポイントなんです。放置された庭と手入れされた庭では、アライグマの被害に大きな差が出てしまいます。
「えっ、そんなに違うの?」
はい、驚くほど違うんです。
放置された庭は、アライグマにとって天国のような環境になってしまうんです。
一方、手入れの行き届いた庭は、アライグマを寄せ付けにくい環境になります。
それぞれの庭の特徴を比べてみましょう:
- 放置された庭:
- 茂みや雑草が生い茂っている
- 落ち葉や枯れ枝が放置されている
- 果物や野菜が収穫されずに放置されている
- ゴミや食べ残しが散らかっている
- 手入れされた庭:
- 植物が適切に剪定されている
- 落ち葉や枯れ枝が定期的に片付けられている
- 収穫適期の作物がこまめに収穫されている
- ゴミや食べ残しが適切に処理されている
そう気づいた方、安心してください。
今からでも遅くありません。
以下のような手入れを心がけることで、アライグマを寄せ付けにくい環境を作ることができます:
- 定期的な草刈りと剪定を行う
- 落ち葉や枯れ枝をこまめに片付ける
- 果物や野菜は適期に収穫する
- ゴミや食べ残しを放置しない
- 水たまりを作らない
確かに、毎日の手入れは大変かもしれません。
でも、週末にまとめて行うだけでも大きな違いが出ますよ。
家族や近所の人と協力して、庭の手入れを楽しみながら行うのもいいかもしれません。
手入れの行き届いた庭は、アライグマを寄せ付けないだけでなく、私たち人間にとっても気持ちの良い空間になります。
「一石二鳥」とはこのことですね。
きれいに手入れされた庭で、アライグマとの知恵比べに勝利しましょう。
そして、美しい庭を心から楽しめる日々を過ごしていきましょう。
庭からアライグマを追い払う5つの裏技

ペットボトルの水で「光の反射」を利用!
アライグマを追い払う裏技の1つ目は、なんとペットボトルの水を使う方法です。これ、意外と効果があるんですよ。
「えっ、ただのペットボトル?本当に効くの?」
そう思われるかもしれませんね。
でも、実はこれ、アライグマにとっては予想外の光の動きを作り出す優れものなんです。
やり方はとっても簡単です。
以下の手順で試してみてください:
- 透明なペットボトルを用意する
- 中に水を半分くらいまで入れる
- 庭の数か所に置く
太陽の光や月の光が水面で反射して、きらきらと揺れる光を作り出します。
この予期せぬ光の動きが、アライグマを不安にさせるんです。
「でも、夜は暗いから効果ないんじゃ…」
そう心配する必要はありません。
月明かりでも十分効果がありますし、街灯の光でも反射するんです。
それに、アライグマは夜行性ですが、目はとても光に敏感。
わずかな光の変化も見逃しません。
この方法の良いところは、安全で環境にやさしいこと。
ペットボトルと水さえあればできるので、コストもかかりません。
しかも、見た目もそれほど悪くならないので、庭の美観を損ねる心配もありません。
ただし、注意点もあります。
強風の日はペットボトルが倒れてしまう可能性があるので、重しを置くなどの工夫が必要です。
また、長期間放置すると水が濁ってしまうので、定期的に水を取り替えましょう。
「よーし、早速試してみよう!」
そうですね。
この意外な裏技で、アライグマとの知恵比べに勝ちましょう。
きらきら光るペットボトルで、アライグマに「ここは居心地が悪いぞ」とメッセージを送るんです。
古いCDを吊るして「動く反射光」で撃退
2つ目の裏技は、古いCDを活用する方法です。これ、実はアライグマ撃退にすごく効果的なんですよ。
「えっ、CDって昔の音楽ディスクのこと?それがどう役立つの?」
そうなんです。
CDの表面は光を強く反射する性質があります。
この特性を利用して、アライグマを驚かせるんです。
具体的なやり方は以下の通りです:
- 使わなくなった古いCDを集める
- CDに穴を開けて、紐を通す
- 庭の木の枝や軒先にCDを吊るす
- 複数のCDを異なる高さに配置する
この予想外の動く光が、アライグマをびっくりさせるんです。
「でも、夜は暗いから効果ないんじゃない?」
そう思われるかもしれませんが、心配ありません。
月明かりや街灯の光でも十分に反射するんです。
それに、アライグマは夜行性ですが、意外と光に敏感。
わずかな光の変化も見逃しません。
この方法の良いところは、コストがほとんどかからないことです。
家にある古いCDを再利用できますし、環境にも優しい。
しかも、風に揺れるCDは風鈴のような効果もあって、見た目も楽しいんです。
ただし、注意点もあります。
強風の日はCDが飛ばされる可能性があるので、しっかりと固定することが大切です。
また、長期間使用すると紐が劣化する場合があるので、定期的に点検しましょう。
「なるほど、CDが守ってくれるんだね!」
そうなんです。
捨てようと思っていた古いCDが、実は庭の守り神になってくれるんです。
キラキラ光るCDで、アライグマに「ここは危険だぞ」とメッセージを送りましょう。
意外な物の再利用で、アライグマ対策と環境保護の一石二鳥、というわけです。
アルミホイルで「不快な触感」を演出
3つ目の裏技は、身近にあるアルミホイルを使う方法です。これ、意外とアライグマ撃退に効果てき面なんですよ。
「えっ、料理に使うアルミホイル?それがどう役立つの?」
そう思われるかもしれませんね。
実は、アライグマは足裏が敏感で、アルミホイルの触感がとても苦手なんです。
この特性を利用して、アライグマの侵入を防ぐんです。
具体的なやり方は以下の通りです:
- アルミホイルを適当な大きさに切る
- 庭の入り口や植木鉢の周りに敷く
- 野菜や果物の周りを囲むように配置する
- 必要に応じて石などの重しを置く
これが嫌で、アライグマは近づかなくなるんです。
「でも、風で飛んじゃわないかな?」
そうですね、その心配もあります。
だからこそ、重しを置いたり、部分的に地面に押し付けたりする工夫が必要です。
それに、定期的にチェックして、破れたり飛ばされたりしたアルミホイルは交換しましょう。
この方法の良いところは、手軽で安全なことです。
アルミホイルは台所にあるものですし、使用後はリサイクルも可能。
環境にも優しい方法なんです。
ただし、注意点もあります。
長期間使用すると見た目が悪くなる可能性があるので、庭の美観を気にする方は使用場所を限定するといいでしょう。
また、雨や露で濡れると効果が落ちる可能性があるので、天気の良い日に使用するのがおすすめです。
「へー、アルミホイルってすごいんだね!」
そうなんです。
料理の味方だと思っていたアルミホイルが、実は庭の守り神にもなってくれるんです。
ガサガサ、ビリビリとした触感で、アライグマに「ここは歩きにくいぞ」とメッセージを送りましょう。
身近な物の意外な使い方で、アライグマ対策ができるんです。
砂場用の砂で「歩きにくい地面」を作る
4つ目の裏技は、なんと砂場用の砂を使う方法です。これ、アライグマ撃退に思わぬ効果があるんですよ。
「えっ、子供の遊び場の砂?それがどう役立つの?」
そう思われるかもしれませんね。
実は、アライグマは砂の上を歩くのがとても苦手なんです。
この特性を利用して、アライグマの侵入を防ぐんです。
具体的なやり方は以下の通りです:
- 砂場用の細かい砂を用意する
- 庭の入り口や畑の周りに砂を撒く
- 幅30センチくらいの帯状に砂を敷く
- 砂の深さは5センチくらいにする
これが不安定で嫌なので、アライグマは近づかなくなるんです。
「でも、雨が降ったら流れちゃわないかな?」
その心配もありますね。
だからこそ、砂の周りに小さな縁を作ったり、定期的にメンテナンスしたりする工夫が必要です。
雨上がりには砂をかき混ぜて、表面を平らにしましょう。
この方法の良いところは、自然な見た目で庭の美観を損ねないことです。
しかも、砂は安価で手に入りやすく、環境にも優しい。
子供がいる家庭なら、遊び場としても活用できますね。
ただし、注意点もあります。
猫のトイレとして使われる可能性があるので、その対策も必要です。
また、砂埃が立つ可能性があるので、近隣への配慮も忘れずに。
「へー、砂がアライグマを追い払うなんて面白いね!」
そうなんです。
子供の遊び場だと思っていた砂が、実は庭の守り番にもなってくれるんです。
ズボズボと沈む不安定な地面で、アライグマに「ここは歩きにくいぞ」とメッセージを送りましょう。
身近な物の意外な使い方で、アライグマ対策ができるんです。
砂場遊びと同時に庭の防衛もできる、一石二鳥の方法といえますね。
風鈴の音で「不意の驚き」を与える
5つ目の裏技は、夏の風物詩である風鈴を使う方法です。これ、アライグマ撃退に意外な効果があるんですよ。
「えっ、風鈴?あの涼しげな音のする飾り?」
そうなんです。
実は、アライグマは突然の音に敏感なんです。
この特性を利用して、アライグマを驚かせて追い払うんです。
具体的なやり方は以下の通りです:
- 金属製の風鈴を数個用意する
- 庭の入り口や野菜畑の周りに吊るす
- 風の通り道を考えて配置する
- 高さを変えて複数設置する
この突然の音に、アライグマはびっくりして近づかなくなるんです。
「でも、無風の日は効果がないんじゃない?」
その心配もありますね。
だからこそ、風の通り道をよく観察して設置場所を決めることが大切です。
それに、複数の風鈴を使うことで、少しの風でも音が鳴るようにしましょう。
この方法の良いところは、見た目も楽しいことです。
風鈴の音は人間にとっても癒やしになりますし、夏らしい雰囲気も演出できます。
しかも、電気を使わないのでエコですし、維持費もかかりません。
ただし、注意点もあります。
近隣への騒音配慮が必要ですので、深夜は取り外すなどの対策をしましょう。
また、強風の日は風鈴が飛ばされる可能性があるので、しっかりと固定することが大切です。
「なるほど、風鈴が守ってくれるんだね!」
そうなんです。
涼しげな音色を楽しむものだと思っていた風鈴が、実は庭の警備員にもなってくれるんです。
チリンチリンという音で、アライグマに「ここは危険だぞ」とメッセージを送りましょう。
夏の風物詩を楽しみながら、同時にアライグマ対策もできる。
一石二鳥どころか、涼しさも加えれば三石三鳥の方法かもしれませんね。
風鈴の音色に耳を傾けながら、安心して庭を楽しめる日々が来ることでしょう。