アライグマのぶどう被害対策は?【ネット設置が最も効果的】収穫量を守る3つの防御方法と設置のコツ

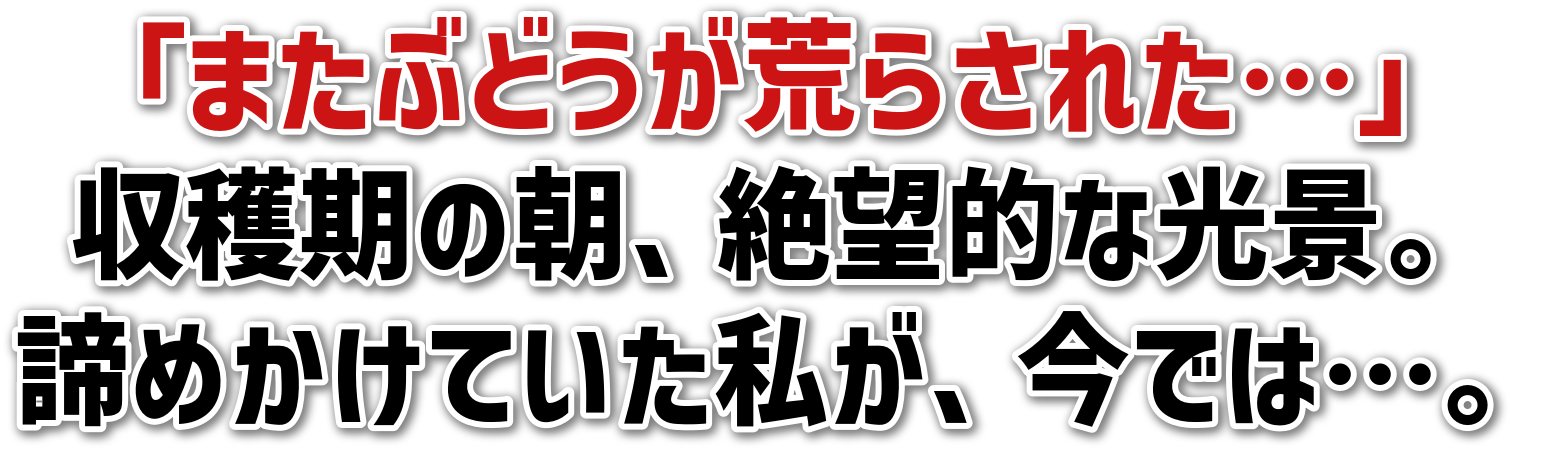
【この記事に書かれてあること】
アライグマのぶどう被害に悩んでいませんか?- アライグマはぶどうの甘さに惹かれ、8月〜9月に被害が集中
- 一晩で数十株もの被害が発生する可能性あり
- 最も効果的な対策は目合い5cm以下のネット設置
- 電気柵や忌避剤など、複合的な対策が有効
- ペットボトル風鈴や唐辛子パウダーなど、意外な裏技も紹介
せっかく丹精込めて育てたぶどうが、一晩で台無しになってしまう…そんな悲しい経験をした方も多いはず。
でも、もう心配は無用です!
この記事では、アライグマによるぶどう被害の実態と、効果的な対策方法をご紹介します。
ネット設置や電気柵の活用法はもちろん、意外な裏技まで。
今年こそは豊かな収穫を目指しましょう。
ぶどう農家さんも、家庭菜園愛好家の方も、必見の情報満載です!
【もくじ】
アライグマによるぶどう被害の実態と対策

アライグマがぶどうを好む理由と被害の特徴
アライグマがぶどうを好むのは、その甘さと栄養価の高さが魅力的だからです。「ん〜、このぶどうの甘い香り、たまらないニャー」とアライグマは考えているかもしれません。
実は、アライグマにとってぶどうは最高のごちそうなんです。
なぜでしょうか?
それは、ぶどうが次のような特徴を持っているからです。
- 甘くて美味しい
- 栄養価が高い
- 手軽に食べられる
- たくさんの実がまとまっている
ぶどうは一度に大量に食べられるので、アライグマにとっては「一石二鳥」の食べ物なんです。
では、アライグマによるぶどう被害にはどんな特徴があるのでしょうか?
主に次の3つが挙げられます。
- 果実を食べ荒らす
- 茎を折ってしまう
- 踏み荒らして畑を荒廃させる
「昼間は何も問題なかったのに、朝起きたら畑が荒れ果てていた!」なんてことも珍しくありません。
アライグマの被害は、まるで泥棒のようにこっそりと進行するのです。
ぶどう畑への侵入時期と被害が集中する8月〜9月
アライグマによるぶどう被害は、8月から9月に集中します。この時期はぶどうが最も美味しくなる時期なんです。
「えっ、アライグマってぶどうが熟すタイミングを知ってるの?」と思うかもしれません。
実は、アライグマは非常に賢い動物で、食べ物が最も美味しくなる時期を本能的に理解しているんです。
ぶどうの成長サイクルを見てみましょう。
- 春:芽吹きと成長開始
- 初夏:花が咲き、実がなり始める
- 真夏:実が大きくなり、糖度が上昇
- 8月〜9月:収穫期を迎え、最も甘くなる
「ちょうど良い具合に熟したぶどうを、いただきま〜す!」とばかりに、畑に侵入してきます。
この時期は農家さんにとっても大切な時期。
収穫の準備に忙しく、油断するとアライグマに先を越されてしまうかもしれません。
「せっかく手塩にかけて育てたぶどうが…」と嘆く前に、しっかりと対策を立てる必要があるんです。
気をつけたいのは、一度アライグマが美味しいぶどうの味を覚えてしまうと、翌年も必ずやってくるということ。
油断は禁物です。
「去年は大丈夫だったから…」なんて思っていると、思わぬ被害に遭うかもしれません。
ぶどうの木や果実への具体的な被害内容
アライグマによるぶどうへの被害は、見た目以上に深刻です。具体的にどんな被害が起こるのか、詳しく見ていきましょう。
まず、最も目立つのが果実への被害です。
アライグマは、ぶどうの実を次々と食べていきます。
「パクパクむしゃむしゃ」と音が聞こえてきそうなほど、貪欲に食べるんです。
しかも、一房全部を食べ尽くすわけではありません。
半分食べたら次の房に移る、なんてこともあるんです。
- 果実を食い荒らす
- 半端に食べられた房が多数残る
- 熟した実だけでなく、青い実まで食べてしまう
アライグマは体重が5〜10kg程度あり、木に登って実を取ろうとします。
その結果、次のような被害が発生します。
- 枝が折れる
- 葉が傷つく
- 樹皮が剥がれる
残念ながら、その通りなんです。
特に若い木は被害を受けやすく、最悪の場合は枯れてしまうこともあります。
さらに、アライグマは地面を歩き回るため、株元も踏み荒らされてしまいます。
これにより、根が傷つき、木の成長に悪影響を及ぼす可能性があるんです。
このように、アライグマの被害は果実だけにとどまらず、木全体に及ぶんです。
一度被害を受けると、翌年以降の収穫にも影響が出てしまうため、早めの対策が不可欠です。
「来年こそは美味しいぶどうを収穫するぞ!」という希望を持って、しっかりと対策を立てましょう。
小規模農家でも深刻!一晩で数十株の被害も
アライグマによるぶどう被害は、小規模農家でも深刻な問題になっています。なんと、一晩で数十株もの被害が出ることもあるんです。
「えっ!そんなに一気に食べられちゃうの?」と驚く声が聞こえてきそうですね。
実は、アライグマは非常に食欲旺盛で、一晩で体重の5〜10%もの食べ物を消費するんです。
つまり、5kgのアライグマなら、250〜500gものぶどうを平らげてしまうわけです。
小規模農家の被害例を見てみましょう。
- 50株のぶどう畑で、一晩に30株が被害を受けた
- 家庭菜園の10株全てが食い荒らされた
- 収穫直前の高級品種が狙われ、80%が食べられた
「一年かけて丹精込めて育てたのに…」と嘆く声が聞こえてきそうです。
特に注意が必要なのは、アライグマは群れで行動することもあるという点です。
2〜3匹で侵入されると、被害はさらに大きくなってしまいます。
まるで「ぶどう食べ放題パーティー」でも開かれたかのように、畑が荒らされてしまうんです。
小規模農家の方々にとって、この被害は死活問題になることもあります。
例えば、高級ぶどう品種を栽培している場合、一房数千円もする商品が台無しになってしまうかもしれません。
「今年の収入が…」と頭を抱えてしまうほどの被害になりかねないんです。
だからこそ、小規模農家でも油断は禁物。
「うちは小さい畑だから大丈夫」なんて思っていると、思わぬ被害に遭うかもしれません。
むしろ、小さい畑だからこそ、一晩で全滅する可能性もあるんです。
早めの対策で、大切なぶどうを守りましょう。
ぶどう被害放置はNG!収穫量激減のリスクあり
アライグマによるぶどう被害を放置するのは、絶対にNGです。なぜなら、収穫量が激減してしまうリスクがあるからです。
「まあ、少しぐらいなら…」なんて思っていると、取り返しのつかないことになりかねません。
アライグマの被害は、雪だるま式に大きくなっていくんです。
被害を放置した場合、どんなことが起こるでしょうか?
- 収穫量が激減する
- ぶどうの品質が低下する
- 木自体にダメージを与え、翌年以降の収穫にも影響が出る
- アライグマが居着いてしまい、被害が継続的に発生する
「えっ、そんなに!?」と驚くかもしれません。
でも、これは決して大げさな話ではありません。
アライグマは非常に賢い動物で、一度美味しい食べ物の在処を覚えると、繰り返し訪れるようになります。
つまり、最初の被害を見逃すと、その後どんどん被害が拡大していくんです。
さらに、経済的損失だけでなく、精神的なダメージも大きいんです。
「長年の栽培努力が水の泡…」なんて悲しい結果になりかねません。
また、リピート被害により、翌年以降の収穫にも深刻な影響が出る可能性があります。
木が傷つけられることで、来年の芽吹きが悪くなったり、果実の品質が落ちたりするかもしれません。
だからこそ、早めの対策が重要なんです。
「まだ大丈夫かな」なんて油断している間に、アライグマはどんどんぶどうを食べ進めていきます。
被害を発見したら、すぐに対策を講じましょう。
そうすることで、大切なぶどうを守り、豊かな収穫を得ることができるんです。
アライグマのぶどう被害対策:効果的な方法

ネット設置が最強の対策!正しい設置方法とは
アライグマのぶどう被害対策として、ネット設置が最も効果的です。でも、ただネットを張ればいいというわけではありません。
正しい設置方法を知らないと、せっかくの対策も水の泡になっちゃうんです。
まず、ネットの選び方が重要です。
「えっ、ネットにも種類があるの?」と思われるかもしれませんね。
実は、アライグマ対策には目合い5cm以下の丈夫なネットを選ぶのがポイントなんです。
なぜかというと、アライグマは小さな隙間でも器用に侵入してしまうからです。
次に、設置の仕方です。
ネットは地面から1.5m以上の高さまで張る必要があります。
「へぇ、アライグマってそんなに高く登れるの?」と驚かれるかもしれませんが、実はアライグマは思った以上に運動能力が高いんです。
さらに重要なのが、地面との隙間をなくすことです。
ここがポイントで、多くの人がうっかり見落としがちなんです。
「ちょっとぐらいの隙間なら大丈夫でしょ」なんて思っていると、アライグマにすきを与えてしまいます。
地面との隙間はぴったりと閉じるようにしましょう。
ネットの固定方法も大切です。
風で飛ばされたり、アライグマの力で外れたりしないよう、しっかりと固定することが必要です。
杭や支柱を使って、がっちりと固定しましょう。
- 目合い5cm以下の丈夫なネットを選ぶ
- 地面から1.5m以上の高さまで張る
- 地面との隙間をぴったりと閉じる
- 杭や支柱でしっかり固定する
「よーし、これでぶどうを守れるぞ!」という気持ちで、しっかりとネットを設置してくださいね。
電気柵vsネット!どちらがより効果的?
アライグマ対策として、電気柵とネット、どちらがより効果的なのでしょうか?結論から言うと、両方とも効果的ですが、状況によって使い分けるのがベストです。
まず、電気柵の特徴を見てみましょう。
電気柵は強力な抑止力があります。
アライグマが触れると軽い電気ショックを受けるので、一度経験すると二度と近づかなくなる可能性が高いんです。
「えっ、動物虐待じゃないの?」なんて心配する方もいるかもしれませんが、大丈夫です。
人畜無害な程度の電流なので、アライグマにダメージを与えることはありません。
電気柵の設置方法は、地上20cmと50cmの2段設置がおすすめです。
なぜ2段なのかというと、アライグマの体の大きさに合わせているんです。
これで、小さなアライグマも大きなアライグマも、しっかりガードできるというわけ。
一方、ネットの特徴は何といっても物理的な障壁となることです。
正しく設置すれば、アライグマが中に入ることはほぼ不可能です。
また、一度設置すれば長期間使えるのも魅力的ですね。
では、どちらを選べばいいの?
というところですが、以下のポイントを参考にしてみてください。
- 広い面積を守りたい → 電気柵
- 完全に侵入を防ぎたい → ネット
- コストを抑えたい → ネット
- メンテナンスを簡単にしたい → 電気柵
「ガッチリガード作戦」というわけですね。
電気柵で初期の抑止力を発揮し、それでも侵入しようとするアライグマをネットで完全ブロック。
これなら、もう百戦錬磨のアライグマでも太刀打ちできません。
結局のところ、自分の農地の状況や予算に合わせて選ぶのが一番です。
どちらを選んでも、正しく設置すれば高い効果が期待できますよ。
「さあ、どっちにしようかな」と悩むのも楽しいかもしれませんね。
忌避剤の種類と正しい使用法:効果は2週間
アライグマ対策の強い味方、忌避剤。でも、ただ撒けばいいというものではありません。
種類や使い方を知らないと、効果半減どころか無駄になっちゃうかも。
そこで、忌避剤の種類と正しい使用法をご紹介します。
まず、忌避剤の種類ですが、大きく分けて化学系と天然系があります。
化学系は効果が強力ですが、天然系のほうが安全性が高いんです。
「う〜ん、どっちがいいんだろう?」なんて迷っちゃいますよね。
実は、最近は天然系の人気が高まっているんです。
人気の天然系忌避剤には、以下のようなものがあります。
- 唐辛子スプレー
- にんにくオイル
- ハッカ油
- 木酢液
「へぇ、身近なもので対策できるんだ!」と驚く方も多いのではないでしょうか。
さて、忌避剤の使い方ですが、ポイントは定期的な散布です。
忌避剤の効果は一般的に2週間程度。
「えっ、たった2週間!?」と思われるかもしれませんが、これが自然の摂理なんです。
雨で流されたり、日光で分解されたりするので、効果が長続きしないんですね。
そこで、以下のような使用方法がおすすめです。
- ぶどう園の周囲に忌避剤を散布する
- 特にアライグマの侵入経路と思われる場所に重点的に散布
- 2週間ごとに再散布する
- 雨の後は必ず散布し直す
でも、大切なぶどうを守るためだと思えば、それほど大変ではありませんよ。
むしろ、定期的に畑を見回るいい機会になるんです。
忌避剤を使う際の注意点として、食べ頃の果実に直接かけないことです。
せっかくのおいしいぶどうが台無しになっちゃいますからね。
「あっ、うっかり忌避剤つけちゃった!」なんてことにならないよう、気をつけましょう。
忌避剤は、ネットや電気柵と組み合わせて使うとさらに効果的です。
「よーし、これでアライグマ対策はバッチリ!」という自信が持てるはずです。
大切なぶどうを守るため、忌避剤を上手に活用してくださいね。
防御策の設置時期:収穫1〜2か月前がベスト
アライグマ対策、いつから始めればいいの?この質問、実はとっても大切なんです。
タイミングを間違えると、せっかくの対策も空振りになっちゃうかも。
結論から言うと、収穫の1〜2か月前に防御策を設置するのがベストです。
なぜ1〜2か月前なのか、ちょっと考えてみましょう。
アライグマは、ぶどうが甘くなり始める頃から活動を開始します。
つまり、完熟する前からねらっているんです。
「えっ、そんなに早くから?」と驚く方も多いかもしれません。
でも、アライグマの嗅覚は鋭敏で、ぶどうの香りを遠くからかぎつけるんです。
防御策の設置時期を決める際は、以下のポイントを押さえておくといいでしょう。
- ぶどうの品種による成熟時期の違い
- その年の気候条件
- 過去のアライグマ被害の発生時期
「うちの畑は複数の品種があるなぁ」という場合は、最も早く熟す品種に合わせて対策を始めましょう。
もちろん、気候条件によっても変わってきます。
暑い年は成熟が早まるので、対策も早めに始める必要があります。
「今年は猛暑だなぁ」と感じたら、通常より1週間ほど早めるのがいいかもしれません。
過去の被害経験も重要です。
「去年はこの時期にやられたなぁ」という記憶があれば、その1〜2週間前から対策を始めるのがおすすめです。
アライグマは学習能力が高いので、一度おいしい思いをすると、翌年も同じ時期にやってくる可能性が高いんです。
ここで注意したいのが、対策の準備は事前に済ませておくことです。
ネットや電気柵の購入、忌避剤の準備など、必要なものは前もって揃えておきましょう。
「いざというときに慌てない」これ、大切なポイントです。
「え?もっと早くから対策を始めたほうがいいんじゃない?」と思う方もいるかもしれません。
でも、あまり早すぎると、維持管理の手間が増えたり、ぶどうの生育に影響を与えたりする可能性があるんです。
適切なタイミングで始めるのがコツです。
防御策の設置、タイミングが肝心です。
カレンダーに印をつけて、しっかり準備しておきましょう。
「よし、今年こそアライグマに負けないぞ!」という気持ちで、適切なタイミングで対策を始めてくださいね。
ぶどう畑の見回りは夜間こそ重要!ただし要注意
ぶどう畑の見回り、昼間だけじゃダメなんです。実は、夜間の見回りこそ重要なんです。
でも、ちょっと待って!
夜間の見回りには注意点もあるんです。
まず、なぜ夜間の見回りが重要なのか、考えてみましょう。
アライグマは夜行性の動物です。
つまり、暗くなってから活動を始めるんです。
「あ〜、だからか!」と納得される方も多いのではないでしょうか。
昼間は静かな畑も、夜になると思わぬ来訪者でにぎわっているかもしれません。
夜間の見回りのポイントは以下の通りです。
- 懐中電灯を持参する
- 静かに歩く
- 足元に注意する
- 異常な音や匂いに気をつける
- アライグマの目の反射を探す
懐中電灯の光に反射して、キラッと光るんです。
「わっ、目が光った!」なんて経験をすると、ちょっとドキドキしちゃいますよね。
でも、ここで重要な注意点があります。
夜間の見回りは危険を伴う可能性があるんです。
アライグマに遭遇した時の対処法をしっかり知っておく必要があります。
- 突然の動きをしない
- 大きな音を立てない
- ゆっくりと後退する
- 決して追いかけない
でも、アライグマは野生動物です。
追い詰められると危険な行動に出る可能性があるんです。
夜間の見回りを行う際は、できれば2人以上で行動するのがおすすめです。
「2人なら心強いよね」という声が聞こえてきそうです。
1人だと不安な場面でも、仲間がいれば落ち着いて対処できるんです。
また、夜間の見回りの頻度も大切です。
毎晩行う必要はありませんが、定期的に行うことで、アライグマの行動パターンを把握できるかもしれません。
「月に2〜3回くらいかな」というペースで始めてみるのがいいでしょう。
ただし、夜間の見回りに頼りすぎるのも考えものです。
見回りはあくまでも補助的な対策。
ネットや電気柵などの物理的な防御策が基本であることを忘れないでくださいね。
「よし、今晩から見回りを始めてみよう!」そんな意気込みも大切ですが、安全第一で行動してくださいね。
アライグマ対策と自分の安全、両方をしっかり守りましょう。
意外と簡単!アライグマのぶどう被害を防ぐ裏技

ペットボトルの風鈴効果!音と光でアライグマ撃退
ペットボトルを使った風鈴で、アライグマを簡単に撃退できちゃうんです。これ、意外と効果があるんですよ。
「えっ、ペットボトルだけでアライグマが寄って来なくなるの?」って思いますよね。
実は、アライグマは意外と臆病な動物なんです。
突然の音や光に驚いて、逃げ出しちゃうんです。
ペットボトル風鈴の作り方は、とっても簡単です。
- 空のペットボトルを用意する
- 底の部分を切り取る
- 中に小さな鈴や貝殻を入れる
- 紐を通して吊るせるようにする
風が吹くたびに「カラカラカラ〜」って音がして、ボトルがキラキラ光るんです。
これがアライグマにとっては「うわっ、なんか怖い!」って感じになるわけです。
特に夜は効果抜群です。
月明かりや街灯の光が反射して、ぶどう畑が不思議な雰囲気になります。
「なんだか怪しくて近寄りがたいぞ」って、アライグマも感じちゃうんです。
ただし、注意点もあります。
強風の日はガタガタうるさくなっちゃうかも。
ご近所迷惑にならないよう、設置場所には気をつけましょうね。
この方法、コストもほとんどかからないし、見た目も楽しいですよ。
「よーし、今日からペットボトル集めだ!」って感じで、ぜひ試してみてください。
アライグマ対策が、ちょっとした工作タイムになっちゃうかもしれませんね。
使用済みの猫砂で天敵の匂いを演出!効果絶大
使用済みの猫砂を利用して、アライグマを寄せ付けない方法があるんです。これ、意外と効果絶大なんですよ。
「えっ、猫のトイレの砂?それって臭くないの?」って思いますよね。
確かに人間には少し気になる臭いかもしれません。
でも、アライグマにとっては「ヒエッ、ここは危険だ!」って感じる匂いなんです。
なぜかというと、猫はアライグマの天敵の一つなんです。
野生のアライグマは、大きな猫に襲われる危険を本能的に感じているんです。
だから、猫の匂いがするところには近づきたくないんです。
使い方は簡単です。
- 使用済みの猫砂を小さな布袋に入れる
- その袋をぶどう畑の周りに置く
- 1週間ごとに新しいものと交換する
お近くの猫カフェや動物病院に相談してみてください。
きっと分けてもらえるはずです。
「アライグマ対策に使うんです!」って説明すれば、協力してくれる人も多いはずですよ。
この方法、匂いが強すぎて気になる場合は、畑の外側に置くのがおすすめです。
人間は気にならないけど、アライグマには十分効果がある距離っていうのがあるんです。
ただし、雨の日は効果が薄れちゃうので注意が必要です。
雨よけのカバーを付けるなど、ちょっとした工夫が大切です。
「よーし、今度から猫砂を無駄にしないぞ!」なんて、新しい発見があるかもしれませんね。
アライグマ対策が、思わぬところでエコ活動になっちゃうかも。
面白いでしょ?
ラジオの低音量夜間放送で人の気配を演出
夜間にラジオを低音量で流すだけで、アライグマを寄せ付けない効果があるんです。これ、意外と簡単で効果的な方法なんですよ。
「えっ、ラジオ?それだけでいいの?」って思いますよね。
実は、アライグマは人間の存在を非常に警戒するんです。
人の声や音楽が聞こえると、「あっ、ここは人がいるぞ。危険だ!」って感じちゃうんです。
具体的な方法は、こんな感じです。
- 小型のラジオを用意する
- ぶどう畑の中央あたりに設置する
- 夜8時頃から朝5時頃まで、低音量で放送する
- トークやニュース番組がおすすめ
人間の耳でぎりぎり聞こえるくらいで十分。
アライグマの耳はとても敏感なので、それでも十分警戒するんです。
「でも、電気代が心配...」って思う方もいるかもしれませんね。
そんな時は、乾電池式のラジオを使うのがおすすめです。
ソーラーパネル付きのものなら、さらに長持ちしますよ。
ただし、毎晩同じ場所で同じように流していると、アライグマが慣れてしまう可能性もあります。
そこで、ちょっとした工夫が必要です。
- 設置場所を時々変える
- 放送局を日によって変える
- たまに音量を少し大きくする日を作る
アライグマにとっては、とってもストレスフルな環境になるわけです。
「よーし、今夜からラジオナイトだ!」なんて、ちょっとわくわくしませんか?
アライグマ対策が、ちょっとしたラジオパーソナリティ気分を味わえる、そんな楽しい時間になるかもしれませんよ。
唐辛子パウダーの驚異の威力!畑周囲に撒くだけ
唐辛子パウダーを畑の周りに撒くだけで、アライグマを寄せ付けない強力な効果があるんです。これ、本当に簡単で驚くほど効果的なんですよ。
「えっ、唐辛子?辛いのが苦手なの?」って思いますよね。
実は、アライグマは唐辛子の刺激的な匂いが大の苦手なんです。
鼻が敏感なアライグマにとって、唐辛子の匂いは「むせかえるような」強烈な刺激なんです。
使い方は本当に簡単です。
- 市販の唐辛子パウダーを用意する
- ぶどう畑の周囲に細く線を引くように撒く
- 雨が降ったら再度撒き直す
大丈夫です。
畑の周囲だけに撒くので、ぶどうには影響ありません。
ただし、風の強い日は注意が必要です。
目に入ると痛いので、撒く時はマスクと手袋を着用しましょう。
「よいしょ、よいしょ」って感じで、慎重に撒いていきます。
効果を高めるためには、こんな工夫もおすすめです。
- 唐辛子パウダーを水で溶いて霧吹きで散布する
- にんにくパウダーを混ぜて効果アップ
- 畑の入り口付近は特に念入りに撒く
でも、それだけアライグマへの効果も絶大なんです。
「よーし、今日から唐辛子戦士だ!」なんて、ちょっと楽しくなってきませんか?
この方法、コストも安いし、環境にも優しいんです。
アライグマ対策が、ちょっとしたスパイシーな冒険になるかもしれませんよ。
辛さに負けずに、頑張っていきましょう!
レモングラスの植栽で自然な忌避効果を実現
レモングラスを植えるだけで、アライグマを自然に寄せ付けない効果があるんです。これ、見た目も美しくて一石二鳥の方法なんですよ。
「えっ、レモングラス?あの料理に使うハーブ?」って思いますよね。
そうなんです。
実はレモングラスの香りが、アライグマにとっては「うわっ、イヤな匂い!」なんです。
レモングラスの植え方は、こんな感じです。
- ぶどう畑の周りに溝を掘る
- レモングラスの苗を30cm間隔で植える
- 水をたっぷりあげる
- 定期的に刈り込んで香りを強く保つ
「わぁ、素敵!」って感じで、畑の景観も良くなっちゃいます。
でも、注意点もあります。
レモングラスは寒さに弱いので、寒冷地では冬場の対策が必要です。
「よしよし、毛布をかけてあげよう」なんて、ちょっと可愛がってあげてくださいね。
効果を高めるためには、こんな工夫もおすすめです。
- 刈り取った葉を畑の中にまく
- レモングラスティーを作って畑に撒く
- 他のハーブ(ミント、ローズマリーなど)も一緒に植える
アライグマには嫌な匂いでも、人間にとっては心地よい香りなんです。
この方法、一度植えてしまえば手間もかからないし、毎年効果が期待できます。
「よーし、今年からハーブ農園の始まりだ!」なんて、新しい趣味が見つかるかもしれませんよ。
アライグマ対策が、ちょっとしたガーデニングタイムになっちゃうかも。
楽しみながら、美しく効果的な対策を続けていきましょう!