アライグマの落花生被害への対策【地中の実も狙われる】畑を守る6つの方法と栽培場所の選び方

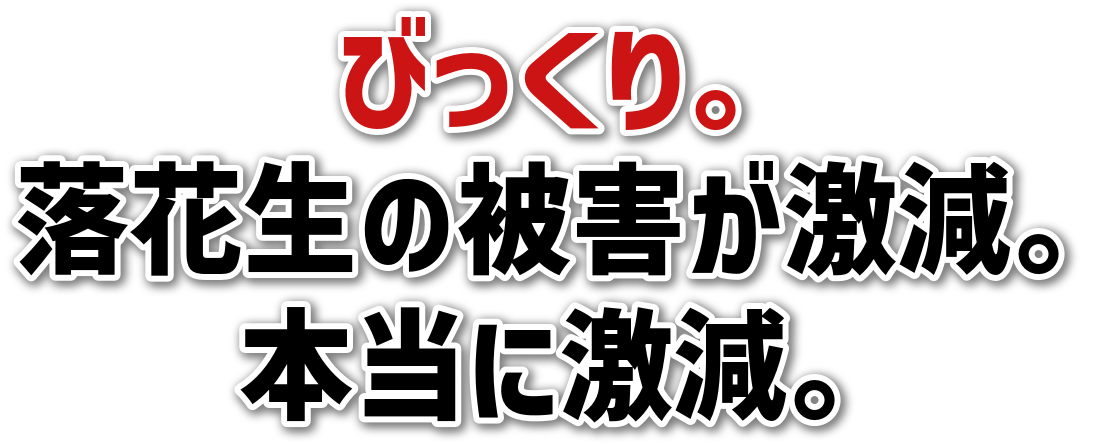
【この記事に書かれてあること】
あなたの大切な落花生畑が、アライグマに荒らされていませんか?- アライグマは落花生の高栄養価に惹かれる
- 被害は8月下旬から10月の収穫期に集中
- 電気柵や金網フェンスが効果的な対策
- 人家近くでの栽培や夜間照明の活用も有効
- ラベンダーの植栽や猫砂の活用など意外な対策も
実はアライグマ、落花生が大好物なんです。
しかも、地中の実まで狙うので被害が深刻。
でも、諦めないでください!
この記事では、アライグマの落花生被害の特徴を解説し、効果的な対策方法を紹介します。
電気柵や金網フェンスはもちろん、意外な裏技まで。
8月下旬から10月の被害集中期に備えて、今すぐ対策を始めましょう。
あなたの落花生、守りましょう!
【もくじ】
アライグマの落花生被害の特徴と深刻さ

アライグマが落花生を好む理由「高栄養価」に注目!
落花生は、アライグマにとって魅力的な高栄養価の食べ物なんです。「なんでアライグマは落花生にそんなに夢中なの?」って思いますよね。
実は、落花生には豊富なタンパク質と脂肪が含まれているんです。
アライグマは、生き残るために効率よくエネルギーを摂取する必要があります。
落花生は、まさにそのニーズにぴったり。
「これぞごちそう!」とアライグマは考えているのかもしれません。
落花生の栄養価を見てみましょう。
- 高タンパク質:体の維持と成長に重要
- 高脂肪:寒い季節を乗り越えるためのエネルギー源
- ビタミンとミネラル:健康維持に不可欠
「まるで自然のパワーフードだね!」と、アライグマは喜んでいるかもしれません。
さらに、落花生は地中にあるため、他の動物に見つかりにくいという利点もあります。
アライグマにとっては、「安全に食べられる高カロリー食」というわけです。
このように、落花生の高栄養価がアライグマを引き寄せる大きな要因になっているんです。
農家さんにとっては頭の痛い問題ですが、アライグマの立場から見れば「美味しくて栄養たっぷりの宝物」なんですね。
地中の実も狙われる!アライグマの落花生被害の特徴
アライグマによる落花生被害は、地上だけでなく地中の実まで狙われるのが大きな特徴です。「え?地中まで掘り起こすの?」と驚く方も多いでしょう。
その通り、アライグマは器用な手と鋭い嗅覚を使って、地中の落花生を見事に掘り出してしまうんです。
被害の様子を具体的に見てみましょう。
- 植物体が引き抜かれる:根こそぎ倒されることも
- 地面に穴が開く:まるでモグラの仕業のよう
- 実だけが消える:葉や茎は残されることも
アライグマの被害が深刻なのは、その徹底ぶり。
地中の実を掘り出す際、周囲の植物まで傷つけてしまいます。
「おいしい実を見つけたぞ!」とばかりに、アライグマは夢中になって掘り進めるんです。
さらに、アライグマは群れで行動することが多いため、一度の襲撃で広範囲に被害が及びます。
「今夜はごちそうだ!」と、仲間を呼んでくるかもしれません。
この特徴的な被害パターンを知ることで、アライグマによる被害かどうかを早期に判断できます。
「あれ?この穴ぼこ、もしかして…」と気づくことが、対策の第一歩になるんです。
落花生被害が集中する時期は「8月下旬?10月」
落花生の被害が最も深刻になるのは、8月下旬から10月にかけてなんです。「なぜこの時期なの?」って思いますよね。
実は、この時期こそが落花生の実りの季節なんです。
アライグマは賢い動物です。
落花生が最もおいしくなる時期を見計らって、集中的に襲撃をかけてくるんです。
まるで「収穫カレンダー」を持っているかのようですね。
この時期の特徴を見てみましょう。
- 8月下旬:落花生の実が膨らみ始める
- 9月:実の成長が最盛期
- 10月:収穫適期を迎える
アライグマは人間と同じタイミングを狙ってくるんです。
気温が下がり始めるこの時期、アライグマは冬に備えてエネルギーを蓄える必要があります。
「冬眠の前に栄養を摂らなきゃ」と必死なんですね。
高カロリーの落花生は、まさに理想的な食べ物というわけ。
また、この時期は子アライグマが親から独立する季節でもあります。
「自分で食べ物を見つけなきゃ」と、若いアライグマたちも必死で食べ物を探しているんです。
農家さんにとっては、まさに総力戦の時期。
「守るぞ、私たちの落花生!」と、この時期に向けて対策を強化することが大切です。
一晩で数百株も!アライグマの被害規模に驚愕
アライグマの落花生被害は、その規模の大きさに驚かされます。なんと、一晩で数百株もの被害が出ることがあるんです。
「えっ、そんなに!?」と驚く声が聞こえてきそうですね。
被害の規模を具体的に見てみましょう。
- 小規模農家:一晩で全滅することも
- 中規模農家:数日で収穫量が半減
- 大規模農家:端から順に被害が広がる
まるで台風が通り過ぎたような惨状になることも。
なぜこんなに大規模な被害になるのでしょうか。
実は、アライグマには「仲間を呼ぶ」習性があるんです。
「おいしいものを見つけたぞ!」と、仲間に知らせるんですね。
すると、あっという間に大勢のアライグマが集まってきて、まさに「落花生パーティー」状態に。
さらに、アライグマは夜行性。
人間が寝ている間に、こっそりと畑を荒らしていくんです。
「夜の間に何が起こったの?」と、朝になって愕然とすることも。
この大規模な被害は、農家さんにとって深刻な問題です。
「今年の収入はどうなるの?」と不安になるほど。
一晩の被害で、一年の努力が水の泡になってしまうこともあるんです。
だからこそ、事前の対策が重要。
「油断は禁物!」と、常に警戒を怠らないことが大切です。
アライグマの習性を知り、適切な対策を取ることで、この驚くべき被害から大切な落花生を守ることができるんです。
落花生の葉や茎まで食べる?アライグマの食性を解説
アライグマの食性は実に幅広く、落花生の場合は実だけでなく、葉や茎まで食べることがあるんです。「えっ、全部食べちゃうの?」と驚く方も多いでしょう。
そう、アライグマはまさに「食いしん坊」なんです。
アライグマの落花生の食べ方を見てみましょう。
- 実:最も好む部分で、真っ先に狙われる
- 葉:栄養価は低いが、食べることもある
- 茎:かじられることがある
- 根:掘り起こす際に傷つけられる
「これぞごちそう!」とばかりに夢中で食べます。
しかし、実だけでは満足できないときや、他に食べ物がないときは、葉や茎にも手を出すんです。
「でも、葉や茎ってそんなにおいしいの?」と思うかもしれません。
実は、アライグマは雑食性の動物。
植物も動物も、さまざまなものを食べる習性があるんです。
落花生の葉や茎には、それなりの栄養価があるんですね。
特に若い芽や柔らかい茎は、アライグマにとっては「おいしいサラダ」のようなもの。
「野菜も食べなきゃ」と、バランスの取れた食事を心がけているのかもしれません。
ただし、根の部分は食べるというよりも、実を掘り出す際に傷つけられることが多いんです。
「ここに実があるはず!」と、がむしゃらに掘るので、根まで被害を受けてしまいます。
このようなアライグマの食性を知ることで、被害の程度や対策の方向性を考えるヒントになります。
「葉まで食べられてる!」という状況なら、かなり深刻な被害が出ている証拠。
早急な対策が必要というわけです。
落花生畑を守る!効果的なアライグマ対策

電気柵の設置「高さと電圧」が重要ポイント
電気柵は、アライグマから落花生畑を守る強力な味方です。でも、ただ設置すればいいというわけではありません。
効果を最大限に発揮させるには、高さと電圧の2つのポイントに注目する必要があるんです。
まず、高さについてですが、地上から15cmから20cmの位置に2段か3段設置するのがおすすめです。
なぜこの高さなのか?
それは、アライグマの体の大きさと動きを考えてのこと。
「ちょうどアライグマの鼻先や胸の辺りに当たる高さなんだ」と思ってください。
次に電圧ですが、4000ボルトから6000ボルトに設定するのが効果的です。
「え?そんな高電圧大丈夫なの?」って思われるかもしれませんね。
でも、ご安心を。
この電圧は一瞬のショックを与えるだけで、人間や動物に深刻な被害を与えることはありません。
電気柵の効果を高めるコツをいくつか紹介しましょう。
- 柵の周りの草を刈り込んで、漏電を防ぐ
- 定期的に電圧をチェックし、必要に応じて調整する
- 雨季には特に注意して、水たまりができないようにする
「ビリッ」とショックを受けたアライグマは、二度と寄り付かなくなるでしょう。
ただし、注意点も。
電気柵は効果的ですが、設置や管理には少し手間がかかります。
また、お子さんやペットがいる家庭では、安全面に十分注意が必要です。
「うちの犬が触っちゃったらどうしよう…」なんて心配な方は、次に紹介する金網フェンスも検討してみてくださいね。
金網フェンスで防御!「目合いと埋め込み深さ」に注意
金網フェンスは、アライグマ対策の定番中の定番。でも、ただ適当に設置しても効果は半減しちゃいます。
ここで押さえたいポイントは、「目合い」と「埋め込み深さ」なんです。
まず目合いについて。
アライグマは意外と器用な動物で、小さな隙間でもすり抜けようとします。
そこで、目合いは5cm以下のものを選びましょう。
「えっ、そんな細かいの必要?」って思うかもしれませんが、これがアライグマの侵入を防ぐ鍵なんです。
次に埋め込み深さ。
これが実は超重要。
なぜって?
アライグマは掘り名人なんです。
地面スレスレにフェンスを設置しても、下から潜り込まれちゃうかもしれません。
そこで、地中に30cm以上埋め込むのがコツ。
「まるで地下要塞みたい!」って感じですね。
効果的な金網フェンスの設置方法をまとめてみましょう。
- 高さは1m以上のものを選ぶ
- 目合い5cm以下の細かいものを使用
- 地中に30cm以上埋め込む
- フェンスの上部を外側に15cm程度折り曲げる
アライグマが登ろうとしても、この折り返しでつまずいちゃうんです。
「よじ登ろうとしたのに、あれ?」って感じで、アライグマも困惑するはず。
金網フェンスのいいところは、一度設置すれば長期間使えること。
電気柵と違って電源も不要だし、お子さんやペットにも安全です。
ただし、設置にはちょっとした力仕事が必要になるので、ご家族や友人と協力して作業するのがおすすめです。
「みんなで力を合わせて、アライグマ対策!」なんて、なんだか楽しそうじゃありませんか?
人家近くの栽培がおすすめ!アライグマを警戒させる工夫
アライグマ対策で意外と効果的なのが、落花生の栽培場所を工夫することなんです。特におすすめなのが、人家の近くでの栽培。
「え?家の近くに畑を作るの?」って思うかもしれませんが、これがアライグマを警戒させる秘策なんです。
アライグマは、基本的に人間を避けます。
だから、人の気配が常にする場所は、彼らにとっては「ちょっと怖い場所」なんです。
家の近くや倉庫のそばなど、人の出入りが多い場所を選ぶことで、アライグマの接近を抑制できるんです。
人家近くでの栽培のメリットを見てみましょう。
- 人の気配でアライグマが警戒する
- 異変に気づきやすい
- 日常的な管理がしやすい
- 夜間の見回りも容易
アライグマは夜行性なので、夜の時間帯に人の気配がするのは、彼らにとってはかなりのプレッシャーになるんです。
ただし、注意点も。
近所迷惑にならないよう、適切な場所選びが重要です。
「隣の家のすぐそばに畑を作っちゃった!」なんてことにならないように気をつけましょう。
また、家の近くに畑を作ることで、別のメリットも。
「今日の落花生、どうかな?」って、ちょっとした時間に様子を見に行けるんです。
アライグマの被害だけでなく、病気や害虫の早期発見にもつながります。
人家近くでの栽培は、まるで落花生を家族の一員として見守るような感覚。
「うちの落花生、すくすく育ってるな〜」なんて、毎日の成長を楽しむこともできるんです。
アライグマ対策と栽培の楽しみ、一石二鳥ですね!
夜間照明の活用で「アライグマの接近を抑制」
夜間照明は、アライグマ対策の強力な武器になるんです。なぜって?
アライグマは夜行性の動物だから、明るい場所は苦手なんです。
「えっ、そんな簡単なことでいいの?」って思うかもしれませんが、これが意外と効果的なんです。
まず、アライグマの生態を考えてみましょう。
彼らは暗闇の中で活動するのが得意。
目も暗闇に適応しているんです。
そこに突然明るい光が当たると、まるでまぶしい日差しを浴びたみたいに感じるんですね。
「うわっ、まぶしい!」って感じで、警戒心が高まるわけです。
効果的な夜間照明の使い方をいくつか紹介しましょう。
- 動きを感知して点灯するセンサーライトを設置する
- ソーラー式のライトで電気代を節約
- LED電球を使って長時間点灯
- 光の向きを畑全体に均等に当てる
アライグマが近づいてきたら自動で点灯するので、「わっ!」と驚いて逃げ出すかもしれません。
まるで、いたずらっ子を懐中電灯で見つけたときのような効果があるんです。
ただし、注意点も。
近所の迷惑にならないよう、光の向きや強さには気をつけましょう。
「隣の家の寝室に光が漏れちゃった!」なんてことにならないように。
また、野生動物の生態系への影響も考慮して、必要最小限の照明にとどめるのがマナーです。
夜間照明は、防犯対策にもなるので一石二鳥。
「アライグマも泥棒も寄せ付けない!」なんて、安心感も倍増です。
ただ、照明を付けっぱなしにするのは電気代が気になるところ。
そんなときは、次に紹介する方法も併せて試してみてくださいね。
周辺環境の整備!「隠れ場所をなくす」ことが重要
アライグマ対策で意外と見落としがちなのが、落花生畑の周辺環境の整備なんです。実は、「隠れ場所をなくす」ことが、アライグマを寄せ付けない重要なポイントなんです。
「え?掃除するだけでいいの?」って思うかもしれませんが、これが意外と効果的なんですよ。
アライグマは、身を隠せる場所があると安心して活動します。
藪や雑木林、積まれた木材や資材の山、これらは全てアライグマにとっての「隠れ家」になるんです。
だから、これらを整理整頓することで、アライグマの行動範囲を制限できるんです。
周辺環境の整備ポイントをまとめてみましょう。
- 畑の周りの草刈りをこまめに行う
- 不要な木材や資材を片付ける
- 果樹の落果はすぐに拾う
- ゴミ置き場は清潔に保つ
- 水たまりができないよう、排水を良くする
背の高い草はアライグマの格好の隠れ場所。
「ザザザッ」と草をかき分けて近づいてくるアライグマの姿が目に浮かびますよね。
草を短く刈っておけば、そんな心配もありません。
また、果樹の落果を放置するのもNG。
腐った果物の匂いは、アライグマにとって「ごちそうはこっちだよ〜」という誘い看板のようなもの。
すぐに拾い集めて処分しましょう。
ゴミ置き場の管理も大切です。
生ゴミの匂いはアライグマを引き寄せます。
「うわっ、くさい!」なんて思うゴミこそ、アライグマには魅力的なんです。
密閉容器を使うなど、匂いが漏れないよう工夫しましょう。
この環境整備、実はアライグマ対策だけじゃなく、庭や畑の美観を保つことにもつながるんです。
「うちの畑、きれいになったな〜」なんて、ちょっとした達成感も味わえるかもしれません。
一石二鳥、いや三鳥くらいの効果があるんじゃないでしょうか?
落花生農家必見!アライグマ被害を劇的に減らす裏技

ラベンダーの植栽で「アライグマを寄せ付けない」効果
ラベンダーの香りは、アライグマを寄せ付けない効果があるんです。「え?そんな簡単なことで効果があるの?」って思われるかもしれませんね。
でも、実はアライグマは強い香りが苦手なんです。
ラベンダーの香りは、人間にとっては心地よいものですが、アライグマにとっては「うわっ、くさい!」と感じる強烈な匂いなんです。
この特性を利用して、落花生畑の周りにラベンダーを植栽することで、アライグマの侵入を防ぐことができるんです。
ラベンダーの植栽方法をいくつか紹介しましょう。
- 畑の周囲に1メートル間隔で植える
- 落花生の畝と畝の間にラベンダーを植える
- 畑の入り口付近に集中して植える
- ラベンダーの鉢植えを畑の周りに配置する
大丈夫です。
ラベンダーは比較的育てやすい植物なんです。
水やりも少なめで済むので、手間もそれほどかかりません。
ラベンダーには別の利点もあるんです。
なんと、害虫を寄せ付けない効果もあるんです。
「一石二鳥じゃん!」って感じですよね。
アライグマも害虫も撃退できちゃうんです。
ただし、注意点も。
ラベンダーの効果は万能ではありません。
特に、おなかを空かせたアライグマには、香りだけでは防ぎきれないこともあります。
他の対策と組み合わせることをおすすめします。
それでも、ラベンダーの植栽は手軽で効果的な対策の一つ。
「うちの落花生畑、いい香りがするね〜」なんて、畑仕事も楽しくなっちゃうかもしれませんよ。
使用済み猫砂の活用!「天敵の匂い」で撃退
使用済みの猫砂を活用すると、アライグマを効果的に撃退できるんです。「え?猫のトイレの砂?」って思われるかもしれませんが、これが意外と強力な武器になるんです。
アライグマにとって、猫は天敵の一つ。
猫の匂いがする場所には近づきたくないんです。
使用済みの猫砂には、猫の尿や糞の匂いが染み付いています。
この匂いを嗅いだアライグマは、「ヤバイ!ここに猫がいる!」と勘違いして、落花生畑に近づかなくなるんです。
猫砂の効果的な使い方をいくつか紹介しましょう。
- 畑の周りに薄く撒く
- 小さな布袋に入れて畑の周りにぶら下げる
- プランターに入れて畑の入り口に置く
- 落花生の株の間に少量ずつ撒く
確かに、人間にも多少匂いは感じます。
でも、アライグマほど敏感ではありませんから、私たちが我慢できないほどの匂いではありません。
ただし、使用する際は衛生面に注意が必要です。
生の猫砂をそのまま使うのではなく、一度乾燥させてから使うのがおすすめです。
「カサカサ」と乾いた猫砂なら、扱いやすいですし、匂いも抑えられます。
この方法のいいところは、コストがほとんどかからないこと。
「ニャンコの力を借りて、アライグマ対策!」なんて、猫好きの方にはたまらない方法かもしれませんね。
ペットの猫がいる家庭なら、さらに手軽に実践できます。
ただし、この方法も万能ではありません。
雨が降ると効果が薄れてしまうので、定期的な補充が必要です。
でも、他の対策と組み合わせれば、より強力なアライグマ対策になりますよ。
ソーラー式人感センサーライトで「夜間の侵入を防止」
ソーラー式の人感センサーライトを設置すると、夜間のアライグマの侵入を効果的に防げるんです。「え?ライトだけで大丈夫なの?」って思うかもしれませんが、これが意外と強力な味方になるんですよ。
アライグマは夜行性の動物です。
暗闇の中で活動するのが得意なんです。
そんなアライグマにとって、突然の明かりは大敵。
「うわっ!」ってびっくりして、逃げ出しちゃうんです。
ソーラー式人感センサーライトの設置方法をいくつか紹介しましょう。
- 畑の周囲に数メートル間隔で設置する
- アライグマの侵入経路に向けて光が当たるように調整する
- 高さ1?1.5メートルの位置に取り付ける
- 木や柵にクリップで留めて簡単設置
大丈夫です。
ソーラー式なら、昼間に太陽光で充電して夜に使用するので、電気代はかかりません。
「エコでお財布にも優しい」なんて、いいことづくめですよね。
この方法のいいところは、設置が簡単なこと。
専門的な知識や工具がなくても、誰でも手軽に始められます。
「よし、今日から我が家の落花生畑も夜間警備開始!」なんて気分で設置できちゃいます。
ただし、注意点も。
光が周囲の家に迷惑をかけないよう、角度調整は慎重に行いましょう。
また、野生動物の生態系への影響も考え、必要以上に明るくしすぎないのがマナーです。
この方法は、アライグマ対策だけでなく、防犯対策にもなります。
「一石二鳥どころか三鳥くらいあるんじゃない?」なんて、うれしい効果が期待できるんです。
CDの反射光でアライグマを怖がらせる意外な方法
古いCDを使って、アライグマを怖がらせる方法があるんです。「え?CDで?」って驚くかもしれませんが、これが意外と効果的なんですよ。
CDの表面は、光をキラキラと反射する性質があります。
この反射光が、アライグマにとっては不気味で怖いものなんです。
風で揺れるCDの反射光は、まるで「ピカピカ」と動く目のように見えるんでしょうね。
アライグマは「うわっ、何か見てる!」と勘違いして、近づくのをためらうんです。
CDを使ったアライグマ対策の方法をいくつか紹介しましょう。
- CDを紐で吊るして、畑の周りにぶら下げる
- CDを棒に刺して、畑の中に立てる
- CDを切って鋭い形にし、畑の周りに並べる
- CDをモビールのように組み合わせて設置する
大丈夫です。
最近はCDを使わなくなった家庭も多いので、友達や親戚に聞いてみれば、きっと喜んで譲ってくれるはずです。
「いらないCDありませんか?」って声をかけるだけで、意外とたくさん集まるかもしれません。
この方法のいいところは、コストがほとんどかからないこと。
家にあるものを再利用できるので、エコでもあります。
「捨てようと思っていたCDが、こんな形で役立つなんて!」って、うれしくなりますよね。
ただし、注意点も。
CDの反射光が周囲の家に迷惑をかけないよう、設置場所と角度には気をつけましょう。
また、強風で飛ばされないよう、しっかり固定することも大切です。
この方法は、見た目もちょっとおしゃれ。
「うちの畑、なんだかアートみたい!」なんて、畑仕事が楽しくなるかもしれませんよ。
アライグマ対策と畑の装飾、一石二鳥の方法なんです。
アンモニア水で「強烈な臭い」のバリアを作る
アンモニア水を使って、アライグマを寄せ付けない臭いのバリアを作ることができるんです。「え?アンモニア?強すぎない?」って思うかもしれませんが、これが意外と効果的な方法なんですよ。
アンモニアの強烈な臭いは、アライグマの鋭敏な嗅覚を刺激します。
人間にとっても強い匂いですから、アライグマにとってはもっと強烈。
「うっ、くさい!」って感じで、アライグマは近づきたくなくなるんです。
アンモニア水を使ったアライグマ対策の方法をいくつか紹介しましょう。
- 布にアンモニア水を染み込ませ、畑の周りに置く
- ペットボトルの底に穴を開け、アンモニア水を入れて畑に立てる
- スプレーボトルに薄めたアンモニア水を入れ、畑の周りに吹きかける
- アンモニア水を入れた容器を、畑の入り口付近に置く
確かに、取り扱いには注意が必要です。
使用する際は、必ず薄めて使いましょう。
原液のまま使うのは危険ですからね。
また、風向きにも注意して、人や作物にかからないようにしましょう。
この方法のいいところは、効果が即効性があること。
設置したその日から、アライグマを寄せ付けない効果が期待できます。
「今夜からアライグマよ、さようなら!」なんて気分で設置できちゃいます。
ただし、注意点も。
アンモニアの臭いは時間とともに弱くなるので、定期的な補充が必要です。
また、雨が降ると効果が薄れてしまうので、天候にも注意が必要です。
この方法は、他の害獣対策にも効果があるんです。
「アライグマだけじゃなく、他の動物も寄り付かなくなった!」なんて、うれしい効果が期待できますよ。
ただし、使用する際は周囲の環境にも配慮しましょう。
強すぎる臭いで近所迷惑にならないよう、適量を守ることが大切です。