アライグマを撃退する効果的な音とは?【高周波音が最も効果的】音源の選び方と3つの使用上の注意点

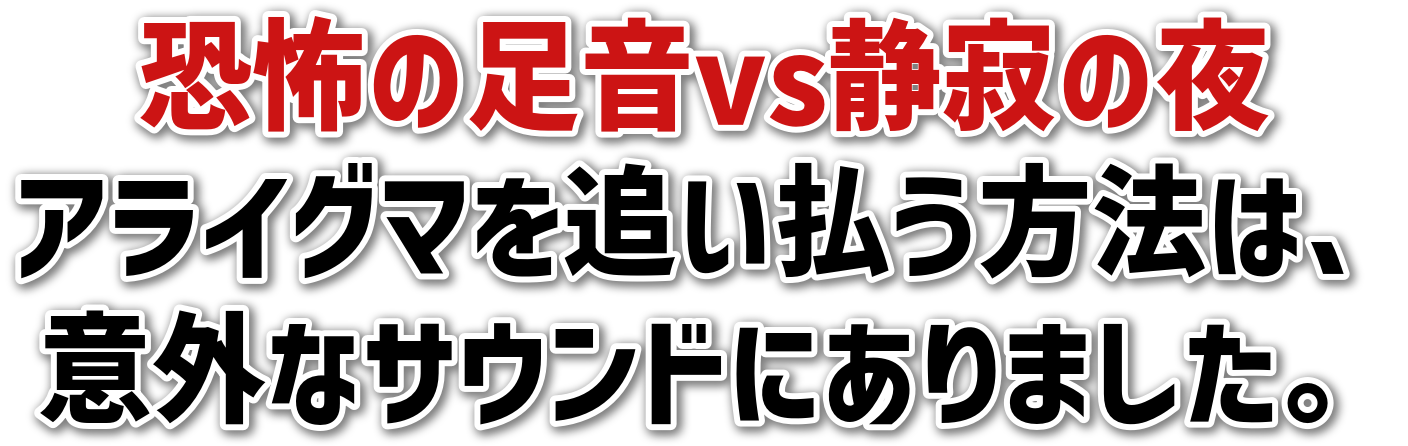
【この記事に書かれてあること】
アライグマの被害に悩まされていませんか?- 20〜25キロヘルツの高周波音がアライグマ撃退に最も効果的
- 突発的な大音量や鋭い金属音もアライグマを驚かせる
- 音の継続時間は10〜30秒が最適で、15分おきに鳴らすのが理想的
- 80〜90デシベルの音量でアライグマを効果的に撃退
- 身近な材料を使った5つの簡単な音源作りで被害を激減させる
実は、音を使った撃退法が驚くほど効果的なんです。
でも、「どんな音がいいの?」「音量はどのくらい?」なんて疑問がわいてきますよね。
この記事では、アライグマを撃退する最適な音の特徴や使い方を詳しく解説します。
さらに、身近な材料で簡単に作れる音源も紹介。
これであなたの庭もアライグマフリーに!
さあ、アライグマとの音合戦、始めましょう!
【もくじ】
アライグマを撃退する音の特徴とは?効果的な対策法を解説

アライグマが最も嫌う「高周波音」の周波数帯は20〜25キロヘルツ!
アライグマを撃退する最も効果的な音は、20〜25キロヘルツの高周波音です。この周波数帯は、アライグマの耳に不快感を与えるのに最適なんです。
「なぜ高周波音がアライグマに効くの?」と思われるかもしれません。
実は、アライグマの聴覚は人間よりもずっと敏感なんです。
人間には聞こえない高い音も、アライグマにはバッチリ聞こえちゃうんです。
高周波音の効果は、次のような特徴があります:
- アライグマの神経を刺激し、不快感を与える
- 長時間聞くと、めまいや吐き気を引き起こす
- アライグマの警戒心を高め、その場所から離れさせる
「高周波音を出し続ければいいんでしょ?」と思うかもしれませんが、それは逆効果。
アライグマは賢い動物なので、同じ音に慣れてしまう可能性があるんです。
そこで、音を断続的に鳴らすのがおすすめ。
例えば、15分おきに10〜30秒間音を鳴らすといった具合です。
このように不規則に音を鳴らすことで、アライグマが音に慣れるのを防ぎ、効果を長く持続させることができるんです。
「でも、近所迷惑にならない?」と心配する方もいるでしょう。
安心してください。
20キロヘルツ以上の高周波音は、ほとんどの人間には聞こえません。
ですので、近隣への迷惑を最小限に抑えながら、効果的にアライグマを撃退できるというわけです。
突発的な大音量や鋭い金属音もアライグマ撃退に効果的!
高周波音だけでなく、突発的な大音量や鋭い金属音もアライグマ撃退に効果的です。これらの音は、アライグマをビックリさせ、警戒心を高めるのに役立ちます。
「どんな音が効果的なの?」と疑問に思う方もいるでしょう。
具体的には、次のような音が効果的です:
- ガシャーンという鍋や金属板を叩く音
- シャカシャカという空き缶の中に小石を入れて振る音
- ピーッという笛や警報音
- バンッという風船を割る音
突然の大きな音に驚いて、すぐにその場から逃げ出したくなるわけです。
ただし、注意点もあります。
人間の耳にも聞こえる音なので、夜中に大音量を出すのは近所迷惑になってしまいます。
そこで、こんな工夫をしてみましょう。
- 日中にアライグマの出没場所に音源を仕掛けておく
- 動きセンサーと連動させて、アライグマが近づいたときだけ音が鳴るようにする
- 音量を調整して、家の中からは聞こえない程度に設定する
「でも、アライグマってすぐに慣れちゃわないの?」という心配も出てくるかもしれません。
確かにその通りです。
そこで、複数の音を組み合わせたり、音を鳴らす間隔を不規則にしたりするのがおすすめ。
アライグマが音に慣れにくくなり、長期的な効果が期待できるんです。
アライグマ撃退音の継続時間は「10〜30秒」が最適!
アライグマを効果的に撃退するには、音の継続時間にも注意が必要です。最適な継続時間は10〜30秒程度。
これくらいの長さが、アライグマを追い払うのに最も効果的なんです。
「なぜ10〜30秒なの?」と思われるかもしれません。
理由は簡単。
短すぎると効果が薄く、長すぎるとアライグマが慣れてしまうからです。
ちょうどいい長さで、アライグマに「ここは危険だ!」と思わせるのがコツなんです。
効果的な音の使い方をもっと詳しく見てみましょう:
- 10秒未満:ビックリはするけど、すぐに戻ってくる可能性大
- 10〜30秒:十分に警戒心を高められ、その場から離れる
- 30秒以上:音に慣れてしまい、効果が薄れる可能性あり
ここで大切なのが、音を鳴らす間隔です。
「ずっと鳴らしっぱなしにすれば効果抜群じゃない?」なんて思う人もいるかもしれません。
でも、それは大間違い!
アライグマは賢い動物です。
同じパターンの音が続くと、すぐに「あ、この音は危険じゃないんだ」と学習してしまいます。
そこで、こんな工夫をしてみましょう:
- 15分おきに音を鳴らす
- 鳴らす時間を10〜30秒の間でランダムに変える
- 複数の音源を用意し、不規則に切り替える
「ピーッ」「ガシャーン」「シャカシャカ」と、まるで音のサプライズパーティーですね。
ただし、注意点も忘れずに。
夜中に大きな音を出し続けると、今度は人間の隣人が「ガルルル」っと怒り出しちゃうかもしれません。
音量調整と使用時間帯の配慮を忘れずに。
アライグマ撃退と近所付き合いの両立、難しいようで意外と簡単なんです。
市販の超音波発生器は「ホームセンター」で入手可能!
アライグマ撃退用の超音波発生器は、実はホームセンターで簡単に入手できるんです。「え?そんな専門的な機器がホームセンターにあるの?」と驚く方も多いかもしれません。
でも、本当なんです。
ホームセンターの害獣対策コーナーに行けば、アライグマ撃退用の超音波発生器がズラリと並んでいます。
まるで「はい、どうぞ。アライグマ撃退はこちらでどうぞ?」と言わんばかり。
値段も手頃なものが多く、2,000円から1万円程度で購入できます。
選び方のポイントは以下の通りです:
- 周波数帯:20〜25キロヘルツの高周波音が出せるもの
- 防水性能:屋外で使用するため、防水機能は必須
- 電源:電池式や太陽光充電式など、設置場所に合わせて選ぶ
- センサー機能:動きを感知して自動で作動するタイプが便利
- 音量調整:状況に応じて音量を変えられるものが◎
ホームセンターのスタッフさんに相談すれば、親切に教えてくれますよ。
「うちの庭にアライグマが出るんですけど…」と言えば、「あ?、それならこの商品がおすすめですよ!」とピッタリの商品を紹介してくれるはず。
ただし、購入する前に忘れずにチェックしたいポイントがあります。
それは、返品・交換policyです。
「せっかく買ったのに効果がイマイチ…」なんてことにならないよう、事前に確認しておきましょう。
また、使用する際は近隣への配慮も忘れずに。
「ウチの隣の家、なんか変な音がするんだけど…」なんて噂が立たないよう、設置場所や使用時間帯には気を付けましょう。
最後に、超音波発生器を使う際のワンポイントアドバイス。
複数台を組み合わせて使うと、より効果的です。
庭の入り口や家の周りに戦略的に配置すれば、まるでアライグマ撃退の要塞のよう。
これで「アライグマよ、さようなら?」というわけです。
スマートフォンアプリで高周波音を再生するのも「意外と効果的」!
実は、スマートフォンアプリを使って高周波音を再生するのも、アライグマ撃退に意外と効果的なんです。「え?スマホで?そんな簡単にできるの?」と思われるかもしれませんが、本当なんです。
アライグマ撃退用の高周波音アプリは、多くのスマートフォンで無料でダウンロードできます。
使い方は超簡単。
アプリを起動して、再生ボタンを押すだけ。
すると、人間には聞こえにくい高周波音が流れ始めます。
こんなメリットがあります:
- 手軽に試せる(すぐにダウンロードして使える)
- コストがかからない(多くのアプリが無料)
- 場所を選ばない(スマホさえあれば、どこでも使える)
- 音量や周波数を調整できる(状況に応じて変更可能)
スマートフォンのスピーカーの性能によっては、十分な音量や周波数が出せない場合があります。
「ピーッ」と鳴らしたつもりが、アライグマにとっては「ん?なんか聞こえた気がする…」程度の効果しかない可能性も。
そこで、効果を高めるためのワンポイントアドバイス。
外部スピーカーを接続すると、より大きな音量で高周波音を再生できます。
「よーし、これでアライグマ撃退パワーアップだ!」という感じですね。
また、アプリを使う際は、バッテリー消費にも注意が必要です。
「アライグマ撃退はできたけど、肝心のスマホの電池が切れちゃった…」なんてことにならないよう、充電器を忘れずに。
最後に、アプリを使う際の面白いアイデアをご紹介。
タイマー機能付きのアプリを使えば、決まった時間に自動で高周波音を再生できます。
例えば、アライグマの活動が活発になる夕方から夜にかけて、30分おきに10秒間音を鳴らすようセットする。
すると、まるでアライグマ撃退の自動システムのよう。
「はい、アライグマさん、お帰りの時間ですよ?」というわけです。
音量と頻度の調整で効果を最大化!近隣への配慮も忘れずに

アライグマ撃退に最適な音量は「80〜90デシベル」!
アライグマを効果的に撃退するなら、80〜90デシベルの音量がおすすめです。この音量なら、アライグマには十分な威力がありながら、人間の耳には聞こえにくいんです。
「えっ、そんな大きな音で大丈夫なの?」と心配する方もいるでしょう。
でも安心してください。
80〜90デシベルというと、人間の耳では「ちょっとうるさいかな」くらいの音量です。
例えると、忙しい道路の騒音や、掃除機の音程度。
アライグマには十分効果があるのに、人間にはそれほど気にならないちょうどいい音量なんです。
ただし、音量の調整には注意が必要です。
以下のポイントを押さえましょう:
- まずは低めの音量から始めて、徐々に上げていく
- アライグマの反応を見ながら、効果的な音量を見つける
- 近隣への影響を考慮し、夜間は音量を少し下げる
- 音源からの距離によって音量が変わるので、設置場所も工夫する
そんな時は、音量だけでなく音の種類も変えてみましょう。
例えば、高周波音に加えて、突発的な金属音を組み合わせるのも効果的です。
「ピー」という高周波音の合間に「ガシャン!」という金属音を入れれば、アライグマもビックリ。
「うわっ、なんだこの音は!」って感じで、逃げ出しちゃうかもしれません。
音量調整は、まるでアライグマとの駆け引きのようなもの。
少しずつ調整しながら、最適な音量を見つけていくのがコツです。
根気よく続けていけば、きっとアライグマを撃退できるはずです。
がんばってみてくださいね!
日没後から夜明けまで「15分おき」に音を鳴らすのが理想的!
アライグマ撃退音の鳴らし方、実は大事なポイントがあるんです。それは、日没後から夜明けまでの間、15分おきに音を鳴らすこと。
これが最も効果的なんです。
「え?ずっと鳴らしっぱなしじゃダメなの?」なんて思った方、正解です!
実は、音を連続して鳴らし続けるのは逆効果。
アライグマって意外と賢い動物で、同じ音が続くとすぐに慣れちゃうんです。
「あ、この音は怖くないな」って学習しちゃうわけです。
そこで、こんな戦略を立ててみましょう:
- 日没直後に1回目の音を鳴らす(ピーッ!
) - 15分間沈黙(シーン…)
- 2回目の音を鳴らす(ガシャーン!
) - また15分間沈黙(シーン…)
- これを夜明けまで繰り返す
まるで、いつ先生に当てられるかわからないドキドキ感のある授業のよう。
アライグマも「ヒヤヒヤ」しながら、だんだん近づく気力がなくなっちゃうんです。
ただし、注意点もあります。
夜中の3時に「ガシャーン!」って音がしたら、お隣さんびっくりしちゃいますよね。
そこで、深夜の時間帯は音量を少し下げたり、高周波音だけにしたりする工夫も必要です。
「でも、15分おきに起きて音を鳴らすなんて無理…」って思いますよね。
大丈夫です。
タイマー付きの装置を使えば、自動で音を鳴らせます。
あなたは安心して眠れるし、アライグマは眠れない。
これぞ理想的な「アライグマ撃退作戦」というわけです。
春から秋は「アライグマの活動期」で音の使用頻度を上げるべき!
アライグマ撃退音の使い方、実は季節によって変えるのがおすすめなんです。特に春から秋にかけては、アライグマの活動が活発になる時期。
この時期は音の使用頻度を上げるべきなんです。
「え?アライグマにも活動期があるの?」って思いましたか?
そうなんです。
アライグマは冬眠しない動物ですが、寒い冬は活動が鈍るんです。
でも、春になると急に元気に。
まるで「よーし、新学期だ!」って感じで活発になっちゃうんです。
季節別のアライグマ対策、こんな感じで考えてみましょう:
- 春(3〜5月):繁殖期で特に活発。
音の頻度を最大に - 夏(6〜8月):食べ物を求めて行動範囲が広がる。
高い頻度を維持 - 秋(9〜11月):冬に備えて食べ物を探す。
頻度は高めに - 冬(12〜2月):活動が鈍るが油断は禁物。
頻度を少し下げてもOK
「ピーッ」「ガシャーン」「キーン」と、まるでアライグマ撃退交響曲のよう。
アライグマも「もう勘弁してよ〜」って音を聞くたびにため息をつくかも。
ただし、冬場は少し対策を変えてもOK。
例えば、30分おきに音を鳴らすとか、夜中の時間帯は音を止めるとか。
でも、完全に対策をやめるのはNG。
冬でも暖かい日はアライグマが活動することがあるので、油断大敵です。
「でも、毎日音を鳴らすの疲れちゃう…」なんて思う方もいるでしょう。
大丈夫です。
自動タイマー付きの装置を使えば、季節に合わせて簡単に設定を変更できます。
「はい、春です。アライグマ撃退モード全開!」って感じで。
この季節に合わせた対策を続けていけば、きっとアライグマも「この家は居心地が悪いな」って思ってくれるはず。
根気強く続けることが、アライグマ撃退への近道なんです。
20キロヘルツ以上の高周波音は「人間には聞こえにくい」ので安心!
アライグマ撃退音で心配なのは、近所迷惑にならないかということ。でも、20キロヘルツ以上の高周波音なら大丈夫。
人間には聞こえにくいので、安心して使えるんです。
「えっ、人間に聞こえない音ってあるの?」って思いましたか?
実は、人間の耳で聞こえる音の範囲って限られているんです。
一般的に、人間が聞こえる音は20ヘルツから20キロヘルツまで。
それ以上の高い音は、ほとんどの人には聞こえないんです。
でも、アライグマはどうかというと…
- 人間:20ヘルツ〜20キロヘルツの音が聞こえる
- アライグマ:100ヘルツ〜40キロヘルツの音が聞こえる
まるで、大人には聞こえない「モスキート音」のようなものです。
ただし、注意点もあります:
- 若い人は高い音が聞こえることも(個人差あり)
- ペットの犬や猫は聞こえる可能性がある
- 機器の性能によっては、人間にも聞こえる音が出ることも
事前に説明して理解を得ておけば大丈夫。
「実はね、うちアライグマ対策してるんだ〜」って感じで。
むしろ、ご近所の方も「うちも困ってたのよ」なんて、協力してくれるかもしれません。
高周波音を使うときは、まるで忍者のよう。
人間には気づかれずに、アライグマだけをこっそり追い払う。
そう考えると、なんだかちょっとワクワクしませんか?
アライグマ撃退、実は楽しい作戦になるかもしれませんよ。
ペットへの影響を考慮し「使用時間や音量」に配慮が必要!
アライグマ撃退音、効果は抜群ですが、ペットへの影響も忘れちゃいけません。使用時間や音量に気を配れば、ペットにも優しい対策ができるんです。
「えっ、ペットにも影響あるの?」って思いましたか?
そうなんです。
犬や猫は人間よりも敏感な耳を持っているので、高周波音を聞くことができるんです。
まるで、人間には聞こえない秘密の会話を聞いているようなもの。
ペットへの影響を最小限に抑えるポイントは以下の通りです:
- 使用時間の調整:ペットが寝ている時間帯を選ぶ
- 音量の調整:必要以上に大きな音は避ける
- 設置場所の工夫:ペットの居場所から離れた場所に設置
- ペットの様子観察:不快な反応があれば即座に対応
夜9時から朝5時まで高周波音を鳴らす。
でも、ペットが寝ている部屋からは離れた場所に設置する。
「ごめんね、ちょっとの間だけガマンしてね」って感じで。
ただし、ペットの反応には個体差があります。
「うちの犬、全然平気みたい」なんて犬もいれば、「うちの猫、ちょっと落ち着かなそう…」って猫もいるかもしれません。
だから、使い始めたらペットの様子をよく観察することが大切。
もし、ペットが不快そうな反応を示したら…
- まず音量を下げてみる
- それでもダメなら、使用時間を短くする
- それでも改善しないなら、別の対策を考える
音による対策以外にも、光や臭いを使った方法など、様々な対策があります。
ペットにもアライグマにも優しい方法を、根気強く探していけばきっと見つかるはずです。
アライグマ対策は、まるで家族全員で取り組むプロジェクトのよう。
ペットも含めて、みんなで協力しながら最適な方法を見つけていく。
そんな風に考えれば、アライグマ撃退も楽しい家族の思い出になるかもしれませんね。
驚きの裏技!身近な材料でアライグマを撃退する音源作り

ペットボトルに水を入れて「日光の反射」でアライグマを威嚇!
ペットボトルを使った簡単なアライグマ撃退法をご紹介します。なんと、水を入れたペットボトルを庭に置くだけで、アライグマを威嚇できるんです!
「え?そんな簡単なことでアライグマが逃げるの?」と思われるかもしれません。
でも、これがけっこう効果的なんです。
仕組みはこうです。
日光がペットボトルの水面で反射して、キラキラと光るんです。
この予期せぬ光の動きが、アライグマをビックリさせるわけです。
具体的な作り方はこちら:
- 透明なペットボトルを用意する
- ボトルの中に水を8分目くらいまで入れる
- 蓋をしっかり閉める
- 庭の日当たりの良い場所に置く
「おや?あそこも光ってる!こっちも!」とアライグマの警戒心を高めることができます。
ただし、注意点もあります。
強風の日はボトルが倒れてしまう可能性があるので、重石を置くなどの工夫が必要です。
また、長期間放置すると水が濁ってしまうので、定期的に水を入れ替えましょう。
「でも、ペットボトルだけで本当に効果あるの?」なんて疑問も出てくるかもしれません。
確かに、これだけでは完璧な対策とは言えません。
でも、他の方法と組み合わせることで、より効果的なアライグマ対策になるんです。
例えば、高周波音と一緒に使えば、視覚と聴覚の両方でアライグマを撃退できます。
この方法、コストもかからないし、環境にも優しい。
まさに一石二鳥のアライグマ対策なんです。
さあ、今すぐ試してみませんか?
アルミホイルを庭に散らばせて「不規則な音」で撃退!
アルミホイルを使ったアライグマ撃退法、実はすごく効果的なんです。庭にアルミホイルを散らばせるだけで、アライグマを撃退できちゃいます。
不思議でしょ?
「えっ?アルミホイルで?」って思いましたよね。
実は、アルミホイルには2つの効果があるんです。
1つは音、もう1つは光です。
まず、音の効果について説明しましょう。
アライグマが歩くとアルミホイルがカサカサ、ガサガサと音を立てます。
この不規則な音がアライグマを驚かせるんです。
「うわっ、何この音!怖い!」ってな感じで、アライグマは逃げ出しちゃうんです。
次に光の効果。
アルミホイルは光を反射しますよね。
この反射光がアライグマの目をくらませるんです。
夜行性のアライグマにとって、突然の光は本当に苦手。
「まぶしい!ここは危険だ!」って思っちゃうわけです。
さて、実際の使い方はこんな感じ:
- アルミホイルを30cmくらいの長さに切る
- それを軽くクシャクシャにする
- 庭のあちこちに散らばせる
- 特にアライグマが来そうな場所に多めに置く
アライグマが予測できないようにするのがコツです。
ただし、注意点もあります。
強風の日はアルミホイルが飛ばされてしまう可能性があるので、石で押さえるなどの工夫が必要です。
また、長期間放置すると見た目が悪くなるので、定期的に新しいものと交換しましょう。
「でも、ご近所の目が気になるなぁ…」って思う方もいるかもしれません。
そんな時は、庭の目立たない場所や、植木の下などに置いてみてください。
効果はそのままで、見た目も気にならなくなりますよ。
この方法、材料費もほとんどかからないし、すぐに始められる。
まさに、今すぐできるアライグマ対策の決定版です。
さあ、アルミホイルでアライグマバイバイ作戦、始めてみませんか?
風鈴を多数設置して「予期せぬ音」でアライグマを警戒させる!
風鈴を使ったアライグマ撃退法、実はこれがなかなかの優れもの。庭に風鈴をいくつも設置するだけで、アライグマを効果的に警戒させることができるんです。
「風鈴って、夏の風物詩じゃないの?」なんて思った方、その通りです。
でも、実はアライグマ対策にもピッタリなんです。
なぜかって?
それは風鈴の音が持つ特徴にあります。
風鈴の音には、こんな効果があるんです:
- 予期せぬタイミングで鳴る
- 音の高さや大きさが不規則
- 金属音がアライグマを驚かせる
- 継続的に音を発する
「チリンチリン」という不規則な音に、アライグマは「うわっ、何この音!怖い!」と思って警戒するわけです。
さて、具体的な設置方法はこんな感じ:
- 風鈴を複数用意する(3個以上がおすすめ)
- 庭のあちこちに吊るす
- 特にアライグマが来そうな場所に重点的に設置
- 高さを変えて設置すると効果的
ガラス製、金属製、竹製など、様々な素材の風鈴を組み合わせると、より不規則な音が出せます。
ただし、注意点もあります。
近所迷惑にならないよう、音量には気をつけましょう。
特に夜間は、小さめの風鈴を使うなどの配慮が必要です。
「でも、風鈴ってずっと鳴ってるの?うるさくないかな…」って心配する方もいるかもしれません。
大丈夫です。
風がないときは鳴りませんし、人間の耳には心地よい音として聞こえることが多いんです。
この方法、見た目もおしゃれだし、涼しげな雰囲気も演出できる。
一石二鳥どころか、三鳥くらいの効果があるんです。
さあ、あなたの庭を風鈴でいっぱいにして、アライグマ撃退と夏気分を同時に楽しんでみませんか?
ソーラーライトで「突然の光」と音でアライグマを驚かせる!
ソーラーライトを使ったアライグマ撃退法、これが意外と効果的なんです。庭にソーラーライトを設置するだけで、アライグマを驚かせて追い払うことができるんです。
「えっ?ただの庭のライトでアライグマが逃げるの?」って思いましたよね。
実は、ソーラーライトには2つの効果があるんです。
1つは光、もう1つは音です。
まず、光の効果について説明しましょう。
多くのソーラーライトには人感センサーが付いています。
アライグマが近づくと、突然ライトが点灯するんです。
この予期せぬ光に、アライグマは「うわっ、何これ!」ってビックリしちゃうわけです。
次に音の効果。
最近のソーラーライトの中には、光と同時に音を出すタイプもあるんです。
「ピッ」とか「ブーッ」とか、そんな感じの音です。
この突然の音にも、アライグマは驚いて逃げ出しちゃいます。
さて、具体的な設置方法はこんな感じ:
- 人感センサー付きのソーラーライトを選ぶ
- 可能なら音も出るタイプを選ぶ
- 庭のアライグマが来そうな場所に設置
- 複数のライトを異なる場所に設置するとより効果的
アライグマの目の高さに合わせて設置すると、より効果的です。
ただし、注意点もあります。
近所の方への配慮も忘れずに。
光が強すぎたり、音が大きすぎたりすると、ご近所トラブルの原因になってしまいます。
適度な明るさと音量のものを選びましょう。
「でも、電気代がかかるんじゃ…」って心配する方もいるかもしれません。
大丈夫です。
ソーラーライトなので、電気代はかかりません。
太陽の光で充電されるので、環境にも優しいんです。
この方法、防犯対策にもなるし、夜の庭を素敵に演出できる。
まさに一石二鳥のアライグマ対策なんです。
さあ、あなたの庭をソーラーライトで飾って、アライグマ撃退と素敵な夜景を同時に楽しんでみませんか?
古いCDをひもで吊るして「風で揺れる音」を利用!
古いCDを使ったアライグマ撃退法、これが意外と効果的なんです。使わなくなったCDをひもで吊るすだけで、アライグマを追い払うことができちゃいます。
不思議でしょ?
「えっ?CDでアライグマが逃げるの?」って思いましたよね。
実は、CDには3つの効果があるんです。
音と光と動きです。
まず、音の効果について説明しましょう。
風が吹くとCDがカラカラ、コロコロと音を立てます。
この不規則な音がアライグマを驚かせるんです。
「うわっ、何この音!怖い!」ってな感じで、アライグマは逃げ出しちゃうんです。
次に光の効果。
CDは光を反射しますよね。
この反射光がキラキラと動いて、アライグマの目をくらませるんです。
夜行性のアライグマにとって、この動く光は本当に苦手。
「まぶしい!ここは危険だ!」って思っちゃうわけです。
最後に動きの効果。
風で揺れるCDの動きが、アライグマを不安にさせるんです。
「あれ何?動いてる!」って感じで、警戒心を高めちゃうんです。
さて、実際の作り方はこんな感じ:
- 使わなくなったCDを集める
- CDの穴にひもを通す
- ひもの長さを変えて、複数のCDを一本のひもにつなぐ
- 庭の木の枝やベランダなどに吊るす
庭のあちこちにCDを吊るすことで、より広い範囲でアライグマを撃退できます。
ただし、注意点もあります。
強風の日はCDが激しく動いて音が大きくなる可能性があるので、近所の方への配慮も忘れずに。
また、長期間外に置くとCDが劣化する可能性があるので、定期的に新しいものと交換しましょう。
「でも、見た目が気になるなぁ…」って思う方もいるかもしれません。
そんな時は、庭の奥や、植木の陰などに設置してみてください。
効果はそのままで、見た目も気にならなくなりますよ。
この方法、材料費もほとんどかからないし、すぐに始められる。
まさに、今すぐできるアライグマ対策の決定版です。
さあ、古いCDでアライグマバイバイ作戦、始めてみませんか?