アライグマが苦手な音は何?【突発的な大音量が効果的】自宅で実践できる4つの音による撃退方法

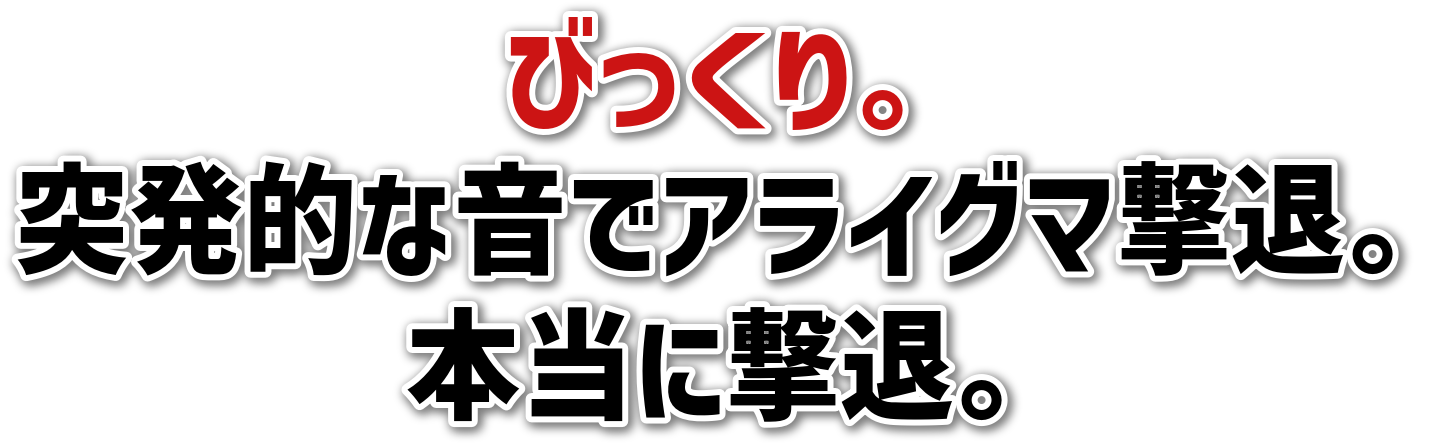
【この記事に書かれてあること】
アライグマの被害に悩まされていませんか?- アライグマは人間の1.5倍の聴覚感度を持ち、高周波に敏感
- 20?25kHzの高周波音がアライグマ撃退に最も効果的
- 音源はアライグマの侵入経路近くに設置するのが効果的
- 突発的な大音量や不規則な音がアライグマを効果的に追い払う
- ペットボトルや風鈴など身近な材料で自作音源が可能
実は、音を使った対策が驚くほど効果的なんです。
アライグマは私たちの1.5倍も敏感な聴覚を持っているため、特定の音に弱いという特徴があります。
でも、どんな音が効果的なのでしょうか?
この記事では、アライグマが苦手な音の特徴と、身近な材料で簡単に作れる音源をご紹介します。
これらの方法を使えば、アライグマを優しく、でも確実に撃退できるんです。
さあ、音の力でアライグマ対策を始めましょう!
【もくじ】
アライグマが苦手な音とは?特徴と効果を徹底解説

アライグマの聴覚は人間の1.5倍!高周波に敏感
アライグマは人間よりも優れた聴覚を持っています。その感度は人間の約1.5倍にもなるんです。
「えっ、そんなに聞こえるの?」と驚く方も多いでしょう。
実は、アライグマの耳は高周波音に特に敏感なんです。
人間には聞こえない高い音まで聞き取れるため、音を使った対策が効果的なんです。
アライグマの聴覚の特徴を詳しく見てみましょう。
- 人間の可聴域を超える20kHz以上の音も聞こえる
- 夜行性のため、夜間はより敏感になる
- わずかな物音も素早く察知できる
捕食者の気配を察知したり、獲物を見つけたりするのに活用しているんです。
でも、この特徴は私たちにとってはチャンス。
アライグマ対策に音を使えば、効果的に撃退できるかもしれません。
「よーし、この特徴を逆手に取って対策しよう!」そんな気持ちになりますよね。
ただし、注意点もあります。
アライグマは賢い動物なので、同じ音を長期間使い続けると慣れてしまう可能性があります。
効果的な対策には、音の種類や使い方を工夫する必要があるんです。
20?25kHzの高周波音が「最も効果的」な理由
アライグマ撃退に最も効果的な音は、20?25kHzの高周波音です。この周波数帯がアライグマにとって特に不快なんです。
なぜこの周波数が効果的なのでしょうか?
理由は3つあります。
- アライグマの聴覚が最も敏感な範囲
- 人間にはほとんど聞こえないため、近隣への迷惑が少ない
- アライグマに強い警戒心を引き起こす
私たちには少し耳障りな音ですが、アライグマにとってはもっと不快な音なんです。
この高周波音を聞くと、アライグマは「ここは危険かも!」と感じて、その場から離れようとします。
まるで、私たちが急に大きな物音を聞いてビクッとするのと同じような反応なんです。
ただし、使い方には注意が必要です。
- 長時間連続して鳴らさない
- 音量は適度に保つ
- 定期的に周波数を変える
「でも、そんな高い音、どうやって出すの?」と思った方もいるでしょう。
実は、ホームセンターなどで売られているアライグマ対策用の超音波発生器を使えば、簡単に高周波音を出せるんです。
これらの機器を使えば、効果的なアライグマ対策が可能になりますよ。
低周波音はNG!アライグマ撃退に逆効果な音
低周波音は、アライグマ撃退にはあまり効果がありません。むしろ、逆効果になる可能性もあるんです。
なぜ低周波音はNGなのでしょうか?
理由は主に3つあります。
- アライグマの聴覚特性に合っていない
- 警戒心を引き起こしにくい
- 慣れやすい音である
この音を聞いても、あまりビクッとしませんよね。
アライグマも同じなんです。
低周波音の問題点をもう少し詳しく見てみましょう。
- 100Hz以下の低周波音はほとんど効果がない
- 自然界の音(風の音、雨音など)に似ているため、警戒心を引き起こしにくい
- 長時間聞いていると慣れてしまい、無視するようになる
低周波音そのものがアライグマを引き寄せるわけではないんです。
ただ、撃退効果が期待できないというだけなんです。
では、どんな音を避けるべきでしょうか?
例えば、次のような音は効果が薄いと言えます。
- 扇風機やエアコンの低いモーター音
- 遠くで鳴っている雷の音
- 大型車両の通過音
むしろ、こういった音に慣れてしまうと、他の対策音にも反応しにくくなってしまう可能性があります。
アライグマ撃退には、やはり高周波音を中心とした対策が効果的。
低周波音に頼らず、適切な音を選ぶことが大切なんです。
音量を上げすぎるのは「逆効果」!適切な音量とは
アライグマ撃退の音対策で、よくある間違いが音量を上げすぎることです。大きな音なら効果的だと思いがちですが、実はこれが逆効果になってしまうんです。
では、なぜ音量を上げすぎてはいけないのでしょうか?
理由は主に3つあります。
- アライグマが音に慣れてしまう
- 近隣トラブルの原因になる
- 他の野生動物にも影響を与える
でも、実はそうではないんです。
適切な音量について、もう少し詳しく見てみましょう。
- 人間の耳で聞いて不快にならない程度が目安
- 昼間よりも夜間は音量を下げる
- 周辺環境に合わせて調整する
ストレスが高まると、かえって攻撃的になったり、予想外の行動を取ったりする可能性があるんです。
適切な音量の目安は、次のようなものです。
- ささやき声程度(30?40デシベル)
- 普通の会話程度(50?60デシベル)
- 最大でも掃除機程度(70デシベル)
大丈夫です。
アライグマの聴覚は人間の1.5倍も敏感なので、私たちには小さく感じる音でも、十分に効果があるんです。
音量を適切に保つことで、アライグマを効果的に撃退しつつ、近隣への迷惑も最小限に抑えることができます。
「ご近所トラブルは避けたいですもんね」そんな気持ちで、思いやりを持って対策を行うことが大切なんです。
アライグマ撃退に効果的な音源と設置方法

突発的な大音量vs連続音!どちらが効果的?
アライグマ撃退には、突発的な大音量の方が連続音よりも効果的です。「えっ?ずっと音を鳴らし続ける方がいいんじゃないの?」と思った方もいるかもしれませんね。
でも、実はそうではないんです。
アライグマは賢い動物なので、同じ音が続くとすぐに慣れてしまうんです。
突発的な大音量が効果的な理由は、アライグマの警戒心を強く刺激するからです。
例えば、静かな夜道を歩いているときに、突然「ガシャーン!」という音がしたら、びっくりしますよね。
アライグマも同じなんです。
効果的な音の特徴をまとめてみましょう。
- 不規則なタイミングで鳴る
- 短時間で終わる
- 予測できない音の変化がある
「ピー!」「ガタン!」「シャー!」といった音が、不規則に鳴り響く状況を想像してみてください。
一方、連続音にはどんな問題があるのでしょうか。
- アライグマが音に慣れてしまう
- 周囲の環境にも悪影響を与える可能性がある
- 効果が薄れるのに気づきにくい
しかし、実際はその逆なんです。
連続音を使い続けると、アライグマがその音を「普通の環境音」として認識してしまい、警戒しなくなってしまうんです。
結局のところ、アライグマ撃退には「ドキッ」とさせる音が効果的、ということですね。
突発的な大音量を上手に活用して、アライグマを寄せ付けない環境を作りましょう。
高音vs低音!アライグマはどちらに敏感に反応?
アライグマは高音により敏感に反応します。低音よりも高音の方が、アライグマを効果的に追い払えるんです。
「えー、低い音の方が怖そうじゃない?」と思った方もいるかもしれませんね。
でも、アライグマの耳は人間とは違うんです。
彼らは高い音にとても敏感なんです。
なぜアライグマは高音に敏感なのでしょうか?
理由は主に3つあります。
- 聴覚が高周波数に適応している
- 高音が危険信号として認識されやすい
- 自然界での捕食者の鳴き声に似ている
これは人間の可聴域をはるかに超えています。
「ピーーッ」という、私たちにはかすかにしか聞こえない音でも、アライグマにはとてもうるさく感じるんです。
高音と低音の効果を比較してみましょう。
- 高音:警戒心を強く刺激し、素早い反応を引き出す
- 低音:比較的穏やかな反応で、慣れやすい
多くの人は高い音の方が不快に感じるはずです。
アライグマも同じような感覚を持っているんです。
ただし、注意点もあります。
高音を使う際は、近隣への配慮が必要です。
人間にも聞こえる高音を長時間使用すると、ご近所トラブルの原因になりかねません。
「隣の家のアライグマ対策がうるさくて眠れない!」なんて事態は避けたいですよね。
高音を活用する際のポイントをまとめてみましょう。
- 短時間の使用にとどめる
- 夜間の使用は控えめにする
- 可能な限り人間の可聴域外の音を選ぶ
高音の力を上手に活用して、アライグマとの平和的な共存を目指しましょう。
音源の設置場所は「侵入経路」に注目!効果倍増
アライグマ撃退用の音源は、侵入経路に設置するのが最も効果的です。的確な場所に音源を置くことで、効果が倍増するんです。
「どこに置けばいいの?」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
実は、アライグマの行動パターンを知れば、最適な設置場所が見えてくるんです。
アライグマの侵入経路として注目すべき場所を見てみましょう。
- 庭の入り口や低いフェンス周辺
- 木の近く(特に家に近い木)
- 屋根や壁の破損箇所
- 排水管や換気口の周辺
- ゴミ置き場の近く
ここに音源を設置すれば、侵入を効果的に防ぐことができます。
音源の理想的な設置高さは、地上から1?2メートルくらい。
アライグマの目線の高さに合わせるのがポイントです。
「えっ、そんな高さまで登れるの?」と驚く方もいるかもしれませんが、アライグマは驚くほど運動能力が高いんです。
効果的な設置方法をいくつか紹介しましょう。
- フェンスの上に音源を取り付ける
- 侵入されやすい木の幹に巻き付ける
- 軒下に設置する
- ゴミ箱の蓋に取り付ける
その場合は、家の周りを重点的に守るのがおすすめです。
玄関や窓の近くに音源を設置すれば、室内への侵入も防げます。
ただし、設置する際は近隣への配慮も忘れずに。
「隣の家の音がうるさくて眠れない!」なんて苦情が来ないよう、音量や向きには十分注意しましょう。
音源の設置場所を工夫するだけで、アライグマ対策の効果は大きく変わります。
アライグマの行動をよく観察して、最適な場所を見つけてくださいね。
複数の音源を使う「最適な配置」でさらに効果UP
複数の音源を使えば、アライグマ撃退の効果がさらにアップします。でも、ただ増やせばいいというわけではありません。
最適な配置が重要なんです。
「たくさん置けば置くほど効果があるの?」そう思った方もいるかもしれませんね。
実は、数よりも配置の仕方が大切なんです。
効果的な配置方法をいくつか紹介しましょう。
- 三角形の頂点に配置する
- 敷地の外周を囲むように配置する
- 侵入されやすい場所を重点的に守る
- 死角をなくすように配置する
これで庭全体をカバーできます。
「まるで見えない壁を作るみたい!」そんなイメージです。
複数の音源を使う際のポイントをまとめてみましょう。
- 音源同士の間隔を均等に保つ
- 異なる種類の音を組み合わせる
- 音が重なり合うよう調整する
- 時間差で作動させる
「ピー」という高周波音、「ガタン」という金属音、「シャー」という空気音、など様々な音を使うと効果的です。
でも、注意点もあります。
音源を増やしすぎると、かえって効果が薄れる可能性があるんです。
「音だらけじゃアライグマも慣れちゃうよね」そう思う方、正解です。
3?5個程度が適量だと言われています。
また、近隣への配慮も忘れずに。
夜間は音量を下げたり、人家から離れた場所に集中して配置したりするなど、工夫が必要です。
複数の音源を賢く使えば、アライグマ対策の効果は飛躍的に高まります。
自分の庭や家の状況に合わせて、最適な配置を見つけてくださいね。
昼と夜で変わる!時間帯別の音源使用法
アライグマ対策の音源は、昼と夜で使い方を変えると効果的です。時間帯に合わせて上手に使えば、アライグマ撃退の効果がグンとアップしますよ。
「え?昼と夜で違うの?」と思った方も多いかもしれませんね。
実は、アライグマの活動時間に合わせて音源を使うのがポイントなんです。
まず、アライグマの活動時間を確認しましょう。
- 昼間:ほとんど活動しない(睡眠中)
- 夕方?夜明け:最も活発に活動する
【夜間の使用法】
- 日没直後から音源をオンに
- 間欠的に音を鳴らす(15分おきなど)
- 深夜0時?早朝5時は音量を下げる
- 夜明け前に音量を少し上げる
ずっと鳴らしていると、アライグマが音に慣れてしまうんです。
また、ご近所トラブルの原因にもなりかねません。
【昼間の使用法】
- 基本的に音源はオフに
- 時々短時間だけオンにする(不定期に)
- 庭仕事など人の活動で代用
ただし、たまに音を鳴らすことで、アライグマの警戒心を維持させる効果があります。
時間帯別の使用法のポイントをまとめてみましょう。
- 夕方:活動開始に備えて音源準備
- 夜間:効果的に音源を使用(ただし近隣に配慮)
- 早朝:活動終了に向けて音量調整
- 昼間:必要最小限の使用
最近は時間設定ができる自動音源装置も販売されています。
これを使えば、効率的にアライグマ対策ができますよ。
時間帯に合わせた音源の使用は、アライグマ対策の要です。
アライグマの生態をよく理解し、適切なタイミングで音を鳴らすことで、より効果的な対策が可能になります。
昼と夜の使い分けをマスターして、アライグマとの知恵比べに勝ちましょう。
意外と簡単!自作できるアライグマ撃退音源5選

ペットボトルの「水面反射音」で寄せ付けない工夫
ペットボトルを使った水面反射音は、アライグマを効果的に寄せ付けない簡単な方法です。「えっ、ペットボトルでアライグマが撃退できるの?」と思った方も多いのではないでしょうか。
実は、この方法はとても効果的なんです。
ペットボトルの水面反射音が効果的な理由は、以下の3つです。
- 不規則な音を生み出す
- 光の反射も同時に発生する
- 低コストで簡単に設置できる
まず、透明なペットボトルを用意します。
中に水を半分ほど入れ、小さな石や貝殻を数個入れます。
そして、庭や畑の木の枝などに吊るすだけ。
風が吹くとペットボトルが揺れ、中の水が動きます。
すると、「チャポチャポ」という不規則な音が発生するんです。
この音がアライグマを警戒させるんです。
さらに、日光や月明かりが水面に反射して、きらきらとした光を放ちます。
この予測不可能な光の動きも、アライグマを不安にさせる効果があります。
「でも、そんな簡単な方法で本当に効果あるの?」と疑問に思う方もいるでしょう。
実は、アライグマは予測できない刺激に対してとても敏感なんです。
この不規則な音と光の組み合わせが、彼らの警戒心を強く刺激するんです。
ペットボトルの水面反射音を使う際のポイントは、以下の通りです。
- 複数設置して効果を高める
- 定期的に中身を変える(石や貝殻を入れ替える)
- 日当たりの良い場所に設置して光の効果を最大化
ぜひ、アライグマ対策の一つとして試してみてくださいね。
風鈴の「不規則な音」がアライグマを警戒させる
風鈴の不規則な音は、アライグマを効果的に警戒させる優れた方法です。「え?普通の風鈴でいいの?」と思った方もいるでしょう。
はい、その通りなんです。
実は、風鈴の音色がアライグマ対策にぴったりなんです。
風鈴がアライグマ撃退に効果的な理由は、主に3つあります。
- 予測不可能な音を発生させる
- 高周波の音を含んでいる
- 人の存在を感じさせる
「チリンチリン」「カランカラン」と、不規則なタイミングで鳴るんです。
この予測できない音がアライグマを警戒させるんです。
さらに、風鈴の音には高周波成分が含まれています。
アライグマは高周波に敏感なので、この音を特に不快に感じるんです。
また、風鈴は人家の軒先によく飾られるものです。
その音を聞くと、アライグマは「ここには人がいるかも」と感じて、近づくのをためらうんです。
風鈴を使ったアライグマ対策のポイントは以下の通りです。
- 複数の風鈴を設置して効果を高める
- 異なる素材の風鈴を組み合わせる(金属製、ガラス製など)
- アライグマの侵入経路付近に設置する
確かに、夜中ずっと鳴らし続けるのは問題かもしれません。
その場合は、夕方から夜の早い時間帯だけ設置するなど、使用時間を工夫しましょう。
風鈴は見た目も楽しめて一石二鳥。
アライグマ対策をしながら、涼しげな雰囲気も楽しめちゃうんです。
素敵な音色で、アライグマを優しく撃退してみませんか?
アルミホイルの「カサカサ音」で侵入を阻止
アルミホイルのカサカサ音は、アライグマの侵入を効果的に阻止する意外な方法です。「えっ、キッチンにあるアレで?」と驚く方も多いかもしれません。
でも、このありふれた道具が実はアライグマ対策の強い味方なんです。
アルミホイルがアライグマ撃退に効果的な理由は、主に3つあります。
- 予想外の音を発生させる
- 光を反射して視覚的な刺激を与える
- 触った感触がアライグマにとって不快
この予想外の音に、アライグマはビックリしてしまうんです。
また、月明かりや街灯の光を反射して、キラキラと光ります。
この不自然な光の動きも、アライグマを警戒させる効果があるんです。
さらに、アルミホイルの表面はザラザラしています。
アライグマの繊細な足裏にとっては、とても歩きにくい不快な感触なんです。
アルミホイルを使ったアライグマ対策のポイントは以下の通りです。
- アライグマの侵入経路に重点的に設置する
- 雨に濡れても大丈夫なように工夫する(例:ビニールで覆う)
- 定期的に位置を変える(慣れを防ぐため)
確かに、庭中アルミホイルだらけではちょっと…。
そんな時は、夜だけ設置するとか、植木鉢の周りだけに使うなど、工夫次第で目立たなくできますよ。
アルミホイルは安価で手に入りやすく、誰でも簡単に試せる方法です。
ぜひ、アライグマ対策の新たな武器として、アルミホイルの力を借りてみてくださいね。
空き缶コインの「チリンチリン音」で驚かせる効果
空き缶にコインを入れて作る「チリンチリン音」は、アライグマを効果的に驚かせる手作り音源です。「そんな簡単なもので本当に効果があるの?」と疑問に思う方もいるでしょう。
でも、これがなかなかの威力を発揮するんです。
空き缶コインがアライグマ撃退に効果的な理由は、以下の3つです。
- 予測不可能な音を発生させる
- 金属音がアライグマを警戒させる
- 動きと音の組み合わせで効果アップ
空き缶を洗って乾かし、中に5?10枚程度の硬貨を入れます。
缶の口をテープでしっかり塞いで、紐を取り付けて完成です。
この手作り音源を庭の木や柵に吊るすと、風で揺れるたびに「チリンチリン」「カランカラン」という音が鳴ります。
この不規則な音に、アライグマは警戒心を抱くんです。
特に金属音は、自然界にはあまりない音なので、アライグマにとっては不安を感じる音なんです。
さらに、揺れる動きと音が組み合わさることで、より強い効果を発揮します。
空き缶コインを使う際のポイントは以下の通りです。
- 複数設置して効果を高める
- 風通しの良い場所に吊るす
- コインの枚数を変えて音の変化をつける
- 定期的に位置を変える(慣れを防ぐため)
その場合は、夜間は取り外すなど、使用時間を工夫しましょう。
また、缶の中にスポンジを少し入れると、音が柔らかくなりますよ。
この方法は、材料費がほとんどかからず、誰でも簡単に作れるのが魅力です。
アライグマ対策に、ちょっとしたリサイクル術を取り入れてみませんか?
簡易スプリンクラーの「水音」でアライグマを撃退
簡易スプリンクラーの水音は、アライグマを効果的に撃退する意外な方法です。「え?水をまくだけでアライグマが逃げるの?」と思った方も多いでしょう。
実は、この方法がかなり効果的なんです。
簡易スプリンクラーがアライグマ撃退に効果的な理由は、主に3つあります。
- 突発的な音と動きでアライグマを驚かせる
- 水しぶきが不快な刺激となる
- 湿った地面を嫌うアライグマの習性を利用
ペットボトルの側面に小さな穴をたくさん開け、ホースをつないで水を流すだけ。
庭のポールや木の枝に取り付ければ完成です。
この簡易スプリンクラーは、水が出る時に「シャー」という音を立てます。
さらに、突然の水しぶきがアライグマを驚かせるんです。
「うわっ、何これ!」とアライグマも思わず逃げ出しちゃうかも。
また、アライグマは湿った地面を歩くのを好みません。
水をまいた後の湿った地面は、彼らにとって居心地の悪い環境なんです。
簡易スプリンクラーを使う際のポイントは以下の通りです。
- 人感センサーと組み合わせて使用する
- アライグマの侵入経路に設置する
- 夜間のみ作動させる(水の無駄遣い防止)
- 定期的に位置を変える(慣れを防ぐため)
確かにその通りです。
だからこそ、人感センサーと組み合わせて使うのがおすすめ。
アライグマが近づいた時だけ作動させれば、無駄な水の使用を防げます。
この方法は、アライグマ対策をしながら庭の水やりもできる一石二鳥の方法。
エコで効果的なアライグマ撃退法として、ぜひ試してみてくださいね。