アライグマが嫌がる音とは?【突発的な大音量が効果的】音による3つの撃退方法と近隣への配慮点

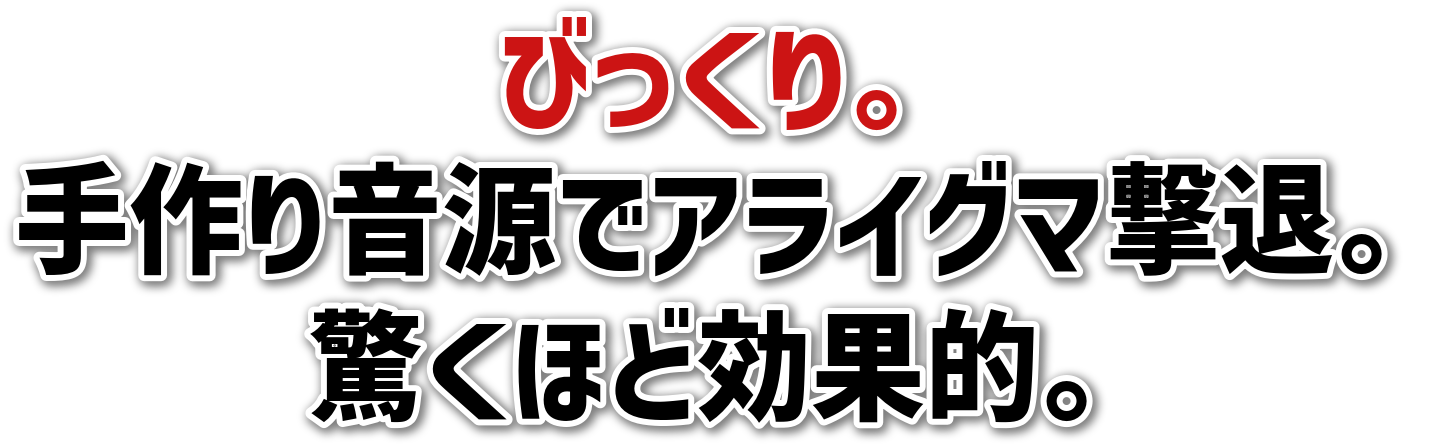
【この記事に書かれてあること】
アライグマの被害に悩まされていませんか?- 突発的な大音量がアライグマ撃退に最も効果的
- 高周波音は20〜25kHzの範囲が最適
- 音の持続時間は5〜10秒が効果的、長時間は逆効果
- 音量は70〜90デシベル程度が目安
- 設置場所は屋根裏や庭の入り口が効果的
- DIYで簡単に作れる音源で効果的に対策可能
実は、音を使った対策が効果的なんです。
でも、ただやみくもに音を出せばいいというわけではありません。
アライグマが本当に嫌がる音には、ちゃんとした特徴があるんです。
この記事では、アライグマ撃退に効果的な音の特徴や、音源の選び方、設置方法までを詳しく解説します。
さらに、驚くほど簡単なDIY音源も5つ紹介!
これを読めば、あなたも音のプロフェッショナルになれちゃいます。
さあ、アライグマとの知恵比べ、始めましょう!
【もくじ】
アライグマが嫌がる音の特徴とは?効果的な対策を解説

突発的な大音量がアライグマを驚かせる!最適な音とは
アライグマを効果的に追い払うには、突発的な大音量の音が最適です。特に金属音や高周波音に敏感に反応します。
「ガシャーン!」「キーン!」といった急な音は、アライグマの神経を逆なでするんです。
彼らの繊細な耳には、こういった音が不快に感じられるわけです。
でも、なぜ突発的な音が効果的なのでしょうか?
それは、アライグマの警戒心を刺激するからなんです。
「え?何の音?危険かも!」とアライグマの頭の中では警報が鳴り響きます。
効果的な音の例をいくつか挙げてみましょう。
- 金属板を叩く音
- 笛の鋭い音
- 拍子木をたたく音
- 風鈴の音
- 犬の鳴き声
「いつ音がするかわからない…ここは危険だ!」とアライグマは考えるわけです。
ただし、注意点もあります。
同じ音を繰り返し使うと、アライグマが慣れてしまう可能性があります。
そのため、音の種類や鳴らすタイミングを変えることがポイントです。
これにより、アライグマを常に緊張させ、効果を持続させることができるんです。
突発的な大音量を上手に活用すれば、アライグマ対策はグッと楽になりますよ。
アライグマ撃退に効く「高周波音」の周波数帯は20〜25kHz
アライグマ撃退に最も効果的な高周波音の周波数帯は20〜25kHzです。この音域は人間には聞こえにくいですが、アライグマには不快に感じられるんです。
「えっ?人間に聞こえない音でアライグマを追い払えるの?」そう思った方もいるでしょう。
実はアライグマの聴覚は人間よりもずっと優れているんです。
彼らは私たちが聞き取れない高い音まで聞こえてしまうんです。
この高周波音の効果は絶大です。
アライグマにとっては「ギーーーー!」という不快な音に聞こえるんです。
まるで、私たちが黒板を爪で引っかいたような音を聞くような感覚でしょうか。
高周波音を使うメリットは3つあります。
- 人間には聞こえにくいので、近隣への迷惑を最小限に抑えられる
- アライグマに対して24時間効果を発揮できる
- 電気で作り出せるので、メンテナンスが簡単
ペットや他の野生動物にも影響を与える可能性があるからです。
「うちの犬が落ち着かなくなった…」なんてことにならないよう、適切な音量調整が大切です。
高周波音発生装置を設置する際のポイントは、アライグマの侵入経路を予想して配置することです。
屋根裏や庭の入り口付近が効果的です。
「ここは危険だ!」とアライグマに思わせることで、寄せ付けない環境を作り出せるんです。
高周波音を上手に活用すれば、静かでストレスフリーなアライグマ対策が可能になりますよ。
音の持続時間は「5〜10秒」が効果的!長時間は逆効果に
アライグマを追い払うのに最適な音の持続時間は5〜10秒程度です。短い音を断続的に鳴らすのが効果的なんです。
「えっ?もっと長く鳴らした方がいいんじゃないの?」と思う方もいるかもしれません。
でも、それが実は大きな間違いなんです。
アライグマは意外と賢い動物で、長時間同じ音が鳴り続けると、「あ、これは危険じゃない音だな」と慣れてしまうんです。
音の鳴らし方のコツは、不規則性にあります。
例えば、こんな感じです。
- 5秒鳴らす → 30秒休む → 7秒鳴らす → 1分休む
- 3秒鳴らす → 20秒休む → 10秒鳴らす → 45秒休む
「いつ音がするかわからない…怖いよ?」とアライグマの頭の中はパニック状態になっちゃうんです。
ただし、注意点もあります。
夜間は近隣への配慮が必要です。
深夜に頻繁に音を鳴らすと、ご近所トラブルの原因になりかねません。
そこで、夜間は音の間隔を長めにしたり、音量を下げたりする工夫が大切です。
音の持続時間と間隔を上手にコントロールすることで、アライグマ対策の効果を最大限に引き出せます。
まるで、ゲリラ豪雨のように予測不可能な音の攻撃で、アライグマを撃退しちゃいましょう!
音量調整は70〜90デシベルが目安!人の会話程度から
アライグマを追い払うのに適した音量は、70〜90デシベル程度です。これは人間の会話程度からやかましいと感じる程度の音量なんです。
「えっ?そんなに大きな音じゃないの?」と思う方もいるかもしれません。
でも、アライグマの耳はとても敏感なんです。
人間にとってはそれほど大きくない音でも、彼らにとっては十分に不快な音量なんです。
音量の目安を具体的に説明すると、こんな感じです。
- 70デシベル:騒がしい事務所程度
- 80デシベル:地下鉄の車内程度
- 90デシベル:騒々しい工場の中程度
ただし、音量調整には注意が必要です。
季節や時間帯によって適切な音量が変わることもあるんです。
例えば、夏は窓を開けている家が多いので、音量を少し下げるのがマナーです。
また、夜間はさらに音量を下げる配慮が必要になります。
音量調整のコツは、徐々に上げていくことです。
最初は70デシベル程度から始めて、効果がなければ少しずつ上げていきます。
「ちょっとずつ音が大きくなってる…怖いよ?」とアライグマの警戒心を徐々に高めていくわけです。
適切な音量調整は、効果的なアライグマ対策の鍵となります。
まるで、音楽のボリュームを調整するように、アライグマ撃退の音量もうまく調整していきましょう。
そうすれば、アライグマも近隣住民も、みんなが快適に過ごせる環境が作れるはずです。
近隣トラブル回避のため「夜間は低音量」で設定を
アライグマ対策の音を使う際、近隣トラブルを避けるには夜間の音量設定に気をつけましょう。低音量に設定することがポイントです。
「でも、夜こそアライグマが活動的になるんじゃないの?」そう思う方もいるでしょう。
確かにその通りです。
でも、人間社会では静かな夜を保つことも大切なんです。
夜間の音量設定のコツは、次の3点です。
- 音量を昼間の半分程度に下げる
- 高周波音を主に使用する
- 音を鳴らす間隔を長めに設定する
これくらいの音量なら、隣の家に届くことはまずありません。
高周波音を使うのも効果的です。
人間には聞こえにくい20〜25kHzの音域を使えば、アライグマへの効果は維持しつつ、近隣への影響を最小限に抑えられます。
「ギーーー!」とアライグマには不快に聞こえる音も、人間にはほとんど気づかれないんです。
音を鳴らす間隔も重要です。
昼間は5分おきだったものを、夜は15分おきにするなど、間隔を長めに設定します。
こうすることで、断続的な音がご近所の睡眠を妨げる心配も減らせます。
ただし、事前に近隣住民に説明し、理解を得ることが大切です。
「実はうちではアライグマ対策をしているんです」と正直に伝え、協力を仰ぐのがベストです。
みんなで協力すれば、より効果的な対策ができるはずです。
夜間の低音量設定は、アライグマ対策と近隣との良好な関係の両立を可能にします。
まるで、真夜中のこっそり作戦のように、静かにしつつ効果的にアライグマを撃退しましょう。
そうすれば、人もアライグマも、そして近隣住民も、みんなが平和に過ごせる環境が作れるはずです。
音源の選び方と設置で効果アップ!具体的な方法を紹介

超音波発生装置vs風鈴!音源の種類による効果の違い
アライグマ対策には、超音波発生装置と風鈴どちらも効果的です。でも、それぞれに特徴があるんです。
まず、超音波発生装置。
これは人間には聞こえない高い音を出す機械です。
「ギーーー!」とアライグマには不快に聞こえるんですね。
近所迷惑にならないのがうれしいところ。
でも、お値段はちょっと高めかも。
一方、風鈴はどうでしょう?
こちらは自然な音で、アライグマを驚かせます。
「チリンチリン」という音が不規則に鳴るので、アライグマは落ち着かなくなるんです。
お手軽で安価なのが魅力ですね。
では、どっちがいいの?
それぞれの特徴をまとめてみましょう。
- 超音波発生装置
- 人間には聞こえない
- 常時作動可能
- 電気代がかかる
- 高価
- 風鈴
- 自然な音
- 風が吹かないと鳴らない
- 電気代不要
- 安価
近所との関係が心配なら超音波発生装置、お財布と相談なら風鈴がおすすめです。
でも、ここで裏技をご紹介!
実は、両方使うのが最強なんです。
「超音波で常時警戒、風鈴で追い打ち」という作戦。
これなら、アライグマも「もうこの家はヤバイ!」と思っちゃうはず。
音源選びは、まるでアライグマとのかくれんぼ。
あの手この手で、しっかり対策していきましょう!
屋根裏vs庭の入り口!音源の効果的な設置場所を比較
アライグマ対策の音源、どこに置けばいいの?答えは、屋根裏と庭の入り口の両方です。
でも、それぞれに特徴があるんですよ。
まず、屋根裏。
ここはアライグマのお気に入り場所なんです。
「ここなら安全」と思っているアライグマを、音でビックリさせられます。
でも、注意点も。
屋根裏は密閉空間なので、音が反響して大きくなることも。
近所迷惑にならないよう、音量調整が大切です。
一方、庭の入り口はどうでしょう?
ここは、アライグマが侵入してくる最初の関門。
「ピー!ガチャン!」という音で、入ってくる前から追い払えるんです。
屋外なので、音量の心配も少なめ。
では、どっちがいいの?
それぞれの特徴をまとめてみましょう。
- 屋根裏
- アライグマの好みの場所
- 音が反響しやすい
- 雨風から音源を守れる
- 設置が少し面倒
- 庭の入り口
- 侵入を未然に防げる
- 音が拡散しやすい
- 雨風対策が必要
- 設置が比較的簡単
でも、実は両方に設置するのが最強なんです。
「入り口で警戒、屋根裏で追い打ち」という作戦。
これなら、アライグマも「この家は危険だ!」と思うはず。
設置場所選びは、まるでアライグマとのかけひき。
あなたの家の状況に合わせて、賢く配置していきましょう。
そうすれば、アライグマも「もうこの家には近づかない!」となっちゃうかも。
がんばって対策、応援してます!
単一音源vs複数音源!効果的な配置方法の違いを解説
アライグマ対策の音源、1つだけ?それとも複数?
答えは、複数がおすすめです。
でも、それぞれに特徴があるんですよ。
まず、単一音源。
これは簡単で分かりやすい。
例えば、庭の真ん中に1つだけ設置する感じ。
「ピー!ガチャン!」と一点集中で音を出します。
設置も簡単だし、費用も抑えられます。
でも、音が届かない場所ができちゃうかも。
一方、複数音源はどうでしょう?
これは、家の周りにバランスよく配置する方法。
「あっちでピー!こっちでガチャン!」と、あちこちから音が聞こえるんです。
アライグマは「どこからでも音がする!怖い!」と思っちゃいます。
では、どっちがいいの?
それぞれの特徴をまとめてみましょう。
- 単一音源
- 設置が簡単
- 費用が抑えられる
- 音が届かない場所ができる
- アライグマが慣れやすい
- 複数音源
- 設置に手間がかかる
- 費用が高くなる
- 音が広範囲に届く
- アライグマが慣れにくい
でも、実は複数音源を徐々に増やしていくのが最強なんです。
最初は1つから始めて、効果を見ながら増やしていく。
「あれ?また新しい音が増えた!」とアライグマを混乱させる作戦です。
音源の配置は、まるでアライグマとのチェス。
あなたの家の状況に合わせて、賢く配置していきましょう。
そうすれば、アライグマも「もうこの家には近づけない!」となっちゃうかも。
みんなで知恵を絞って、アライグマ対策、がんばりましょう!
センサー式vs常時作動!状況に応じた音源の選び方
アライグマ対策の音源、センサー式?それとも常時作動?
答えは、両方とも良いんです。
でも、それぞれに特徴があるんですよ。
まず、センサー式。
これは動きを感知したときだけ音が鳴る仕組み。
「ピッ!ガチャン!」とアライグマが近づいたときだけ音が出ます。
電気代が節約できるし、近所迷惑も少ない。
でも、センサーの反応が遅れることも。
一方、常時作動はどうでしょう?
これは、文字通り常に音を出し続ける方法。
「ピー!ガチャン!」と24時間休みなく音が鳴ります。
アライグマを寄せ付けない効果は抜群。
でも、電気代がかかるし、音に慣れられちゃうかも。
では、どっちがいいの?
それぞれの特徴をまとめてみましょう。
- センサー式
- 電気代が節約できる
- 近所迷惑が少ない
- センサーの反応が遅れることも
- バッテリー切れに注意
- 常時作動
- 電気代がかかる
- 近所迷惑の可能性あり
- 常に警戒態勢
- 音に慣れられる可能性
でも、実は両方を組み合わせるのが最強なんです。
例えば、低音量の常時作動と高音量のセンサー式を併用する。
「いつも音がするけど、近づくともっと大きな音が!」とアライグマを混乱させる作戦です。
音源の選び方は、まるでアライグマとの頭脳戦。
あなたの家の状況に合わせて、賢く選んでいきましょう。
そうすれば、アライグマも「この家は用心深いぞ!」と思うはず。
みんなで知恵を絞って、アライグマ対策、がんばりましょう!
大音量の音楽を終夜流すのはやっちゃダメ!逆効果の理由
大音量の音楽を一晩中流せば、アライグマは逃げ出す?実はこれ、大きな間違いなんです。
逆効果になっちゃうんですよ。
なぜダメなのか、理由を見ていきましょう。
まず、アライグマは賢い動物。
同じ音が続くと、「あ、これは危険じゃない音だな」と慣れてしまいます。
終夜流す音楽なんて、まさにうってつけ。
「BGMつきの食事か。ごちそうさま!」なんて、喜ばれちゃうかも。
次に、近所迷惑の問題。
「うるさくて眠れない!」と苦情が来るのは目に見えてます。
アライグマを追い払うどころか、ご近所さんまで追い払っちゃうかも。
さらに、他の動物への影響も。
鳥や虫たちの生態系を乱す可能性も。
「自然の音が聞こえない…」なんて、悲しい状況になるかもしれません。
では、どうすればいいの?
ポイントは3つ。
- 突発的な音を使う。
不規則に鳴る音の方が効果的。 - 音量は控えめに。
70?90デシベル程度が目安。 - 音源を変える。
同じ音に慣れさせない工夫を。
音源も風鈴やラジオなど、日によって変えてみる。
そんな工夫が効果的なんです。
大音量の音楽を流すのは、まるで空振りの大ホームラン。
派手だけど、効果はゼロ。
それどころか、マイナスになっちゃう。
代わりに、小さな音でも効果的な方法を選びましょう。
アライグマ対策は、力任せじゃなく知恵比べ。
賢く対策して、アライグマに「この家はやばい!」と思わせちゃいましょう。
驚くほど簡単!DIYで作れるアライグマ撃退音源5選

アルミホイルの風鈴で不規則な音を演出!作り方と効果
アルミホイルで作る風鈴は、アライグマを驚かせる不規則な音を簡単に作れる優れものです。作り方はとっても簡単!
まず、アルミホイルを30センチ四方くらいに切ります。
それを丸めて、細長い筒状にしましょう。
次に、その筒を5センチくらいの長さに切り分けます。
「ちょきちょき」とハサミを入れるだけでOK。
これらの小さな筒を、ビニール紐で吊るすんです。
長さの異なる紐を使うと、より不規則な音が出せますよ。
「うーん、何か怪しい音がする…」とアライグマも警戒心マックスに。
効果はバツグン!
風が吹くたびに「カラカラ」「シャカシャカ」と不思議な音が鳴ります。
アライグマにとっては、この予測不可能な音がとても不快なんです。
設置場所は、庭の入り口や木の枝、軒下がおすすめ。
アライグマが通りそうな場所を狙って吊るしましょう。
このDIY風鈴の魅力は3つ。
- 材料費がほぼゼロ
- 誰でも簡単に作れる
- 見た目もおしゃれ
その場合は一時的に取り外すなど、近所への配慮も忘れずに。
アルミホイルの風鈴で、アライグマに「ここは居心地が悪いぞ」と思わせちゃいましょう。
簡単、お手軽、そして効果的。
まさに一石三鳥の対策方法です!
ペットボトルの手作りガラガラ!設置場所のコツを紹介
ペットボトルで作るガラガラは、アライグマを驚かせる効果抜群の音源です。しかも、作り方はとっても簡単!
まず、空のペットボトルを用意します。
500ミリリットルサイズがちょうどいいでしょう。
中に小石や硬貨を入れます。
「ジャラジャラ」という音が出れば成功です。
蓋をしっかり閉めたら、紐やワイヤーでペットボトルを吊るします。
これで完成!
簡単すぎて拍子抜けしちゃいますね。
さて、このガラガラ、どこに設置するのがベストなのでしょうか?
コツは3つあります。
- アライグマの通り道に設置する
- 風で揺れやすい場所を選ぶ
- 複数個所に分散して設置する
風で揺れると「ガラガラ」という不規則な音が鳴り、アライグマは「なんだ?なんだ?」と落ち着かなくなります。
複数設置すると効果アップ!
「あっちでもこっちでも変な音がする…」とアライグマの頭の中は大パニック。
ただし、注意点も。
強風の日は音が大きくなりすぎる可能性があります。
その時は一時的に取り外すなど、近所への配慮も忘れずに。
このDIYガラガラ、実は一石二鳥なんです。
アライグマ対策になるだけでなく、リサイクルにもなっちゃう。
環境にも優しい対策方法、というわけ。
ペットボトルガラガラで、アライグマに「この庭は危険がいっぱい!」と思わせちゃいましょう。
簡単、効果的、そして環境にも優しい。
まさに理想的な対策方法ですね!
CDを使った光と音のコラボ効果!簡単な取り付け方法
古いCDを使った対策方法は、光と音のダブル効果でアライグマを撃退します。しかも、作り方は驚くほど簡単!
まず、使わなくなったCDを集めましょう。
3?5枚あれば十分です。
次に、丈夫な紐やワイヤーを用意します。
CDの穴に紐を通して、結びます。
これだけで完成です!
取り付け方は、庭の木の枝や軒下、フェンスなどに吊るすだけ。
高さは地面から1?2メートルくらいがおすすめです。
この方法の魅力は、光と音のコラボレーション効果。
風が吹くとCDが揺れて、「カラカラ」という不規則な音が鳴ります。
同時に、CDの表面が光を反射して、キラキラと不思議な光を放ちます。
アライグマにとっては、まるで悪夢のようなシチュエーション。
「うわっ、なんだこの音は!?しかも、目がチカチカする!」と、きっと大混乱に陥るはず。
効果を高めるコツは3つあります。
- 複数のCDを異なる長さの紐で吊るす
- 風通しの良い場所に設置する
- 街灯や月明かりが当たる位置を選ぶ
ただし、強風の日は音が大きくなりすぎたり、反射光が強くなりすぎたりする可能性も。
その場合は一時的に取り外すなど、近所への配慮も忘れずに。
CDを使った対策は、まるで小さなディスコ会場を作るようなもの。
でも、アライグマにとっては恐怖のパーティー会場になっちゃうんです。
古いCDで、アライグマに「この庭はヤバイ!逃げよう!」と思わせちゃいましょう。
リサイクル、効果的、そして見た目もおしゃれ。
一石三鳥の対策方法ですね!
竹筒の風鈴で自然な音を!アライグマを怖がらせるコツ
竹筒で作る風鈴は、自然な音でありながらアライグマを効果的に怖がらせる優れものです。作り方も意外と簡単なんですよ。
まず、太さ3?5センチほどの竹を20?30センチの長さに切ります。
3?5本用意しましょう。
次に、それぞれの竹の一方の端を斜めに切ります。
これで音が出やすくなります。
竹筒の上部に小さな穴を開け、そこに紐を通します。
紐の先に木片やビー玉をつけると、風で揺れやすくなりますよ。
さて、この竹筒風鈴、どう使えばアライグマを効果的に怖がらせられるのでしょうか?
コツは3つあります。
- 異なる長さの竹筒を組み合わせる
- アライグマの侵入経路に設置する
- 夜間も音が鳴るよう、風通しの良い場所を選ぶ
これがアライグマには不気味に聞こえるんです。
「なんだこの音は?自然の音なのに、何か怖い…」とアライグマの頭の中はパニック状態に。
設置場所は、庭の入り口や垣根沿い、軒下などがおすすめ。
アライグマが通りそうな場所を狙って吊るしましょう。
この竹筒風鈴の魅力は、自然素材を使っているところ。
人工的な音よりも、アライグマの警戒心を高めやすいんです。
まるで、森の中で不気味な音に出会ったような感覚を与えられます。
ただし、強風の日は音が大きくなりすぎる可能性も。
その場合は一時的に取り外すなど、近所への配慮も忘れずに。
竹筒風鈴で、アライグマに「この場所は危険がいっぱい!」と思わせちゃいましょう。
自然素材、効果的、そして見た目も和風でおしゃれ。
まさに一石三鳥の対策方法です!
空き缶アラームの作り方!フェンスへの取り付け手順
空き缶を使ったアラームは、アライグマを驚かせる効果抜群の音源です。しかも、作り方は驚くほど簡単!
まず、空き缶を5?10個用意します。
缶の大きさは問いません。
次に、それぞれの缶に小さな穴を2つ開けます。
これは紐を通すためです。
さあ、ここからが楽しいパート。
缶の中に小石や硬貨を入れましょう。
「ジャラジャラ」という音が出ればOKです。
缶ごとに中身を変えると、様々な音が出せますよ。
次に、長い紐を用意します。
この紐に、先ほどの缶を10?20センチ間隔で結びつけていきます。
これで完成です!
さて、このアラーム、どうやってフェンスに取り付ければいいのでしょうか?
手順は簡単です。
- フェンスの上部に沿って紐を張る
- 両端をしっかり固定する
- 缶が自由に揺れるよう、少したるませる
フェンスを乗り越えようとしたアライグマは、「ガシャーン!ジャラジャラ!」という予想外の音にびっくり仰天。
「うわっ、なんだこれは!?」と、すぐに逃げ出すはずです。
効果を高めるコツは2つ。
- フェンス全体に均等に配置する
- 定期的に缶の中身を変えて、音に変化をつける
ただし、強風の日は音が大きくなりすぎる可能性も。
その時は一時的に取り外すなど、近所への配慮も忘れずに。
空き缶アラームで、アライグマに「このフェンスは越えられない!」と思わせちゃいましょう。
リサイクル、効果的、そして見た目もユニーク。
まさに理想的な対策方法ですね!