アライグマを寄せ付けない方法とは?【環境整備が最も重要】効果的な5つの対策と継続のコツを解説

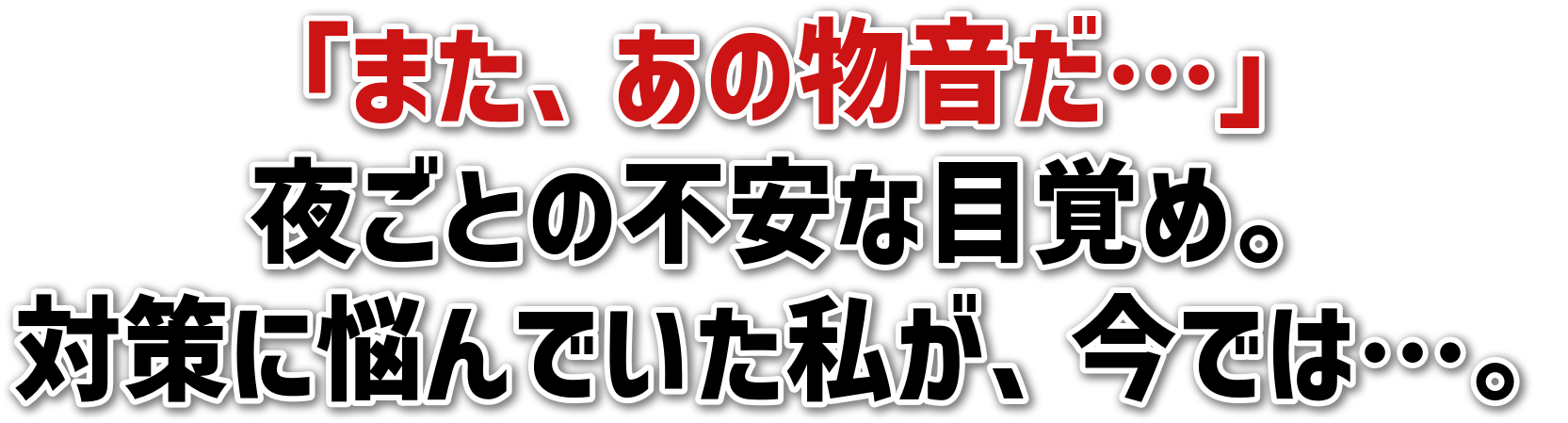
【この記事に書かれてあること】
アライグマの被害に悩まされていませんか?- アライグマによる家屋被害のリスクと対策の重要性
- 環境整備によるアライグマを引き寄せる要因の除去
- 物理的障壁とケミカル対策の比較と効果的な使用法
- 費用対効果を考慮した長期的なアライグマ対策の選び方
- すぐに始められる10の驚きの裏技で即効性のある撃退方法
家屋への侵入や農作物の食害、ゴミ荒らしなど、アライグマによる被害は深刻です。
でも、大丈夫。
この記事では、アライグマを寄せ付けない効果的な方法を紹介します。
環境整備の重要性から、物理的障壁やケミカル対策の比較、さらにはすぐに始められる10の驚きの裏技まで。
費用対効果を考慮した即効性のある撃退方法を徹底解説します。
「もうアライグマには困らない!」そんな安心した生活を取り戻しましょう。
【もくじ】
アライグマを寄せ付けない方法とは?家に侵入されるリスク

アライグマが引き起こす「深刻な被害」の実態!
アライグマによる被害は、想像以上に深刻です。家屋への侵入や農作物の食害だけでなく、衛生面でも大きな問題を引き起こします。
「うわっ、屋根裏から変な音がする!」そんな経験はありませんか?
実はこれ、アライグマが侵入している可能性が高いんです。
アライグマは驚くほど器用で、わずかな隙間から家に入り込んでしまいます。
屋根裏に住み着いたアライグマは、断熱材をボロボロに引き裂いたり、電線をかじったりします。
「えっ、火事になるかも!?」そう、最悪の場合は漏電による火災の危険性もあるんです。
さらに、アライグマの糞尿による被害も深刻です。
強烈な匂いが家中に広がるだけでなく、衛生面でも大問題。
アライグマの糞には危険な寄生虫が含まれていることがあり、人間やペットの健康を脅かす可能性があります。
- 屋根や壁の損傷:修理費用が高額に
- 電線被害:火災のリスクあり
- 糞尿被害:悪臭と健康被害の危険性
- 農作物被害:庭の野菜や果物が食べられてしまう
- ペットへの攻撃:小型のペットが襲われる可能性も
アライグマの被害は見た目以上に深刻なんです。
早めの対策が大切ですよ。
アライグマが好む侵入経路と「隠れ場所」を知ろう
アライグマは意外と賢くて器用なんです。家に侵入する経路や隠れ場所を知っておくことが、効果的な対策の第一歩になります。
まず、アライグマが好む侵入経路をチェックしましょう。
「えっ、こんな小さな隙間から入れるの!?」と驚くかもしれません。
実は、アライグマは体を縮めて直径10センチほどの穴からでも侵入できるんです。
すごい身体能力ですよね。
- 屋根の破損箇所や軒下の隙間
- 換気口や煙突
- 樹木から屋根へのアクセス
- 開いた窓やドア
- デッキの下や基礎の隙間
「まさか、うちにそんな場所があるなんて!」と思うかもしれません。
でも、アライグマにとっては快適な住処になっているんです。
- 屋根裏や天井裏
- 物置や倉庫
- デッキの下
- 大きな木の洞
- 放置された車や機械の中
でも大丈夫。
これらの場所を知っておくことで、効果的な対策が打てるようになります。
まずは家の周りをぐるっと見回って、アライグマが侵入しそうな場所をチェックしてみましょう。
小さな隙間も見逃さないでくださいね。
早めに対策を取ることで、アライグマの被害を防ぐことができますよ。
環境整備の重要性!アライグマを引き寄せる要因とは
アライグマ対策の基本は、実は環境整備なんです。「えっ、そんな簡単なことで効果があるの?」と思うかもしれません。
でも、アライグマを引き寄せる要因を取り除くことが、最も効果的な対策なんです。
アライグマが家の周りにやってくる理由は主に3つ。
食べ物、水、そして隠れ場所です。
これらを上手に管理することで、アライグマを寄せ付けない環境を作ることができます。
まず、食べ物の管理が重要です。
「うちの庭にはそんなものないよ」と思うかもしれません。
でも、アライグマにとっては、人間が気づかないようなものも立派な「ごちそう」なんです。
- 生ゴミの放置をやめる
- ペットのエサは屋外に置かない
- 果物の木の実は早めに収穫する
- 野菜畑にはネットをかける
- コンポストは密閉式のものを使う
アライグマは水浴びが大好き。
庭に水たまりや小さな池があると、アライグマにとっては魅力的な場所になってしまいます。
- 雨どいの修理をして水たまりをなくす
- ペットの水飲み場は夜間は片付ける
- 庭の池には柵をつける
「うちの庭、ちょっと荒れてるかも…」そんな庭は、アライグマの格好の隠れ家になってしまいます。
- 木の枝は地上3メートルまで剪定する
- 薮や茂みは刈り込む
- 物置はきちんと戸締まりする
- 廃材や古タイヤなどは片付ける
でも、これらの環境整備を行うことで、アライグマを寄せ付けない強固な防衛線を築くことができるんです。
地道な作業ですが、長期的に見れば最も効果的な対策なんですよ。
餌となる食べ物の管理「6つのポイント」
アライグマ対策の要は、餌となる食べ物の管理です。「えっ、うちにアライグマの餌なんてないよ」と思うかもしれません。
でも、意外なものがアライグマを引き寄せているかもしれないんです。
まずは、アライグマが大好きな食べ物を知っておきましょう。
果物、野菜、小動物、昆虫、そして人間の食べ残しなど、実に幅広いんです。
「まるで、なんでも屋さんみたい!」そう、アライグマは本当に何でも食べてしまうんです。
では、具体的な管理方法を6つのポイントでご紹介します。
- ゴミ箱の管理:しっかり蓋をして、夜間は屋内に置く
- 果樹の管理:熟した果実はすぐに収穫し、落果は毎日拾う
- 野菜畑の対策:ネットや柵で囲い、夜間は収穫物を屋内に
- ペットフードの管理:屋外での給餌は避け、食べ残しはすぐに片付ける
- バーベキューの後始末:食べ残しや調理くずはしっかり片付ける
- コンポストの管理:蓋付きの容器を使用し、肉や魚の残渣は入れない
でも、これらのポイントを押さえることで、アライグマを引き寄せる要因を大幅に減らすことができるんです。
特に注意したいのが、思わぬところに隠れた「餌場」です。
例えば、鳥の餌台。
「鳥のためにいいことしてるのに…」と思うかもしれません。
でも、こぼれ落ちた種はアライグマの格好のごちそうになってしまうんです。
また、庭の池や小川もご注意を。
「魚なんていないよ」と思っても、そこにいる昆虫やカエルがアライグマを引き寄せてしまうことがあります。
食べ物の管理は少し面倒に感じるかもしれません。
でも、「これで安心して眠れる!」そんな満足感を得られるはずです。
アライグマ対策の基本中の基本、しっかり押さえておきましょう。
アライグマを寄せ付けない「逆効果な対策」に注意!
アライグマ対策、一生懸命やっているのに効果がない…そんな経験はありませんか?実は、よかれと思ってやっていることが、逆効果になっていることがあるんです。
「えっ、そんなバカな!」と思うかもしれません。
でも、本当なんです。
まず、絶対にやってはいけないのが「餌付け」です。
「かわいそうだから」「観察したいから」という理由で餌をあげている人がいますが、これは大問題。
アライグマを引き寄せるだけでなく、人に慣れさせてしまい、より大きな被害を招く可能性があります。
次に注意したいのが、市販の殺鼠剤の使用です。
「アライグマも齧歯類だから効くはず」と思うかもしれません。
でも、実はアライグマへの効果は低く、むしろペットや他の野生動物に悪影響を及ぼす危険性があるんです。
他にも、逆効果になりがちな対策をいくつか紹介します。
- 強すぎる光や音:一時的には効果があっても、すぐに慣れてしまいます
- 不適切な柵:簡単に乗り越えられる高さの柵は、むしろ格好の遊び場に
- 不完全な封鎖:一か所だけ塞いでも、他の侵入口を見つけられてしまいます
- 香りのきつすぎる忌避剤:アライグマの鋭い嗅覚を刺激し、逆に興味を引くことも
大切なのは、アライグマの生態をよく理解し、総合的な対策を取ることです。
環境整備を基本に、物理的な防御と適切な忌避策を組み合わせるのが効果的です。
また、近所の人たちと協力することも重要です。
「隣の家が餌付けしてるんじゃ…」なんて思っても、直接言いづらいですよね。
そんな時は、町内会や自治会で話し合いの場を設けるのもいいかもしれません。
アライグマ対策、一筋縄ではいきません。
でも、正しい知識を持って粘り強く取り組めば、必ず効果が表れます。
逆効果な対策に惑わされず、賢く対処していきましょう。
物理的障壁vsケミカル対策!効果的な防御法を比較

柵vs電気柵!アライグマ対策における「設置の違い」
アライグマ対策には、柵と電気柵の2つの選択肢があります。どちらも効果的ですが、設置方法や特徴に違いがあるんです。
まず、普通の柵から見ていきましょう。
「えっ、普通の柵じゃダメなの?」って思うかもしれませんね。
実は、アライグマは驚くほど器用なんです。
普通の柵を簡単に乗り越えちゃうんですよ。
そこで、アライグマ対策用の柵には特別な工夫が必要になります。
- 高さ:最低でも1.5メートル以上、できれば2メートル以上が理想的
- 材質:金網や硬い素材を使用し、噛み切られにくくする
- 設置方法:地面に30センチほど埋め込み、掘り返されないようにする
- 上部の処理:内側に45度程度傾けるか、滑りやすい素材をつける
「ビリビリって痛そう…」って思いますよね。
でも、大丈夫です。
アライグマに重大な危害を加えるわけではありません。
ただ、不快な刺激を与えて寄せ付けないようにするんです。
電気柵の特徴は以下の通りです。
- 高さ:複数の高さに設置し、すり抜けを防ぐ
- 電圧:アライグマに効果的な程度に設定(一般的に3000〜5000ボルト)
- 設置場所:侵入経路や被害場所の周囲に配置
- メンテナンス:定期的な点検と草刈りが必要
実は、状況によって最適な選択が変わるんです。
広い農地なら電気柵、家庭菜園なら普通の柵が向いているかもしれません。
大切なのは、アライグマの習性を理解し、自分の環境に合った対策を選ぶこと。
「よし、うちはこっちだな!」って感じで、ぴったりの方法を見つけてくださいね。
忌避剤vs超音波装置!持続性と効果の「比較検証」
アライグマ対策の武器として、忌避剤と超音波装置が注目されています。でも、「どっちがいいの?」って悩んじゃいますよね。
それぞれの特徴を比べてみましょう。
まず、忌避剤から見ていきます。
忌避剤は、アライグマが嫌がる匂いや味を利用して寄せ付けないようにする方法です。
- 主な成分:唐辛子成分(カプサイシン)や柑橘系の精油など
- 効果の持続性:雨で流されるまで効果が続く(概ね1〜2週間程度)
- 使用方法:侵入経路や被害場所に直接散布
- メリット:場所を選ばず使える、手軽に再塗布できる
- デメリット:定期的な再塗布が必要、雨に弱い
実は、アライグマは辛いものが苦手なんです。
一方、超音波装置はどうでしょうか。
これは、人間には聞こえない高周波音を出して、アライグマを寄せ付けないようにする装置です。
- 周波数:20〜25キロヘルツ程度(アライグマが嫌がる音域)
- 効果の持続性:電源が続く限り継続的に作動
- 設置場所:庭や侵入経路の近く
- メリット:メンテナンスが少ない、天候に左右されにくい
- デメリット:効果範囲が限られる、慣れによる効果低下の可能性
でも、注意点もあります。
他の動物や虫にも影響を与える可能性があるんです。
さて、「どっちがいいの?」って考えると、実はケースバイケースなんです。
広い庭なら超音波装置、狭い場所なら忌避剤が向いているかもしれません。
大切なのは、自分の環境に合わせて選ぶこと。
「うちの庭ならこっちかな」って感じで、ぴったりの方法を見つけてくださいね。
両方組み合わせるのも良い手かもしれません。
アライグマ対策、あの手この手で攻めていきましょう!
光vs音!アライグマを驚かせる「効果的な使い方」
アライグマ対策に、光と音を使う方法があるんです。「え、そんな簡単なもので効果があるの?」って思うかもしれませんね。
でも、使い方次第でとっても効果的なんですよ。
まず、光による対策から見ていきましょう。
アライグマは夜行性なので、突然の明るい光に驚いてしまうんです。
- 動きセンサー付きライト:アライグマが近づくと自動で点灯
- 点滅するライト:不規則な光の変化でアライグマを混乱させる
- ソーラーライト:電気代がかからず、設置場所を選ばない
- LED投光器:広範囲を明るく照らし、侵入を防ぐ
でも、アライグマにとっては本当に驚くような体験なんです。
次に、音による対策を見てみましょう。
突然の大きな音や、アライグマが苦手な音を利用します。
- 動きセンサー付き音声装置:人の声や犬の鳴き声を再生
- 風鈴やチャイム:不規則な音でアライグマを警戒させる
- ラジオ:人の存在を演出し、アライグマを寄せ付けない
- 超音波装置:人間には聞こえない高周波音でアライグマを追い払う
でも、大丈夫。
人間にはそれほど気にならない程度の音量で十分効果があるんです。
さて、光と音、どちらがいいでしょうか?
実は、両方使うのが一番効果的なんです。
「えっ、そんなにやる必要あるの?」って思うかもしれませんが、アライグマは賢いんです。
一つの対策だけだと、すぐに慣れてしまうんですよ。
例えば、こんな使い方はどうでしょう。
庭の入り口にセンサーライトを設置して、家の近くに風鈴を下げる。
アライグマが近づくと光がパッと付いて、風鈴がチリンチリン。
「うわっ、なんだか怖いぞ」ってアライグマも思わず逃げ出しちゃうかも。
大切なのは、アライグマの習性を理解して、効果的な使い方を工夫すること。
「よし、これでうちの庭は安全だ!」って自信が持てるまで、いろいろ試してみてくださいね。
天然vs化学!アライグマ対策における「忌避剤の選び方」
アライグマ対策の忌避剤、天然のものと化学的なもの、どちらを選べばいいのか悩みますよね。「安全性は?効果は?」いろいろ気になるポイントがあると思います。
それぞれの特徴を見ていきましょう。
まず、天然の忌避剤から。
これは自然由来の成分を使ったものです。
- 主な成分:唐辛子、にんにく、ミント、柑橘類の精油など
- 安全性:人やペットへの影響が少ない
- 効果の持続性:比較的短い(1〜2週間程度)
- 使いやすさ:自作も可能で、手軽に使える
- 環境への影響:小さい
実は、身近なものでも十分な効果があるんです。
一方、化学的な忌避剤はどうでしょうか。
これは科学的に開発された成分を使用しています。
- 主な成分:合成された忌避物質(例:メチルノナノン)
- 安全性:使用方法を守れば問題ないが、注意が必要
- 効果の持続性:比較的長い(1ヶ月以上)
- 使いやすさ:既製品を購入して使用
- 環境への影響:天然のものより大きい可能性がある
確かに、使い方には注意が必要です。
さて、どちらを選べばいいのでしょうか?
実は、状況によって最適な選択が変わるんです。
例えば、小さな子供やペットがいる家庭なら天然のもの、広い農地なら化学的なものが向いているかもしれません。
大切なのは、自分の環境と優先したいポイントを考えること。
「うちは安全性重視だから天然かな」「効果の持続性が欲しいから化学的なものにしよう」といった具合に選んでいくんです。
また、両方を組み合わせて使うのも一つの手です。
例えば、庭の周りには化学的な忌避剤を使い、家の近くには天然のものを使う。
「これで完璧!」って感じで、重層的な防御線を張れますよ。
忌避剤選び、一筋縄ではいきませんが、じっくり考えて最適なものを見つけてくださいね。
アライグマ対策、賢く効果的に進めていきましょう!
費用vs効果!長期的に見た「各対策方法の比較」
アライグマ対策、いろいろな方法がありますよね。でも、「どれが一番お得なの?」って悩んじゃいますよね。
長期的に見て、費用対効果の高い方法を比較してみましょう。
まず、主な対策方法の特徴を見てみます。
- 環境整備:餌や隠れ場所をなくす基本的な対策
- 物理的障壁:柵や電気柵でアライグマの侵入を防ぐ
- 忌避剤:嫌な匂いや味でアライグマを寄せ付けない
- 音光による撃退:センサーライトや音声装置でアライグマを驚かせる
- 罠による捕獲:アライグマを捕まえて排除する
実は、これらを組み合わせるのが一番効果的なんです。
では、それぞれの方法の費用対効果を見ていきましょう。
- 環境整備:初期費用は低く、効果は高い。
継続的な労力が必要だが、長期的に見て最も費用対効果が高い。 - 物理的障壁:初期費用は高いが、長期的な効果が期待できる。
メンテナンス費用は比較的低い。 - 忌避剤:初期費用は中程度で、効果は短期的。
定期的な再塗布が必要で、長期的には費用がかさむ可能性がある。 - 音光による撃退:初期費用は中程度だが、電気代がかかる。
効果は中程度で、アライグマが慣れる可能性もある。 - 罠による捕獲:初期費用は低いが、継続的な労力と処分費用がかかる。
効果は即時的だが、新たなアライグマが入ってくる可能性もある。
実は、これらを組み合わせるのが一番効果的なんです。
例えば、こんな感じはどうでしょう。
- まず環境整備をしっかり行う(餌や隠れ場所をなくす)
- 物理的障壁(柵)を設置して侵入を防ぐ
- 忌避剤を定期的に使用して、寄せ付けない環境を作る
- 音光による撃退を補助的に使用する
でも、これが長期的に見て一番費用対効果が高いんです。
大切なのは、自分の環境に合わせてバランスよく対策を組み合わせること。
「よし、うちはこれでいこう!」って感じで、最適な組み合わせを見つけてくださいね。
アライグマ対策、一度にたくさんのことをするのは大変かもしれません。
でも、少しずつ着実に進めていけば、きっと効果が表れるはずです。
頑張って対策を進めていきましょう!
驚きの裏技!すぐに始められるアライグマ撃退5つの秘策

ペットボトルの水で「反射光トラップ」を仕掛けよう
ペットボトルの水を使った反射光トラップは、アライグマを驚かせる簡単で効果的な方法です。「えっ、ペットボトルでアライグマが追い払えるの?」って思いますよね。
実は、アライグマは急な光の変化に敏感なんです。
ペットボトルの水が作り出す不規則な反射光が、アライグマをビックリさせるんです。
作り方はとっても簡単!
空のペットボトルに水を半分くらい入れて、庭の木や柵に吊るすだけ。
風で揺れると、キラキラっと光が反射して、アライグマを警戒させるんです。
- 必要なもの:空のペットボトル、水、紐
- 設置場所:アライグマが来そうな場所(庭の入り口、木の近くなど)
- 効果的な使い方:複数のボトルを異なる高さに設置する
- メンテナンス:定期的に水を入れ替え、汚れを落とす
大丈夫です。
月明かりや街灯の光でも反射するので、夜でも効果があるんです。
この方法のいいところは、コストがほとんどかからないこと。
「家にあるもので対策できるなんて、すごい!」ってワクワクしませんか?
ただし、注意点もあります。
強風の日は音がうるさくなる可能性があるので、近所迷惑にならないよう気をつけましょう。
ペットボトルの反射光トラップ、簡単で効果的なアライグマ対策。
さっそく試してみてはいかがでしょうか?
アンモニア水の布で「強烈な臭い障壁」を作る方法
アンモニア水を染み込ませた布は、アライグマを寄せ付けない強力な臭い障壁になります。「えっ、アンモニア?臭そう…」って思いましたよね。
その通り、アンモニアの強烈な臭いがアライグマの敏感な鼻をゾクゾクっとさせるんです。
でも、安心してください。
人間にとっては少し臭いだけで、健康に害はありません。
アライグマにとっては「うわっ、ここは危険だ!」というシグナルになるんです。
使い方は簡単です。
以下の手順で準備しましょう。
- 古いタオルや布を用意する
- アンモニア水を水で薄める(1:10くらいの割合)
- 薄めたアンモニア水に布を浸す
- 布を絞って、アライグマが来そうな場所に置く
アライグマが侵入しそうな場所がおすすめです。
例えば、庭の入り口や、家の周りの植え込みの中なんかがいいでしょう。
注意点もあります。
- 定期的な交換:1週間に1回くらいは新しい布に取り替えましょう
- 雨対策:雨に濡れると効果が薄れるので、屋根のある場所に置くのがおすすめ
- ペットへの配慮:犬や猫も嫌がる可能性があるので、ペットの通り道は避けましょう
でも、アンモニアの臭いには慣れてしまう可能性もあるので、他の対策と組み合わせるのがおすすめです。
アンモニア水の布、強力なアライグマ撃退法です。
さっそく試してみてください!
使用済み猫砂で「天敵の気配」を演出しよう
使用済みの猫砂を利用すれば、アライグマに天敵の存在を感じさせる効果があります。「えっ、猫砂?」って驚きましたか?
実は、アライグマは猫を天敵と認識しているんです。
猫の匂いがするだけで、ビクビクっと警戒してしまうんです。
使い方は本当に簡単。
使用済みの猫砂を、アライグマが来そうな場所にパラパラっとまくだけ。
これだけで、「ここには怖い猫がいるぞ!」とアライグマに思わせることができるんです。
ポイントは以下の通りです。
- まく場所:庭の入り口や、家の周りの植え込みの中
- 量の目安:1平方メートルあたり、コップ1杯程度
- 交換頻度:1週間に1回くらい新しいものに交換
- 雨対策:雨に濡れると効果が薄れるので、屋根のある場所がおすすめ
近所に猫を飼っている友達がいれば、おすそ分けしてもらうのもいいですね。
ただし、注意点もあります。
使用済みの猫砂には衛生面でのリスクもあるので、子供やペットが触れない場所に置きましょう。
また、花壇や野菜畑には直接まかないようにしましょう。
「これで我が家はアライグマお断り!」って感じですね。
でも、この方法だけに頼らず、他の対策と組み合わせるのがベストです。
使用済み猫砂、意外だけど効果的なアライグマ撃退法。
試してみる価値ありですよ!
風鈴の音で「不規則な警戒音」を発生させる技
風鈴の音を利用すれば、アライグマを警戒させる不規則な音を簡単に作り出せます。「えっ、風鈴でアライグマが逃げるの?」って思いましたよね。
実は、アライグマは予期せぬ音にとても敏感なんです。
風鈴のチリンチリンという不規則な音が、アライグマをビクッとさせるんです。
設置方法は本当に簡単。
以下の手順で準備しましょう。
- 風鈴を購入する(金属製がおすすめ)
- アライグマが来そうな場所を選ぶ
- 風鈴を吊るす(地面から1.5〜2メートルくらいの高さ)
- 風通しの良い場所を選んで設置する
実は、金属製の風鈴が最も効果的です。
高い音と低い音が混ざった複雑な音色が、アライグマをより警戒させるんです。
注意点もいくつかあります。
- 音量調整:近所迷惑にならない程度の音量に調整する
- 複数設置:庭の入り口や家の周りなど、複数箇所に設置するとより効果的
- 定期的なメンテナンス:埃を落とし、音が鳴りやすいように調整する
そう、風鈴はアライグマ対策だけでなく、季節感も演出できる一石二鳥のアイテムなんです。
ただし、風のない日は効果が薄れるので、他の対策と組み合わせるのがおすすめです。
「よし、これで我が家は完璧防衛だ!」って自信が持てますよ。
風鈴の音、意外と強力なアライグマ撃退法です。
さっそく試してみてはいかがでしょうか?
ソーラーライトで「夜間の突然照明」を実現する方法
ソーラーライトを使えば、夜間にアライグマを驚かせる突然の照明を実現できます。「えっ、ただの庭灯でアライグマが逃げるの?」って思いましたよね。
実は、アライグマは急な明るさの変化にとても敏感なんです。
ソーラーライトのパッと付く光が、アライグマをビックリさせるんです。
設置方法は本当に簡単。
以下の手順で準備しましょう。
- 動きセンサー付きのソーラーライトを購入する
- 日中に十分な日光が当たる場所を選ぶ
- アライグマが来そうな場所に設置する
- センサーの向きと感度を調整する
実は、LEDライトが最もおすすめです。
明るくて省電力、そして寿命も長いんです。
効果を高めるポイントはこんな感じです。
- 複数設置:庭の入り口や家の周りなど、複数箇所に設置するとより効果的
- 高さの調整:地面から1.5〜2メートルくらいの高さに設置すると、アライグマの目線に近くなります
- 定期的な清掃:ソーラーパネルの埃を落として、充電効率を保つ
大丈夫です。
最近のソーラーライトは、人の目に優しい暖色系のLEDを使っているものが多いんです。
ただし、雨の日や曇りの日は充電が不十分になる可能性があるので、他の対策と組み合わせるのがベストです。
「よし、これでうちの庭は安全だ!」って自信が持てますよ。
ソーラーライト、エコでお財布にも優しいアライグマ対策です。
ぜひ試してみてください!