アライグマ捕獲器の種類と選び方【箱罠が最も安全】効果的な使用法と4つの設置ポイントを紹介

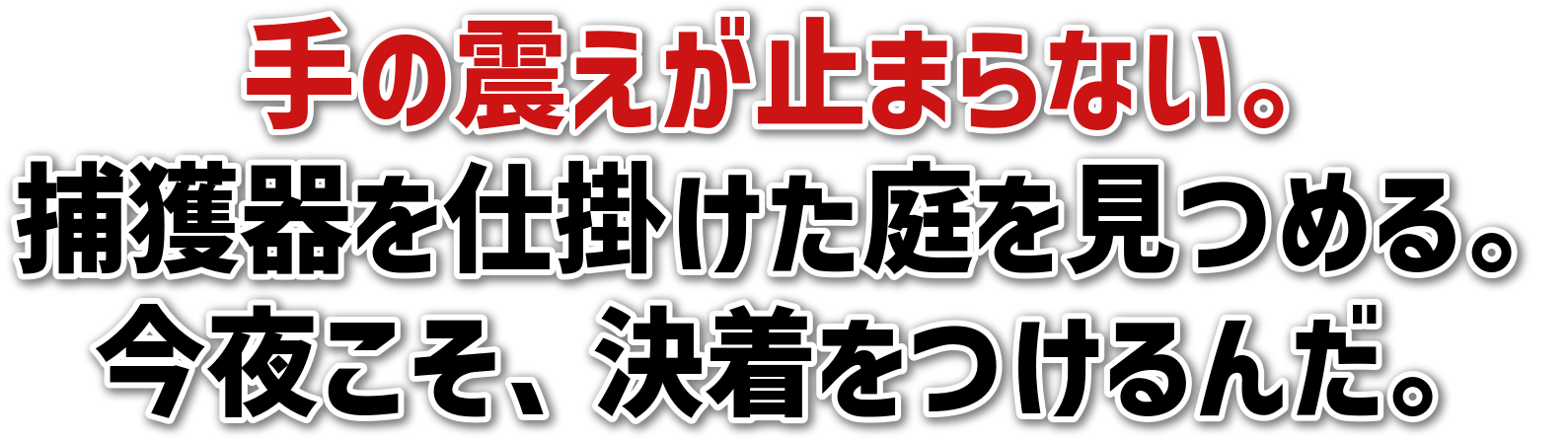
【この記事に書かれてあること】
アライグマの被害に悩まされていませんか?- アライグマ捕獲器には箱罠、はし罠、足くくり罠の3種類がある
- 箱罠が最も安全で扱いやすく、初心者にもおすすめ
- 捕獲器の設置場所と餌選びが効果的な捕獲のカギ
- 定期的な点検とメンテナンスで捕獲器の性能を維持
- 鏡の設置や偽の足跡など、5つの裏技で捕獲率をアップ
捕獲を考えているけれど、どの捕獲器を選べばいいのか迷っているという方も多いはず。
実は、捕獲器の種類によって安全性や効果に大きな違いがあるんです。
正しい選択で、アライグマ問題を解決しましょう!
この記事では、箱罠、はし罠、足くくり罠の特徴を徹底比較。
さらに、捕獲率をアップさせる5つの裏技もご紹介します。
あなたの悩みを解決する最適な捕獲器が、きっと見つかるはずです。
【もくじ】
アライグマ捕獲器の種類と特徴を徹底解説

箱罠が最も安全!人にも動物にも優しい構造
箱罠は、アライグマ捕獲器の中で最も安全な選択肢です。人間にも動物にも優しい構造になっているんです。
箱罠は、その名の通り箱型の構造をしています。
アライグマが中に入ると、扉が閉まって捕獲される仕組みです。
「どうして箱罠が安全なの?」と思う方もいるでしょう。
理由は簡単。
アライグマを完全に閉じ込めることができるからなんです。
箱罠の特徴をご紹介しましょう。
- 金属製で丈夫な作り
- 通気性のある網目構造
- トリガー式の自動閉門装置
- 持ち運びに便利な取っ手付き
「うわっ、噛まれちゃう!」なんて心配はご無用です。
また、アライグマにとってもストレスの少ない方法なんです。
「でも、設置や使い方が難しそう…」なんて心配している方、ご安心ください。
箱罠は初心者でも扱いやすいんです。
設置は平らな場所に置くだけ。
餌を中に入れて、あとは待つだけです。
捕獲後の処理も簡単。
そのまま専門家に引き渡せば、安全に処分してもらえます。
人にも動物にも優しい箱罠。
アライグマ対策の第一歩として、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。
はし罠の特徴と注意点「設置は簡単だが危険性も」
はし罠は、設置が簡単な反面、危険性も伴う捕獲器です。初心者には向かないかもしれません。
はし罠の構造は、ばねの力を利用した挟み込み式。
アライグマが餌を取ろうとすると、パチンと挟まれる仕組みです。
「簡単そうだな」と思った方、ちょっと待ってください。
確かに設置は簡単ですが、扱いには十分な注意が必要なんです。
はし罠の特徴をまとめてみましょう。
- コンパクトで持ち運びやすい
- 設置場所を選ばない
- 強力なばねの力で確実に捕獲
- 誤作動のリスクがある
- アライグマを傷つける可能性がある
でも、その音は危険の始まりかもしれません。
捕獲されたアライグマは、痛みとストレスで凶暴になることも。
「うわっ、噛まれそう!」なんて事態は避けたいですよね。
また、はし罠は他の動物を誤って捕獲してしまう可能性も。
近所の猫ちゃんが被害に遭ったら大変です。
「ごめんね、うちのはし罠で…」なんて謝罪、したくありませんよね。
使用する際は、十分な知識と経験が必要です。
初心者の方は、まずは安全な箱罠から始めるのがおすすめ。
アライグマ対策は、安全第一で進めましょう。
足くくり罠の効果と問題点「捕獲率は高いが傷つく可能性」
足くくり罠は捕獲率が高い反面、アライグマを傷つけてしまう可能性があります。使用には慎重な判断が必要です。
足くくり罠は、地面に設置したワイヤーの輪にアライグマが足を踏み入れると、くるっと締まって捕獲する仕組み。
「なるほど、簡単そうだな」と思った方、ちょっと待ってください。
確かに捕獲率は高いのですが、いくつか問題点があるんです。
足くくり罠の特徴と問題点をまとめてみましょう。
- 設置が比較的容易
- 広範囲に設置可能
- 捕獲率が高い
- アライグマを傷つける可能性がある
- 他の動物を誤って捕獲する危険性
- 法律で使用が制限されている地域がある
それはアライグマにとって恐怖の始まりかもしれません。
足を傷つけられたアライグマは、痛みとストレスで暴れる可能性が。
「キーッ!」という悲鳴が聞こえてきそうです。
また、足くくり罠は他の動物も捕獲してしまう可能性が高いんです。
「あれ?うちの犬が帰ってこない…」なんて事態は避けたいですよね。
さらに、地域によっては法律で使用が制限されていることも。
「知らなかったでは済まされません」と言われかねません。
使用を検討する際は、まず地域の法律を確認し、十分な知識と経験を持つことが大切。
初心者の方は、安全な箱罠から始めるのがおすすめです。
アライグマ対策は、動物への配慮と法令遵守を忘れずに。
捕獲器の大きさ選び「アライグマの体格に合わせて」
捕獲器の大きさ選びは、アライグマの体格に合わせることが重要です。適切なサイズを選ぶことで、捕獲の成功率が大幅に上がります。
アライグマの体格は、想像以上に大きいんです。
体長は40〜70センチ、体重は4〜10キロほど。
「えっ、そんなに大きいの?」と驚く方も多いでしょう。
この体格に合わせて、捕獲器を選ぶ必要があるんです。
捕獲器の大きさ選びのポイントをまとめてみましょう。
- 長さ:最低でも80センチ以上
- 幅:25〜30センチ程度
- 高さ:30〜35センチ程度
- 入り口の大きさ:20センチ×20センチ程度
- 重量:持ち運びやすい10キロ以下がおすすめ
そのとおりです。
アライグマがリラックスして入れる大きさが理想的。
また、捕獲器の重量も考慮しましょう。
「うーん、重たくて持ち上がらない」なんて状況は避けたいですよね。
設置や移動のしやすさを考えると、10キロ以下のものがおすすめです。
捕獲器選びは、アライグマとのかけひきとも言えます。
大きさを間違えると、「あれ?全然捕まらないな」なんてことに。
適切なサイズを選んで、効果的な対策を進めましょう。
捕獲器の設置場所「アライグマの侵入経路を見極めて」
捕獲器の設置場所は、アライグマの侵入経路を見極めることが肝心です。適切な場所に設置することで、捕獲の成功率が格段に上がります。
アライグマは、意外と決まったルートを使うんです。
「へえ、そうなんだ」と思った方、その習性を利用しましょう。
侵入経路を見極めて、そこに捕獲器を置くのが効果的なんです。
アライグマの侵入経路と捕獲器の設置場所のポイントをご紹介します。
- 屋根や壁の隙間:建物への主な侵入口
- 木の近く:木登りが得意なアライグマの通り道
- 水場の周辺:飲み水を求めてよく来る場所
- ゴミ置き場:食べ物を探しに来ることが多い
- 果樹や菜園の近く:食べ物が豊富な場所
アライグマの足跡や糞、物を荒らした跡などがあれば、そこは侵入経路の可能性大。
そういった場所に捕獲器を設置しましょう。
また、設置する際は周囲の環境にも注意が必要です。
「ガタン!」という音で捕獲器が倒れてしまっては元も子もありません。
平らで安定した場所を選びましょう。
そして、人や他の動物が誤って捕獲されないよう、設置場所には十分注意が必要です。
「あれ?隣の犬が捕まっちゃった…」なんて事態は避けたいですよね。
適切な場所に設置することで、アライグラさんとのかけひきに勝利できます。
侵入経路をよく観察して、ベストな設置場所を見つけましょう。
効果的な捕獲器の選び方と使用方法

家の周りvs畑や果樹園「場所に適した捕獲器選び」
場所によって適した捕獲器は異なります。家の周りなら箱罠、広い畑や果樹園では複数の罠を組み合わせるのが効果的です。
家の周りでアライグマ対策をする場合、安全性が何より大切です。
「子どもやペットが近くにいるから、危険な罠は使いたくないな…」そんな不安がある方も多いでしょう。
そんな時は箱罠がおすすめです。
箱罠の特徴をまとめてみましょう。
- 安全性が高い
- 設置が簡単
- 周囲への影響が少ない
- 捕獲したアライグマを傷つけにくい
「広すぎて1つの罠じゃカバーできないよ」そんな声が聞こえてきそうです。
そんな時は複数の罠を組み合わせるのが効果的。
箱罠と足くくり罠を適切に配置することで、広範囲をカバーできます。
ただし、足くくり罠を使う際は注意が必要です。
「ガシャッ」という音とともにアライグマが捕まりますが、傷つける可能性もあるんです。
使用する際は十分な知識と経験が必要です。
場所に合わせて適切な捕獲器を選ぶことで、効果的なアライグマ対策ができます。
家の周りなら安全第一、広い農地なら効率重視、というように使い分けてみてはいかがでしょうか。
箱罠vs足くくり罠「複数捕獲にはどちらが向いている?」
複数のアライグマを捕獲する場合、箱罠の方が適しています。安全性が高く、アライグマへのストレスも少ないんです。
「たくさんのアライグマがいるんだけど、一度にたくさん捕まえられないかな」そんな悩みを抱えている方も多いでしょう。
そんな時は箱罠がおすすめです。
箱罠と足くくり罠の比較をしてみましょう。
- 安全性:箱罠〇 足くくり罠×
- 複数捕獲:箱罠〇 足くくり罠×
- アライグマへのストレス:箱罠△ 足くくり罠×
- 設置の簡易さ:箱罠〇 足くくり罠△
- 捕獲効率:箱罠〇 足くくり罠△
「ガチャン」という音と共に扉が閉まり、中にいるアライグマたちを閉じ込めます。
アライグマたちは互いの存在に安心感を覚え、比較的落ち着いた状態でいられるんです。
一方、足くくり罠は1匹ずつしか捕獲できません。
「キーッ」という鳴き声を上げて暴れる可能性も高く、周囲のアライグマを警戒させてしまいます。
また、箱罠は捕獲したアライグマを傷つけにくい構造になっています。
「かわいそうだけど、捕まえないといけないんだよね…」そんな気持ちの方にも、箱罠なら安心して使っていただけます。
複数のアライグマを捕獲する場合は、安全性と効率を考えて箱罠を選びましょう。
アライグマにも優しく、効果的な対策ができますよ。
餌の選び方と量「匂いの強さと新鮮さがカギ!」
アライグマを効果的に誘引するには、匂いの強い新鮮な餌を適量使うのがポイントです。魚や果物、ピーナッツバターなどが特に効果的です。
「どんな餌を使えばいいの?」「量はどれくらい?」そんな疑問を持つ方も多いでしょう。
実は、餌選びと量の調整が捕獲成功の大きなカギなんです。
効果的な餌と適切な量について、まとめてみましょう。
- 魚(特にサバやイワシ):強い匂いで誘引力抜群
- 果物(リンゴやバナナ):甘い香りがアライグマを引き寄せる
- ピーナッツバター:粘着性があり、長時間香りが持続
- 量の目安:ゴルフボール大(直径約4cm)
- 設置位置:捕獲器の奥に置く
ピーナッツバターは粘着性があるので、アライグマが簡単に持ち去れないのもポイントです。
量は多ければいいというものではありません。
「たくさん置いておけば絶対捕まるはず!」なんて考えちゃダメ。
多すぎると、アライグマが罠に入らずに外から餌を取ろうとしてしまうんです。
餌は捕獲器の奥に置くのが効果的。
アライグマが餌を取ろうとして奥に進むうちに、トリガーを踏んで捕獲される仕組みです。
また、餌の鮮度も重要です。
「ちょっと古くなったけど、まだ大丈夫かな?」なんて考えずに、できるだけ新鮮な餌を使いましょう。
特に暑い季節は毎日交換するのがベストです。
適切な餌選びと量の調整で、アライグマ捕獲の成功率がグンと上がります。
匂いの強い新鮮な餌を、ゴルフボール大の量で試してみてください。
捕獲器の点検・メンテナンス「定期的な清掃が重要」
捕獲器の性能を維持するには、定期的な点検とメンテナンスが欠かせません。特に使用前後の確認と清掃が重要です。
「せっかく設置したのに、うまく作動しなかった…」そんな経験をした方もいるかもしれません。
実は、捕獲器の不調は適切なメンテナンスで防げることが多いんです。
捕獲器の点検・メンテナンスのポイントをまとめてみましょう。
- 使用前:破損や変形がないか確認
- 使用後:汚れを落とし、十分に乾燥させる
- 定期的に:可動部分に注油
- 捕獲成功後:徹底的な洗浄と消毒
- 保管時:湿気のない場所で保管
「ガタガタ」と音がしたり、「グラグラ」と不安定だったりしないか確認しましょう。
トリガー部分がスムーズに動くかも要チェックです。
使用後は必ず清掃を。
「ちょっと汚れただけだから大丈夫」なんて油断は禁物です。
アライグマの体臭や餌の残りが付着していると、次の捕獲の邪魔になってしまいます。
捕獲に成功したら、より丁寧な洗浄と消毒が必要です。
「臭いが取れない!」そんな時は、重曹水での洗浄がおすすめ。
消毒には薄めた塩素系漂白剤が効果的です。
定期的な注油も忘れずに。
「キーキー」という音がしたら要注意。
可動部分がスムーズに動くよう、適量の油を差しましょう。
そして保管時は、湿気のない場所を選びます。
「さび付いちゃった…」なんてことにならないよう、乾燥した場所で保管してください。
こまめな点検とメンテナンスで、捕獲器の性能を長く保つことができます。
効果的なアライグマ対策のために、定期的なケアを心がけましょう。
安全な取り扱い方「素手での接触は絶対NG!」
捕獲器の安全な取り扱いは、何よりも大切です。特に、捕獲されたアライグマには絶対に素手で触れないでください。
「捕まえたけど、この後どうすればいいの?」そんな疑問を持つ方も多いでしょう。
でも、ちょっと待ってください。
アライグマとの接触には大きな危険が潜んでいるんです。
安全な取り扱いのポイントをまとめてみましょう。
- 捕獲器の設置:安定した平らな場所を選ぶ
- 餌の設置:長い棒などを使い、手を入れない
- 捕獲確認:安全な距離から目視で行う
- 移動時:厚手の手袋を着用し、慎重に
- 捕獲後:専門家に連絡し、適切な処置を依頼
「ガタン」と音がして倒れてしまっては元も子もありません。
安定した平らな場所を選び、がっちりと固定します。
餌を設置する時も注意が必要です。
「ちょっとだけなら大丈夫」なんて考えは危険。
長い棒や専用の道具を使って、絶対に手を捕獲器の中に入れないでください。
捕獲できたかどうかの確認は、安全な距離から行います。
「近づいて確認しなきゃ」なんて考えは捨ててください。
アライグマは予想以上に素早く攻撃的です。
もし捕獲器を移動する必要がある場合は、必ず厚手の手袋を着用してください。
「ちょっとだけだから素手でいいや」は絶対NG。
思わぬケガや病気の感染を防ぐためです。
そして、捕獲に成功したら、すぐに専門家に連絡しましょう。
「自分で何とかできるかな」なんて考えはやめてください。
適切な処置には専門的な知識と経験が必要なんです。
安全第一を心がけることで、効果的なアライグマ対策ができます。
常に慎重に、そして専門家の助言を仰ぎながら進めていきましょう。
アライグマ捕獲の効果を高める裏技と注意点

捕獲器内に鏡を設置「好奇心を刺激して捕獲率アップ!」
捕獲器内に鏡を設置すると、アライグマの好奇心を刺激して捕獲率が上がります。この意外な裏技で、捕獲の効果をぐっと高められるんです。
アライグマって、とっても好奇心旺盛な動物なんです。
「キラキラ光るものが大好き!」というわけです。
そこで登場するのが、鏡を使った裏技。
捕獲器の中に小さな鏡を置くだけで、アライグマの興味をグッと引くことができるんです。
鏡の効果をさらに高める方法をご紹介しましょう。
- 鏡のサイズは手のひらサイズがおすすめ
- 捕獲器の奥に設置すると効果的
- 鏡の角度を少し傾けると光の反射が増える
- 複数の小さな鏡を使うとより効果的
実は、アライグマは自分の姿を鏡に映して認識できないんです。
「あれ?何か動いてる!」と思って近づいてくるわけです。
ただし、注意点もあります。
鏡はしっかり固定しましょう。
「ガシャン!」と音がしたら、アライグマが警戒してしまいます。
また、鋭利な破片で怪我をしないよう、安全な素材の鏡を選びましょう。
この裏技、意外と知られていないんです。
でも、試してみると「えっ、こんなに簡単に捕まるの?」って驚くかもしれません。
アライグマの好奇心を利用した、賢い捕獲方法と言えるでしょう。
ぜひ試してみてくださいね。
トウモロコシの粉で誘引「匂いで寄せ付ける効果的な方法」
トウモロコシの粉を捕獲器の周りに撒くと、その匂いでアライグマを効果的に誘引できます。この意外な裏技で、捕獲の成功率がぐんと上がるんです。
アライグマって、実はすごく嗅覚が鋭いんです。
「おいしそうな匂いがする!」って遠くからでも感じ取れちゃうんです。
そこで活躍するのが、トウモロコシの粉。
アライグマが大好きな匂いで、ついつい寄ってきちゃうんです。
トウモロコシの粉の効果的な使い方をご紹介しましょう。
- 粉は細かいものを選ぶ(匂いが広がりやすい)
- 捕獲器の周りに円を描くように撒く
- 風向きを考えて撒く場所を決める
- 雨に濡れないよう、屋根のある場所がベスト
- 定期的に新しい粉に交換する
でも、この方法、実はすごく効果的なんです。
アライグマは匂いに誘われて近づいてきて、そのままスルスルっと捕獲器の中に入っちゃうんです。
ただし、注意点もあります。
トウモロコシの粉を使うときは、周りの環境にも気を付けましょう。
「他の動物も寄ってきちゃった!」なんてことにならないよう、近隣の状況をよく確認してくださいね。
この裏技、意外と知られていないんです。
でも、試してみると「こんなに簡単に寄ってくるなんて!」って驚くかもしれません。
アライグマの鋭い嗅覚を利用した、賢い誘引方法と言えるでしょう。
ぜひ、お試しあれ!
偽の足跡で警戒心を低下「アライグマの習性を利用」
捕獲器の周りにアライグマの足跡サイズの偽の足跡をつけると、警戒心を低下させることができます。この意外な裏技で、捕獲の成功率がぐっと上がるんです。
アライグマって、実はすごく警戒心が強い動物なんです。
「ここ、安全かな?」って、いつもキョロキョロしながら歩いているんです。
でも、同じ仲間の足跡を見つけると、「あ、ここは大丈夫なんだ!」って安心しちゃうんです。
その習性を利用するのが、この偽の足跡作戦なんです。
偽の足跡を効果的につける方法をご紹介しましょう。
- 足跡の大きさは約5〜7センチが目安
- 捕獲器に向かって歩いてきたような配置に
- 湿った土や砂の上につけるとくっきり残る
- 複数の個体がいるように、サイズを少し変える
- 餌のある方向に足跡を向ける
でも、この方法、実はすごく効果的なんです。
アライグマは足跡を見て安心し、警戒心を解いてスイスイと捕獲器に近づいてくるんです。
ただし、注意点もあります。
あまりに完璧すぎる足跡は逆に不自然です。
「ちょっと、これ怪しくない?」ってアライグマに気づかれちゃうかもしれません。
自然な感じを心がけましょう。
この裏技、意外と知られていないんです。
でも、試してみると「こんなに簡単に入ってくるなんて!」って驚くかもしれません。
アライグマの習性を上手く利用した、賢い捕獲方法と言えるでしょう。
ぜひ、お試しあれ!
湿った砂で行動パターンを分析「足跡調査で効率アップ」
捕獲器の周囲に湿った砂を撒くと、アライグマの足跡が残りやすくなり、その行動パターンを分析できます。この意外な裏技で、捕獲の効率がぐんと上がるんです。
アライグマって、実は結構習慣的な動物なんです。
「いつもの道を通ろう」って、同じルートを使うことが多いんです。
その習性を利用するのが、この湿った砂作戦。
足跡をはっきり残すことで、アライグマの行動を読み解けるんです。
湿った砂を効果的に使う方法をご紹介しましょう。
- 砂は細かいものを選ぶ(足跡がくっきり残る)
- 捕獲器の周りに幅50センチほどの帯状に撒く
- 厚さは2〜3センチ程度が適当
- 毎日朝晩チェックして足跡を確認
- 雨が降ったら砂を入れ替える
でも、この方法、実はすごく効果的なんです。
アライグマの行動パターンが分かれば、捕獲器の設置場所や時間を最適化できるんです。
ただし、注意点もあります。
砂が乾燥しすぎると足跡が残りにくくなります。
「あれ?足跡が見えない…」なんてことにならないよう、適度な湿り気を保つことが大切です。
この裏技、意外と知られていないんです。
でも、試してみると「こんなにはっきり行動が分かるなんて!」って驚くかもしれません。
アライグマの習性を上手く利用した、賢い分析方法と言えるでしょう。
ぜひ、お試しあれ!
暗視カメラの活用「夜行性のアライグマの動きを把握」
捕獲器の近くに暗視カメラを設置すると、夜行性のアライグマの行動パターンを詳しく把握できます。この意外な裏技で、捕獲の成功率がぐっと上がるんです。
アライグマって、夜の行動が活発な動物なんです。
「真っ暗な夜でもスイスイ動き回れる」っていう特徴があるんです。
そんなアライグマの動きを見逃さないのが、この暗視カメラ作戦。
夜の行動を克明に記録できるんです。
暗視カメラを効果的に使う方法をご紹介しましょう。
- カメラは防水タイプを選ぶ(屋外でも使える)
- 捕獲器から3〜5メートル離れた場所に設置
- 木の枝や柱にしっかり固定する
- バッテリー式なら電源の心配なし
- 動体検知機能付きだと無駄な撮影を避けられる
でも、この方法、実はすごく効果的なんです。
アライグマがいつ、どんなルートで近づいてくるのか、はっきり分かるんです。
ただし、注意点もあります。
カメラの赤外線が強すぎると、アライグマが警戒してしまうことがあります。
「あれ?なんか光ってる…」って気づかれちゃうかもしれません。
低光度のものを選ぶのがポイントです。
この裏技、意外と知られていないんです。
でも、試してみると「こんなにはっきりアライグマの行動が分かるなんて!」って驚くかもしれません。
夜行性のアライグマの特性を上手く利用した、賢い観察方法と言えるでしょう。
ぜひ、お試しあれ!