アライグマが罠にかからない原因と対処法【餌の選択が重要】捕獲効率を上げる5つの設置テクニック

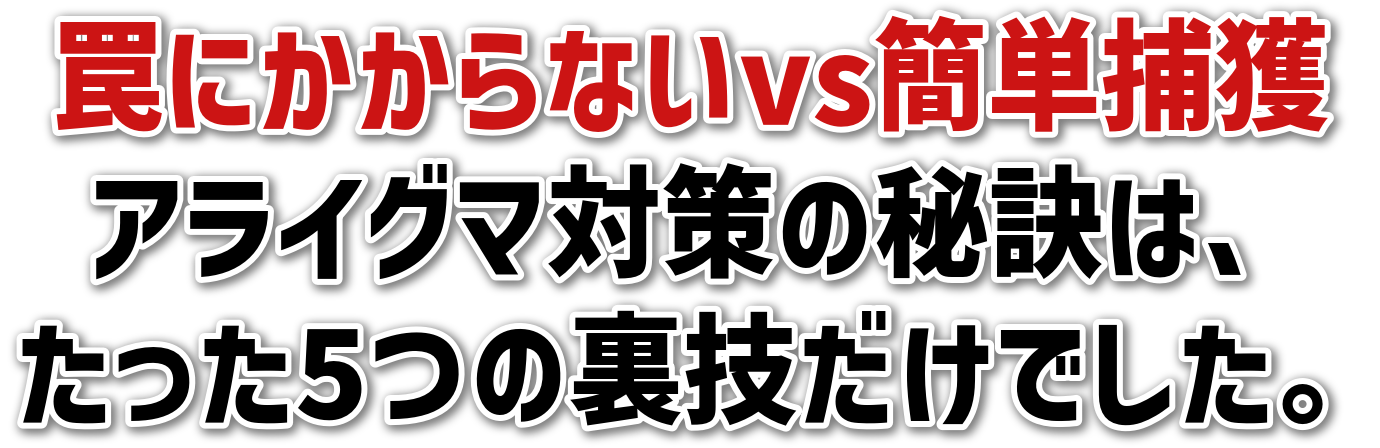
【この記事に書かれてあること】
アライグマの罠にかからない…そんな悩みを抱えていませんか?- 箱罠の選択がアライグマ捕獲の成功率を左右
- アライグマの通り道を見極めた設置場所が重要
- 餌の種類と量で誘引効果に大きな差
- 1日2回の点検で捕獲チャンスを逃さない
- 人間の匂いをつけない注意が必要
- 5つの裏技を活用して捕獲率をアップ
実は、罠の設置にはちょっとしたコツがあるんです。
餌の選び方や設置場所、点検頻度など、意外と見落としがちなポイントがたくさん。
でも、大丈夫。
この記事では、アライグマ捕獲の失敗原因と、それを解決する効果的な対策法をご紹介します。
さらに、捕獲率を劇的にアップさせる5つの裏技も。
これであなたも、アライグマ対策のプロに!
さあ、一緒にアライグマフリーな環境を目指しましょう。
【もくじ】
アライグマが罠にかからない原因とは?適切な対策で捕獲率アップ

罠の選び方!アライグマに効果的な「箱罠」の特徴
アライグマ捕獲には「箱罠」が最適です。安全性が高く、捕獲効率も抜群なんです。
箱罠は、アライグマを生きたまま捕まえられる優れものです。
「どんな特徴があるの?」と思った方に、箱罠の魅力をお伝えしましょう。
まず、大きさが重要です。
成獣のアライグマを捕まえるなら、幅30センチ、奥行80センチ、高さ30センチくらいの箱罠がぴったり。
「えっ、そんなに大きいの?」と驚く方もいるかもしれません。
でも、アライグマは意外と大きいんです。
材質は、金属製がおすすめです。
木製やプラスチック製もありますが、耐久性で劣ります。
「ガリガリ」と噛み砕かれちゃう可能性も。
金属製なら、アライグマの鋭い歯にも負けません。
箱罠の特徴をまとめると、こんな感じです。
- アライグマを生きたまま捕獲できる
- 適切なサイズで快適に捕獲
- 金属製で耐久性抜群
- 設置や移動が比較的簡単
- 他の動物を誤って捕獲しても安全に解放可能
確かに初期投資は必要ですが、長期的に見れば経済的。
何度も使えるので、コスパは抜群です。
箱罠を選ぶときは、重さにも注目してください。
軽すぎると風で飛ばされたり、アライグマに動かされたりする可能性があります。
適度な重さがあれば、安定して設置できますよ。
設置場所のコツ!「アライグマの通り道」を見極めよう
罠の設置場所こそが、捕獲成功の鍵を握っています。アライグマの「お気に入りルート」を見つけることが大切なんです。
アライグマは賢い動物です。
彼らは決まった経路を通ることが多いんです。
「じゃあ、どこに設置すればいいの?」そんな疑問にお答えしましょう。
まず、足跡や糞を探してみてください。
これらは、アライグマが頻繁に通る場所のサインです。
「えっ、糞を探すの?」と思った方もいるでしょう。
でも、これが一番確実な方法なんです。
次に、建物の隅や塀、柵に沿った場所も要チェック。
アライグマはこういった場所を移動経路として好みます。
「カサカサ」と物音がしたら、そこかもしれません。
効果的な設置場所をまとめると、こんな感じです。
- 足跡や糞が見られる場所
- 建物の隅や出入り口付近
- 塀や柵に沿った場所
- 果樹園や畑の周辺
- 水場の近く
出入り口をアライグマの移動経路に向け、少し斜めに設置すると捕獲率がアップします。
「なぜ斜めなの?」と思った方、実はアライグマは真正面から入るのを警戒するんです。
複数の罠を設置する場合は、最低10メートル以上間隔を空けましょう。
「近くに置いた方が効果的じゃない?」と思うかもしれません。
でも、罠が密集していると、アライグマが警戒心を強めてしまうんです。
最後に、周囲の環境にも注意を。
明るすぎる場所や人の往来が激しい場所は避けましょう。
アライグマは人間を警戒するので、ひっそりとした場所の方が効果的です。
餌選びの秘訣!「魚の缶詰」vs「果物」どちらが効果的?
餌選びは、アライグマ捕獲の成功率を大きく左右します。魚の缶詰と果物、どちらがより効果的なのか、徹底的に比較してみましょう。
まず、魚の缶詰です。
これはアライグマにとって、とっても魅力的な香りを放ちます。
「くんくん」と嗅ぎつけて、どんどん近づいてくるんです。
特にサバやツナの缶詰が効果的。
「でも、臭くないの?」と心配する方もいるでしょう。
確かに人間には強烈な臭いですが、アライグマにとっては「ごちそう」の香りなんです。
一方、果物もアライグマを引き寄せる強い味方です。
特に甘い香りの果物が効果的。
イチゴやスイカは、アライグマの大好物なんです。
「へえ、意外と果物好きなんだ」と思った方も多いのでは?
それぞれの特徴をまとめると、こんな感じです。
- 魚の缶詰:
- 強い匂いで遠くからアライグマを引き寄せる
- 長期保存が可能
- 天候に左右されにくい
- 果物:
- 甘い香りでアライグマを誘惑
- 自然な餌なので警戒されにくい
- 季節によって新鮮なものが入手可能
実は、両方使うのが一番効果的なんです。
魚の缶詰で遠くから引き寄せ、果物で罠の中へ誘い込む。
これが、プロの技なんです。
餌の量も重要です。
小さじ1〜2杯程度の少量で十分。
「少なすぎない?」と思うかもしれません。
でも、多すぎると罠の外で満足してしまい、中に入らなくなっちゃうんです。
最後に、鮮度にも気を付けましょう。
毎日新鮮な餌に交換するのが理想的です。
アライグマは鼻が良いので、古くなった餌には興味を示さなくなってしまいます。
罠の管理方法!「1日2回の点検」で捕獲チャンスを逃すな
罠の管理は、アライグマ捕獲の成功率を大きく左右します。特に重要なのが、1日2回の点検。
これで捕獲チャンスを逃さず、効率よく対策できるんです。
なぜ1日2回なのか、疑問に思う方もいるでしょう。
「そんなに頻繁に見る必要あるの?」という声が聞こえてきそうです。
実は、アライグマは夜行性。
夕方から明け方にかけて活発に活動するんです。
だから、朝と夕方の2回点検するのが理想的なんです。
点検時のポイントをまとめると、こんな感じです。
- 罠が正しく設置されているか確認
- 餌の状態をチェック(なくなっていたら補充)
- 罠の周辺に不審な痕跡がないか調査
- 捕獲されている場合は適切に対処
- 罠の損傷がないか点検
確かに手間はかかります。
でも、こまめな点検が捕獲成功の近道なんです。
「ガシャン」という音がしたら、アライグマが捕まった合図かもしれません。
長期間使用していない罠を再利用する際は要注意。
錆びや破損がないか、しっかりチェックしましょう。
「ガタガタ」と音がしたら、修理が必要かもしれません。
中性洗剤で洗浄し、よくすすいで乾燥させてから使用するのがコツです。
雨天時の管理も重要です。
防水シートで罠を覆い、餌が濡れないよう工夫しましょう。
「ぐしょぐしょ」になった餌では、アライグマも興味を示しません。
また、排水にも注意が必要。
水たまりができると、アライグマが警戒してしまいます。
最後に、安全面にも気を付けましょう。
アライグマは驚くと攻撃的になることも。
捕獲されているアライグマに近づく際は、十分な距離を保ち、慎重に行動することが大切です。
やってはいけない!「罠に人間の匂いをつける」は逆効果
アライグマ捕獲の大敵、それは「人間の匂い」なんです。罠に人間の匂いをつけてしまうと、せっかくの努力が水の泡に。
なぜなら、アライグマは驚くほど鋭い嗅覚の持ち主だからです。
「えっ、そんなに敏感なの?」と驚く方も多いでしょう。
実は、アライグマの嗅覚は人間の約100倍も優れているんです。
つまり、私たちが気づかない微かな匂いも、アライグマにはバレバレなんです。
人間の匂いがつくと、どんな問題が起きるのでしょうか。
- アライグマが警戒心を強め、罠に近づかなくなる
- 餌に興味を示さなくなる
- 捕獲の成功率が大幅に低下する
- 周辺のアライグマにも警戒心が伝わる
- せっかく準備した罠が無駄になってしまう
大丈夫、対策はあります。
まず、罠を扱うときは必ず手袋を着用しましょう。
ゴム手袋や作業用手袋が適しています。
「面倒くさい」と思うかもしれませんが、これが成功への近道なんです。
次に、罠を設置する前に、土や落ち葉でこすって自然の匂いをつけるのもおすすめです。
「えっ、わざわざ汚すの?」と驚く方もいるでしょう。
でも、これがアライグマを安心させる秘訣なんです。
餌を置くときも注意が必要です。
直接手で触れず、箸やピンセットを使いましょう。
「そこまでする必要ある?」と思うかもしれません。
でも、細かい配慮が大きな違いを生むんです。
最後に、罠の周辺に人間の足跡を残さないよう気を付けましょう。
可能であれば、長い棒などを使って離れた場所から罠を設置するのがベストです。
アライグマを確実に捕獲!罠の効果を高める5つのテクニック

「餌の量」vs「誘引効果」最適なバランスを探れ
餌の量と誘引効果のバランスが、アライグマ捕獲の成功を左右します。多すぎず、少なすぎず、ちょうどいい量が重要なんです。
「たくさん餌を置けば、たくさん捕まえられるんじゃないの?」そう思った方もいるかもしれませんね。
でも、実はそれが大きな間違いなんです。
アライグマは賢い動物です。
餌が多すぎると、「ここは危険かも」と警戒心を抱いてしまいます。
かといって、少なすぎても興味を引けません。
じゃあ、どうすればいいの?
- 小さじ1?2杯程度の餌を用意する
- 罠の奥に餌を置き、入り口付近にも少量をばら撒く
- 餌は毎日新鮮なものに交換する
- 季節によって餌の種類を変える(春は新芽、秋は果物など)
でも、安心してください。
この量が、アライグマを誘い込むのに最適なんです。
餌の種類も重要です。
魚の缶詰やピーナッツバター、果物(特にいちごやすいか)が効果的です。
これらの香りは、アライグマの鼻をくすぐり、「むしゃむしゃ」と食べたくなる衝動を引き起こすんです。
餌の配置にも工夫が必要です。
罠の奥に主な餌を置き、入り口付近に少量をばら撒くことで、アライグマを徐々に誘い込めます。
まるで、宝探しゲームのようですね。
そして、忘れてはいけないのが鮮度です。
古くなった餌はアライグマの興味を引きません。
毎日新鮮な餌に交換することで、「わくわく」するような魅力的な罠になるんです。
「単口の罠」vs「両口の罠」捕獲効率の違いに注目
単口の罠と両口の罠、どちらがアライグマ捕獲に効果的でしょうか?実は、両方に一長一短があるんです。
まず、単口の罠について考えてみましょう。
「シンプルイズベスト」という言葉がありますが、これがぴったり当てはまります。
単口の罠は、構造が単純で設置が簡単。
初心者の方にもおすすめです。
一方、両口の罠はどうでしょうか。
「二兎を追う者は一兎も得ず」なんて言葉がありますが、実はこの罠、二兎どころか多くのアライグマを捕まえる可能性があるんです。
それぞれの特徴をまとめてみましょう。
- 単口の罠:
- 設置が簡単
- 場所を選ばない
- アライグマが警戒しにくい
- 両口の罠:
- 捕獲効率が高い
- 複数のアライグマを一度に捕獲できる可能性がある
- 設置には広いスペースが必要
実は、状況に応じて使い分けるのがコツなんです。
狭い場所や、アライグマの通り道が明確な場合は単口の罠が有効です。
「ガシャン」という音がしたら、きっと捕まえられているはずです。
一方、広い農地や、複数のアライグマが出没する場所では両口の罠が威力を発揮します。
まるで、魚を網で一網打尽にするような感覚ですね。
ただし、両口の罠は設置に広いスペースが必要です。
また、アライグマが警戒しやすいという欠点もあります。
「用意周到」に準備することが大切です。
結局のところ、どちらを選ぶかは状況次第。
でも、両方用意しておけば、まさに「八方美人」ならぬ「八方アライグマ捕獲人」になれるかもしれませんね。
「金属製」vs「プラスチック製」罠の素材で成功率に差が
罠の素材、実はアライグマ捕獲の成功率に大きく影響するんです。金属製とプラスチック製、どちらが効果的なのか、徹底比較してみましょう。
まず、金属製の罠について考えてみましょう。
「鉄は熱いうちに打て」という言葉がありますが、アライグマ捕獲にも鉄(金属)は強い味方になります。
なぜでしょうか?
- 金属製の罠の特徴:
- 耐久性が高い
- アライグマが噛んでも壊れにくい
- 重量があるので安定している
- 長期間使用可能
「軽いは正義」なんて言葉はありませんが、確かに持ち運びは楽ちんです。
- プラスチック製の罠の特徴:
- 軽量で持ち運びが簡単
- 価格が比較的安い
- さびる心配がない
- 柔らかい素材でアライグマにケガをさせにくい
実は、金属製の罠の方が捕獲成功率が高いんです。
なぜかというと、アライグマは歯や爪が鋭く、プラスチック製だと「ガリガリ」と噛み砕いて逃げ出してしまう可能性があるからです。
金属製なら、「カチカチ」と音がしても、びくともしません。
また、金属製の罠は重量があるので、アライグマが暴れても動きません。
プラスチック製だと、「コロコロ」と転がってしまうかもしれません。
ただし、金属製にも欠点はあります。
さびやすいので、使用後はしっかり手入れが必要です。
「さびた罠は半分の罠」なんて言葉はありませんが、効果は半減してしまいます。
結論として、長期的な視点で考えると金属製の罠がおすすめです。
初期投資は少し高くなりますが、耐久性と捕獲効率を考えると、十分元が取れるはずです。
「罠の向き」と「設置角度」で捕獲率が劇的アップ!
罠の向きと設置角度、実はこれがアライグマ捕獲の成功の鍵を握っているんです。ちょっとした工夫で、捕獲率が劇的にアップします。
まず、罠の向きについて考えてみましょう。
「風向きを読む」なんて言葉がありますが、アライグマ捕獲では「通り道を読む」が大切です。
罠の入り口は、アライグマの移動経路に向けて設置するのがポイントです。
でも、ちょっと待ってください。
真正面から罠を置くのは、実は逆効果なんです。
なぜでしょうか?
アライグマは警戒心が強い動物です。
真正面から罠を見ると、「ここは危ないぞ」と警戒してしまいます。
そこで登場するのが、「斜め設置」という秘技です。
罠をアライグマの移動経路に対して、やや斜めに設置してみましょう。
これにより、アライグマは罠を正面から見ることなく、自然に中に入っていくんです。
まるで、気づかないうちに罠にはまってしまう、というわけです。
具体的な設置方法をまとめてみましょう。
- アライグマの移動経路を特定する(足跡や糞を手がかりに)
- 罠の入り口を移動経路に向ける
- 入り口を経路に対して15?30度ほど斜めに設置
- 罠の周囲に自然の枝や葉を置いて、違和感をなくす
- 罠の下に板を敷き、安定させる
でも、これらの小さな工夫が、捕獲率を大きく左右するんです。
また、罠の設置角度も重要です。
地面に対して完全に水平ではなく、わずかに(5度程度)入り口を上げ気味に設置するのがコツです。
これにより、アライグマが罠に入りやすくなり、かつ出にくくなるんです。
さらに、罠の周囲の環境にも注意を払いましょう。
周りに自然の枝や葉を置くことで、罠が目立たなくなります。
アライグマにとっては、ただの自然の一部に見えるわけです。
これらの工夫を組み合わせることで、アライグマ捕獲の成功率が格段に上がります。
まさに、「仕掛け」と「角度」で勝負が決まるんです。
複数の罠を仕掛ける!「最適な間隔」と「配置」のコツ
複数の罠を仕掛けることで、アライグマ捕獲の効率が格段に上がります。でも、ただやみくもに置けばいいというわけではありません。
最適な間隔と配置には、ちょっとしたコツがあるんです。
まず、罠と罠の間隔について考えてみましょう。
「近すぎず、遠すぎず」がポイントです。
具体的には、最低でも10メートル以上空けることをおすすめします。
「えっ、そんなに離す必要があるの?」と思った方もいるでしょう。
実は、罠を近づけすぎると、アライグマが警戒心を強めてしまうんです。
「罠だらけじゃん」と気づかれちゃうわけです。
では、具体的な配置方法を見ていきましょう。
- 罠の間隔は10?20メートルを目安に
- アライグマの通り道に沿って直線的に配置
- 建物の隅や塀沿いなど、アライグマが好む場所を選ぶ
- 水場や餌場の近くにも設置
- 地形を利用して、アライグマの動きを予測
アライグマの動きを予測し、逃げ道をふさぐように罠を配置するんです。
例えば、建物の周りに罠を置く場合は、出入り口や角を中心に配置します。
「ここを通るしかない」という場所を作り出すわけです。
また、地形を利用するのも効果的です。
丘や谷があれば、アライグマはそれに沿って移動します。
その経路上に罠を置けば、捕獲チャンスが大幅に上がります。
さらに、罠の種類を組み合わせるのも一手です。
箱罠と網罠を交互に置くことで、アライグマの好みや警戒心の違いに対応できます。
ただし、注意点もあります。
あまりに多くの罠を一度に設置すると、管理が大変になります。
「目は百個、口は一つ」とまではいきませんが、自分で管理できる数に抑えることが大切です。
結局のところ、複数の罠を仕掛けるコツは、アライグマの習性を理解し、環境に合わせて柔軟に配置すること。
「頭を使って罠を置く」ことで、捕獲効率が劇的にアップするんです。
プロ級の罠テクニック!アライグマを引き寄せる驚きの裏技

「砂の足跡作戦」でアライグマの行動パターンを把握
砂の足跡作戦は、アライグマの行動パターンを知る秘密兵器です。この方法を使えば、罠の設置場所を的確に決められます。
まず、罠の周りに細かい砂を薄く撒きます。
「えっ、そんなことで分かるの?」と思うかもしれませんね。
でも、これがすごく役立つんです。
アライグマは夜行性。
朝起きて砂を見れば、足跡がくっきり。
まるで、アライグマが「ここを通ったよ」と教えてくれているようです。
足跡を見つけたら、次はその向きをチェック。
アライグマがどこから来て、どこへ行ったのか、「ふむふむ」と推理します。
これで、アライグマの通り道が分かるんです。
この作戦のポイントをまとめると:
- 罠の周りに細かい砂を薄く撒く
- 朝、足跡の有無と向きをチェック
- 複数日観察して、パターンを見つける
- 足跡が多い場所に罠を移動させる
雨の日は確かに難しいです。
でも、雨上がりの柔らかい地面なら、逆に足跡がくっきり残ることも。
天気予報をチェックしながら、作戦を立てましょう。
この方法を使えば、アライグマの習性に合わせた罠の配置ができます。
まるで、アライグマの気持ちになって考えるようなものです。
「ここなら絶対に通るはず!」という場所が見えてくるんです。
砂の足跡作戦、ちょっとした手間ですが、捕獲率アップの強い味方になりますよ。
「ピーナッツバター」の塗り方で罠の中へ誘導する方法
ピーナッツバターは、アライグマを罠の中へ誘う魔法の食べ物です。その塗り方次第で、捕獲率がぐんと上がるんです。
まず、なぜピーナッツバターなのか?
それは、強い香りと濃厚な味わいがアライグマを引き寄せるからです。
「えっ、アライグマってピーナッツバター好きなの?」と驚く方もいるでしょう。
実は大好物なんです。
さて、塗り方のコツをお教えしましょう。
- 罠の入り口付近から奥に向かって、少しずつ塗る
- 網目にも薄く塗り、香りを充満させる
- 罠の奥に行くほど、量を増やす
- トリガー(捕獲装置)の近くに一番多く塗る
入り口付近の少量で興味を引き、奥に進むにつれて「もっと食べたい!」という気持ちにさせるわけです。
「でも、べたべたして大変そう…」と思った方、ご心配なく。
小さなヘラや使い捨ての割り箸を使えば、手を汚さずに塗れます。
ここで、ちょっとした裏技。
ピーナッツバターを塗った後、その上からほんの少しだけ砂糖をふりかけてみてください。
甘い香りが加わって、さらに誘引効果がアップするんです。
ただし、注意点も。
ピーナッツバターは腐りやすいので、1日で交換するのがベスト。
「もったいない!」と思っても、古いままだと逆効果になっちゃいます。
この方法を使えば、アライグマは「むしゃむしゃ」と夢中で食べ始め、気づいたときには罠の中。
まさに「甘い罠」というわけです。
「アロマ効果」を活用!ミントの香りでアライグマを誘う
意外かもしれませんが、アライグマはミントの香りに引き寄せられるんです。この「アロマ効果」を活用すれば、捕獲率がぐっと上がります。
「えっ、アライグマって香り好きなの?」と思った方も多いでしょう。
実は、アライグマは嗅覚が非常に優れていて、魅力的な香りには目がないんです。
特にミントは、その清々しい香りがアライグマを引き付けるんです。
では、具体的な使い方を見ていきましょう。
- ミントの生葉か乾燥葉を用意する
- 小さな布袋に入れて、罠の中にぶら下げる
- 罠の周りにもミントを散らばせる
- 2?3日おきに新しいものと交換する
罠の周りから中に向かって、徐々に香りが強くなるようにするんです。
アライグマは「もっといい匂いのする方へ」と誘われるように罠の中へ入っていきます。
「でも、ミントってどこで手に入れるの?」という疑問も出てくるでしょう。
実は、スーパーの野菜コーナーで見つかることも。
庭で育てれば、常に新鮮なミントが使えますよ。
ここで、ちょっとした裏技。
ミントティーのティーバッグを使うのも効果的です。
香りが強くて、扱いやすいんです。
使用済みのティーバッグでもOK。
「もったいない」精神で、一石二鳥ですね。
ただし、注意点も。
雨の日は香りが薄まってしまうので、防水対策が必要です。
小さなビニール袋に入れて穴を開ければ、雨でも香りが漂います。
この「アロマ効果」、意外と強力です。
アライグマは「くんくん」と香りを嗅ぎながら、知らず知らずのうちに罠の中へ。
まるで、香りの魔法にかかったかのようです。
「枝のトンネル」作戦でアライグマの警戒心を解く
「枝のトンネル」作戦は、アライグマの警戒心を巧みにかわす秘策です。この方法を使えば、罠への抵抗感をぐっと下げられます。
アライグマは用心深い動物。
むき出しの罠を見ると「あやしい!」と警戒してしまいます。
でも、自然の中にあるような「トンネル」なら?
そう、警戒心がぐっと下がるんです。
では、具体的な作り方を見ていきましょう。
- 細い枝や葉っぱを集める
- 罠の周りに枝を立てかけ、屋根のように覆う
- 入り口から奥まで、自然なトンネルを作る
- 葉っぱで隙間を埋め、中が見えにくくする
実は、アライグマもこういう空間が大好きなんです。
「わくわく」しながら中に入っていくわけです。
「でも、そんな簡単なもので騙されるの?」と思う方もいるでしょう。
驚くことに、かなり効果があるんです。
アライグマにとっては、ただの自然の一部に見えるからです。
ここで、ちょっとした裏技。
トンネルの中に、アライグマの好物をちりばめてみましょう。
果物の切れ端や、ナッツ類を少しずつ置いていくんです。
まるで、お菓子の家に誘われるヘンゼルとグレーテルのよう。
アライグマは「むしゃむしゃ」と食べながら、どんどん奥へ進んでいきます。
ただし、注意点も。
あまりに不自然なトンネルだと、逆効果。
周りの環境に合わせて、できるだけ自然に見えるよう工夫しましょう。
この「枝のトンネル」作戦、見た目は単純ですが効果は抜群。
アライグマは「ここなら安全」と思い込んで入ってきます。
そして気づいたときには、もう罠の中。
まさに自然を味方につけた作戦、というわけです。
「鏡」の活用法!仲間がいると勘違いさせる心理テク
鏡を使った心理テクニック、実はアライグマ捕獲の強力な武器になるんです。この方法を使えば、アライグマを巧みに罠に誘い込めます。
アライグマは群れで行動する習性があります。
仲間がいると安心するんですね。
ここで登場するのが「鏡」。
自分の姿を見て「仲間がいる!」と勘違いさせる作戦です。
具体的な使い方を見ていきましょう。
- 小さな鏡(手鏡サイズ)を用意する
- 罠の奥の壁に鏡を取り付ける
- 鏡の角度を調整し、入り口から見えるようにする
- 鏡の周りを枝や葉で自然に隠す
でも、これが意外と効果的なんです。
アライグマは鏡に映る自分の姿を見て「あ、仲間だ!」と安心して中に入ってくるんです。
ここで、ちょっとした裏技。
鏡の前に餌を置いてみましょう。
アライグマは「仲間と一緒に食事」と思い込んで、警戒心なく食べ始めます。
そして、気づいたときには罠の中。
まさに「目は心の窓」ならぬ「鏡は罠の窓」というわけです。
ただし、注意点も。
鏡が光って不自然に目立つと、逆効果。
周りの環境に溶け込むよう、枝や葉で上手に隠すのがコツです。
この方法、ちょっとした工夫で捕獲率がぐっと上がります。
アライグマの社会性を逆手に取った、まさに「目からウロコ」の作戦。
試してみる価値は十分にありますよ。
「鏡よ鏡、誰が一番アライグマを捕まえられる?」その答えは、この心理テクを使いこなしたあなたかもしれません。